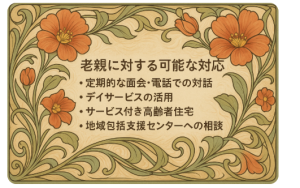 「施設入所だけが答えではない」──老親の介護を考えるときに大切なこと
「施設入所だけが答えではない」──老親の介護を考えるときに大切なこと
高齢化社会の進展に伴い、多くのご家庭で「年老いた親の介護」という課題に直面します。認知症の兆候や転倒リスクの増加などによって、子どもたちは「施設に入れた方が安全なのでは」と考えがちです。しかし、施設入所が必ずしも最適な選択肢とは限りません。この記事では、ネットに紹介されたあるご家庭の事例を通じて、介護における多様な選択肢とケアの在り方を、眼科医の視点も交えて考えていきます。
「帰りたい」と涙する父の声──安心だけでは満たされない心
あるご家庭では、要介護2とされる78歳の父が、一人暮らしの不安から施設入所を決めました。設備が整い、スタッフの対応にも問題はなかったにもかかわらず、入所からわずか3日後、父は「帰りたい」と涙ながらに長男に電話をかけてきました。面会に行った長男が見たのは、テレビもついていない静かな個室で、虚ろな目をしている父の姿でした。人との会話がほとんどない孤立した環境が、目に見えない大きなストレスとなっていたのです。ゴールドオンライン
安心だけでは救えない孤独と不安
施設への入所は、確かに身体面の安全を守る選択です。しかし、家族との絆や日常のぬくもりを失った孤独は、精神的な衰えを加速させることがあります。特に認知症の初期段階で介護度が軽めの方ほど、「やることがない」「誰とも話せない」不安を深く感じやすいという傾向も指摘されています。ゴールドオンライン
眼科医の視点から見た「見えることの大切さ」
私は眼科医として、多くの高齢患者さまに接しています。身体の見え方の変化は、視覚的な安全だけでなく、心のつながりにも大きく影響を与えます。
-
老人性白内障:進行すると視界がぼやけ、足元が見えにくくなるため、転倒リスクが高まります。
-
緑内障:視野狭窄が進行していても、矯正視力が良好なため気づかれにくく、「行が飛んで読めない」「駅のホームで段差に気づかなかった」など日常での困難につながることも少なくありません。
これらの視覚障害がある高齢者は、生活の質が低下し、介護度の進行につながる可能性があります。身体的な安全の確保と同時に、「見える」という安心を支えてあげることが重要です。
家族にできる温かな支援とは?
施設入所が安心の選択に見えても、心のケアを忘れてはなりません。実際に先のご家庭では、施設を一時退所して訪問介護を受け、週2回のデイサービスを利用することに。結果、父親の表情は穏やかに戻り、安心と自立を取り戻し多としていました。
-
定期的な面会・電話での対話:週に1度声や顔を見せるだけで、不安は大きく和らぎます。
-
デイサービスの活用:自宅を中心に人との交流をもつことで、孤立感の予防につながります。
-
サービス付き高齢者住宅(サ高住):自由度が高く、自立度のある高齢者に適しています。
-
地域包括支援センターへの相談:地域資源の活用や精神的ケアについて、継続的な支援が受けられます。
終わりに──「心の安心」こそが支えになる
老親の介護に直面すると、「施設に入れれば安心」と思いたくなるのは自然な感情です。しかし本当に必要なのは、どの環境にあっても「あたたかな存在を感じること」です。
身体のケアと同じように、「視えることの安心」「声やぬくもりを届けること」が、高齢者の生活の質を支える力になります。ぜひ多様な選択肢を考慮しながら、最もその方らしい支え方を見つけていきましょう。
参考文献
・「『帰りたい』要介護2の父、〈入所3日〉で泣きながら電話…面会に行った長男が『言葉を失った理由』」『THE GOLD ONLINE』、2025年8月19日配信 ゴールドオンライン+5ゴールドオンライン+5news.livedoor.com+5




コメント