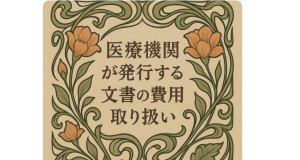 今月の「東京保険医新聞 2025年9月15日号」に医療機関が発行する文書の費用取り扱いという記事が出ています。この記事内容をベースに、
今月の「東京保険医新聞 2025年9月15日号」に医療機関が発行する文書の費用取り扱いという記事が出ています。この記事内容をベースに、
6つの項目(①〜⑥)ごとに整理してまとめました。ご質問は医院の受付担当者にお聞きください。
医療機関が発行する文書の費用取り扱いについて
―眼科医院から患者さんへのご案内―
医療機関では日常診療のほかに、患者さんや各種機関から依頼されて診断書・証明書・意見書などの文書を作成することが少なくありません。先日の東京保険医新聞でも「医療機関が発行する文書の費用の取り扱い」が整理されていました。ここでは眼科医院の立場から、どの文書が自費で、どの文書が保険や公費で扱われるのかを、わかりやすくご説明します。
① 自費扱いとなる診断書
最も一般的なのが、保険診療の対象外となる各種診断書です。
例えば「就職時の健康診断書」「運転免許更新用の診断書」「旅行や留学のための診断書」などは、診察や検査の結果を記載するとはいえ、診療報酬点数には含まれていません。そのため自費(保険外負担)として患者さんに費用をご負担いただくことになります。眼科でも視力証明や就学時の診断書などがこれに該当します。
② 保険給付を受けるための文書料
一方で、健康保険や生命保険の給付を受けるために必要な診断書は、患者さんからの依頼に基づく文書であり、自費であるのが原則です。ただし、保険会社が独自に費用を負担する場合もあります。たとえば「医療保険給付金請求のための入院・手術証明」などがこれにあたります。眼科手術(白内障や硝子体手術)の後に提出を求められるケースも多く見られます。
③ 介護サービス利用時の主治医意見書・診断書
介護保険制度では、要介護認定の際に主治医が記載する「主治医意見書」が必要です。これは保険制度に組み込まれた文書であり、診療報酬として算定できるため患者さんから直接費用を徴収することはありません。ただし、作成には時間を要し、医師としても負担の大きい文書です。眼科では、視覚障害による介護度判定の資料として重要になる場合があります。
④ 生活保護患者への各種証明書・意見書
生活保護を受けている患者さんの場合、医療扶助制度により、医療機関が交付する診断書や意見書についても費用を患者さん本人に請求することはできません。生活保護法に基づき自治体が費用を負担します。そのため眼科医院でも、白内障手術適応や障害年金関連で証明書を求められる場合、患者さんに請求せず自治体へ請求することになります。
⑤ 公費医療の診断書・証明書
小児慢性特定疾病医療費助成や難病医療費助成など、公費医療制度に関連する診断書や証明書も、制度上の規定に従って作成し、所定の点数や費用が国や自治体から支払われます。この場合も患者さんに直接費用を請求しないのが原則です。眼科では網膜色素変性症などの指定難病や、小児の弱視治療用眼鏡に関する助成診断書が該当します。
⑥ 学校・保育園に対する書類
最後に、学校や保育園から依頼される各種書類があります。たとえば「登校許可証明書」「眼疾患により体育制限が必要である旨の証明」などです。これらは医師の判断を記す書類ですが、診療報酬には含まれないため、自費扱いとされるのが一般的です。ただし地域や自治体の取り扱いによっては例外もあるため、個別に確認が必要です。
まとめ
このように、医療機関が発行する文書は大きく分けると
-
自費扱いの診断書
-
保険給付請求のための文書(原則自費)
-
介護保険の主治医意見書(保険算定可能)
-
生活保護関連の証明書(自治体負担)
-
公費医療制度に基づく診断書(公費負担)
-
学校・保育園提出用の書類(多くは自費)
に整理されます。
眼科医院でも、視力や眼疾患に関連した診断書・証明書の依頼は少なくありません。患者さんにとっては費用の有無がわかりにくい分野ですが、医療機関としては制度上の位置づけを踏まえ、透明性をもって対応することが大切です。当院でも院内掲示やホームページに料金一覧を示し、患者さんに安心してご依頼いただける体制を整えていきます。




コメント