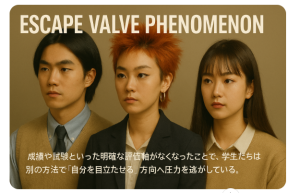 医学教育における「逃げ道現象」とは ― 評価指標を失った学生たちの不安
医学教育における「逃げ道現象」とは ― 評価指標を失った学生たちの不安
近年の米国医学教育では、「学生の心身の健康を守り、公平な評価を行う」という理念のもと、過度な競争を減らす改革が進んでいます。前臨床の成績は合否のみ、米国医師国家試験(USMLE)Step 1も合否方式に変更され、Step 2 Clinical Skillsは廃止されました。さらに、一部の大学では臨床実習(clerkship)も合否制に移行し、従来の点数評価が次々と姿を消しています。
これらは善意から生まれた改革ですが、結果的に「逃げ道現象(Escape Valve Phenomenon)」という新たな問題を生んでいると、Safdieh医師は指摘します。つまり、成績や試験といった明確な評価軸がなくなったことで、学生たちは別の方法で「自分を目立たせる」方向へ圧力を逃がしているというのです。
評価がなくなっても、ストレスは減らない
評価項目が減ればストレスも減る――そう期待されましたが、現実は逆でした。学生たちは、何を基準に評価されるのかわからないまま、不安と焦りを感じています。明確な物差しがないため、誰もが履歴書を飾るような活動――リーダーシップ、地域活動、研究発表など――に追われるようになりました。中には「捕食ジャーナル(predatory journal)」と呼ばれる質の低い学術誌に投稿して実績を作ろうとする例も報告されています。
「平等化」が招いた新しい不公平
成績表という“物差し”が消えた結果、今度は「人脈」や「経済力」といった社会資本が評価を左右するようになりました。指導教員を見つけて研究機会を得たり、有名施設で実習をしたりするには、時間や費用の余裕が必要です。こうして、かえって不平等が広がってしまったのです。
教育側も混乱 ― 評価できる基準がない
一方で、研修医採用を行う教育病院側も困っています。従来の試験や成績がなくなった今、応募者をどう比較すればよいかが不明確です。その結果、大学の名声や推薦者の知名度など、曖昧な基準に頼る傾向が強まっています。結局、USMLE Step 2(知識試験)に過剰な重みが置かれ、以前と同じ「高ストレス試験主義」に逆戻りする懸念もあります。
公平で明確な評価の再構築を
Safdieh医師は「昔の序列型評価に戻るべきではない」としながらも、学生が自分の立ち位置を理解し、成長を確認できる透明で客観的な評価軸の必要性を訴えます。その一例として、各大学が共通して用いる「信頼できる専門活動(Entrustable Professional Activities:EPA)」や、全国で比較可能な臨床評価の導入を提案しています。学生も「明確な基準に基づいて評価されるなら安心できる」と答えており、これは教育現場にも受け入れられやすい改革です。
清澤のコメント
この論文は発表されたばかりですから、別の論文だったのでしょうが、同様の論旨の論説を数か月前に読み、私のブログでも紹介した記憶があります(末尾参照)。医学生教育の話ですが、私たち臨床医にも通じる内容です。評価基準をなくして“優しさ”を目指しても、人は結局どこかで比較され、努力の方向を探します。日本の医学教育でも同様に、明確で公正な評価と、学生・研修医が安心して学べる環境の両立が求められています。現状は、何とか有名な初期研修プログラムに入りたいという苛酷な競争があるように見えます。目指すべきは、競争の否定ではなく、納得できる評価と健全な成長の仕組みなのでしょうけれど。
出典:
Safdieh JE. The Escape Valve Phenomenon in Medical Education. JAMA Neurol. 2025;82(11):1085-1086. doi:10.1001/jamaneurol.2025.2292




コメント