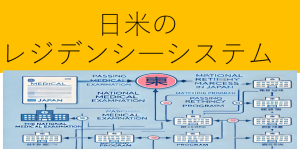 日米の研修医マッチングシステムの比較
日米の研修医マッチングシステムの比較
日本では、医師国家試験が合格すると、事前に決定したマッチングプログラムに沿って研修病院に配属されます。一方、米国ではUSMLE(米国医師免許試験)の合格後、全国統一のレジデンシーマッチングシステムを通じて研修病院が決定されます。JAMA最新号では、米国で卒業時の成績評価が「合否のみ」となったことで、研修病院側が受験者の優劣を判断しにくくなり、名門医学部の出身や研究実績が過度に重視される状況が生じていると指摘されています。(2025年2月6日 レジデンシー申請プロセスにおける客観性の低下 記事情報 。 2025年2月6日公開 doi:10.1001/jama.2024.28397)本記事では、日本と米国の研修医選考システムの違いと課題について整理します。
- 日本と米国の医師免許取得までの流れ
日本の流れ
- 6年間の医学部教育を修了
- 医師国家試験に合格
- 初期研修医マッチングで2年間の研修
- その後、専門分野を選択し後期研修(専攻医)へ進む
米国の流れ
- 4年間の大学を卒業(一般教養課程)
- 4年間の医学部(医科大学院)を修了(MD取得)
- USMLEステップ1・2に合格
- レジデンシーマッチングを経て、3年以上の専門研修(レジデンシー)
- 必要に応じてフェローシップ(専門研修)へ進む
- マッチングプログラムの比較
日本のマッチングシステム
- 医師国家試験合格後、全国の病院と研修医が希望順位を提出し、最適な組み合わせを決定。
- 病院側は、医学部の成績・CBT(共用試験)・面接・病院見学での評価を重視。
米国のマッチングシステム
- “National Resident Matching Program (NRMP)” により全国統一のマッチングを実施。
- 応募者は志望病院に応募し、面接を経て希望順位を提出。
- 各病院も応募者の評価を基に順位リストを作成し、コンピューターが最適な組み合わせを決定。
- USMLEスコア・医学部成績・推薦状・研究実績・面接の印象が評価基準。
- 日本と米国の研修医選考の違い
|
項目 |
日本 |
米国 |
|
医学部修了年数 |
6年(高校卒業後) |
8年(4年制大学+4年制医学部) |
|
国家試験 |
医師国家試験 |
USMLE(3ステップ) |
|
マッチング |
全国統一マッチング |
NRMP(全国統一レジデンシーマッチング) |
|
選考基準 |
成績・CBT・面接・病院見学 |
USMLEスコア・成績・推薦状・研究実績・面接 |
|
研修の流れ |
2年間の初期研修後、専門選択 |
3年以上のレジデンシー |
|
研究論文の影響 |
さほど重視されない |
研究実績が重視される傾向 |
|
名門医学部の影響 |
影響はあるが試験成績が重視 |
名門出身者が有利になりやすい |
- 最近の課題と議論
米国の課題
- USMLEステップ1が合否判定のみとなり、成績差が見えにくくなった。
- その結果、医学部の知名度や研究論文の実績が選考に大きく影響。
- 研究実績の競争が過熱し、公平性が損なわれる可能性。
日本の課題
- 人気病院への希望が集中し、地方病院の研修医不足が深刻。
- マッチング後に「この病院で良かったのか」と悩む研修医も多い。
- 研修医の長時間労働が依然として課題。
- 結論
- 日本と米国はどちらも全国的なマッチング制度を採用しているが、評価基準や研修の流れが異なる。
- 日本のマッチング制度は比較的公平だが、研修医の偏在や労働環境の問題がある。
- 米国では、USMLEの評価変更により、医学部のブランド力や研究実績が過度に重視される傾向が強まり、不公平感が指摘されている。
- 日本は公平な選考を維持しつつ、研修医の労働環境改善やキャリア支援の充実が求められる。




コメント