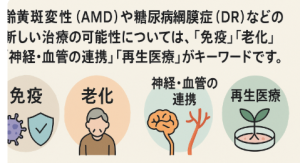 「次世代の網膜疾患治療」日本眼科学会国際シンポジウム1
「次世代の網膜疾患治療」日本眼科学会国際シンポジウム1
清澤のコメント:これまでに日本眼科学界抄録から特別演題とシンポジウム演題の記事をまとめました。ここからは、インターナショナルシンポジウム1「次世代の網膜疾患治療」の内容を、再度一般向けに4演題分まとめて示します。加齢黄斑変性(AMD)や糖尿病網膜症(DR)など、視力を脅かす網膜疾患の新しい治療の可能性について語られます。特に「免疫」「老化」「神経・血管の連携」「再生医療」などがキーワードとなっており、臨床医にも規模プが持てそうな将来の革新的治療に向けた展望が紹介されるでしょう。
ーーーーーー
次世代の網膜疾患治療:インターナショナルシンポジウム1より(2025年4月18日/東京国際フォーラム)
IS01-1 Dr. Rajendra S. Apte(ワシントン大学)
「加齢黄斑変性における炎症と老化の役割」
AMDの進行には、コレステロールの異常な蓄積が引き金となって、免疫細胞(マクロファージ)が老化し、神経の変性や脂肪の沈着を引き起こすことが分かってきました。この仕組みを「NAD+の枯渇」が中心であると突き止め、NAD+を補うことで病状が改善する可能性を示しました。また、老化細胞を除去することで網膜の神経変性を抑えられることも報告されました。AMDの原因解明と新たな治療法開発に大きく貢献する成果です。
IS01-2 畑 匡侑先生(京都大学)
「自然免疫の記憶と加齢黄斑変性」
AMDは遺伝的要因だけでなく、肥満や細菌感染といった過去の生活環境が、体の「自然免疫」の働きを再プログラムしてしまい、将来的なAMDの発症リスクを高めることが示されました。これは「自然免疫の記憶」と呼ばれる新しい概念で、老化とともに起こる神経炎症性疾患の一因として注目されています。免疫の働きをうまく調整することが、AMDの新しい予防法や治療法になる可能性があります。
IS01-3 大内 亜由美先生(順天堂大学 浦安病院)
「糖尿病網膜症におけるミクログリアと神経血管ユニットの破綻」
糖尿病網膜症(DR)は、網膜の神経と血管、そして免疫細胞が連携している「神経血管ユニット」がうまく働かなくなることで進行します。特にミクログリアという免疫細胞の性質が変わることで、炎症や血管新生、線維化が進みます。この細胞は神経を守る役割もあるため、悪化を防ぐにはそのバランス調整が重要です。ヒトiPS細胞やマウスモデルを使った研究が進められており、新たな治療法開発に期待が寄せられています。
IS01-4 Dr. Martin Friedlander(スクリプス研究所)
「網膜疾患に対する幹細胞と前駆細胞を用いた革新的アプローチ」
Friedlander先生は、網膜の血管や神経の損傷に対して、幹細胞や前駆細胞を使って修復するアプローチを紹介しました。これにより、血管の再生や神経保護が可能になることが示され、従来の抗VEGF治療では対応できなかった症例にも光が差す可能性があります。特に再生医療や分子治療を組み合わせることで、重症の網膜疾患に対する新しい治療法が現実味を帯びてきており、将来の視機能回復に期待が高まります。




コメント