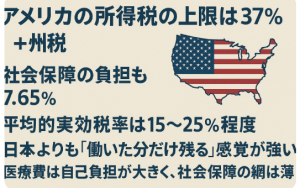 働き盛りの私たちは、何にどれだけ税を払っているのか?──日米の実効税率を比べて考える
働き盛りの私たちは、何にどれだけ税を払っているのか?──日米の実効税率を比べて考える
日々働き、家庭を支え、将来に備えながら生活している私たちにとって、所得税や社会保険料などの「見えにくい負担」は年々重くなっているように感じませんか?
眼科の院長として患者さんとお話ししていると、「税金が重すぎて、子育てや教育に回す余裕がない」「働くほど手取りが減る気がする」といった声が聞こえてきます。
そこで今回は、日本とアメリカの税制を比較しながら、特に“標準的な勤労世帯”がどのような負担を強いられているのかを、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。
🇯🇵 日本:じわじわと重くなる「見えない負担」
日本の所得税は、年収が上がるにつれて税率が上がる累進課税です。課税所得(控除後)に対して、最大45%の国税がかかり、これに加えて全国一律の住民税10%がかかります。たとえば年収800〜1000万円前後の“アッパーミドル”と呼ばれる層では、各種控除を差し引いても、実際には20〜30%前後の税負担がかかるとされます。さらに、給与から自動的に引かれる社会保険料(健康保険、厚生年金など)も、労使折半とはいえ、本人側で年収の約15%程度を負担することになります。結果として、額面の収入のうち40%前後が税や保険料として差し引かれ、「働いても手元に残りにくい」という実感を抱く方が多いのです。
🇺🇸 アメリカ:税率は低いが「自己責任」も
一方、アメリカの所得税(連邦)は7段階の累進制で、上限は37%。しかし、連邦税以外の「州税」が加わるため、住む場所によって実効税率は大きく変動します。たとえばカリフォルニア州では州税も累進制で最高13%ですが、テキサスやフロリダでは州所得税ゼロというところもあります。また社会保障の負担も、給与の7.65%(雇用主と折半)と比較的シンプルです。平均的な労働者の実効税率は15~25%程度とされ、日本よりも「働いた分だけ残る」感覚が強い国です。その分、医療費や教育費は自己負担が大きく、社会保障の網は日本ほど手厚くありません。
数字で比べてみる
| 分類 | 日本 | アメリカ |
|---|---|---|
| 所得税率 | 5~45%(+住民税10%) | 10~37%(+州税0~13%) |
| 社会保険料(被用者負担) | 約15%(健康保険+年金) | 約7.65%(Social Security+Medicare) |
| 実効税率(中堅給与層) | 約25~40% | 約15~25% |
| 法人税(大企業) | 実効30%超(防衛増税後) | 実効25~30%(州込み) |
※いずれも2025年時点の参考値。控除などで個人差あり。
なぜ日本はここまで「高負担型」なのか?
一因として挙げられるのは、日本の少子高齢化です。高齢者が多くなり、医療・介護・年金にかかる公的支出が年々増える中、それを支えるのは現役世代。実際、政府の支出のうち社会保障費はすでに全体の約3分の1以上を占めています。高齢者福祉の充実は重要ですが、その一方で、働き盛りの世代への「将来不安」や「手取りの少なさ」も深刻な課題です。
では、どう考えればよいのでしょう?
ここで一つ大切なのは、「分配」と「再投資」のバランスをどう取るかという視点です。高齢化社会における社会保障は必要不可欠ですが、それだけに偏ると、現役世代の「挑戦」や「次世代への投資」がしにくくなります。医療の現場でも、若い世代が健康や子育てのコストを理由に受診を控えたり、視覚障害のある高齢者にリソースが集中する構造が見られます。社会全体の「視力=見通し」を守るためにも、未来を担う世代に優しい制度設計が必要です。
最後に
私は医師として、目の健康を守ると同時に、社会の見え方にも関心を持っています。今回の日米税制の比較は、「どちらが正しい」という話ではありません。ただ、現役世代が頑張って働き、納税しながらも報われる実感を持てる社会であってほしい、という思いから、この話題を取り上げました。
7月の参議院選挙では、どの政党がどんな財政・税制ビジョンを持っているのか、じっくり見て判断したいですね。
「見えにくい問題」こそ、医師としても、国民としても、目を凝らして考えたいと思います。




コメント