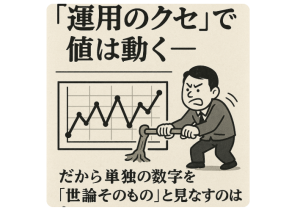 世論調査は“設計”でいかようにもなるものなのか?
世論調査は“設計”でいかようにもなるものなのか?
このユーチューブ番組の主題は「石破おろし」をめぐる政局と報道の“見せ方”。3氏は一貫して、世論調査は設問や対象の取り方で結果が大きく変わり得ると強調しました。具体的には、固定電話中心か携帯も含むか、年代分布の実態、設問の順序や文言、再コールの有無など“運用のクセ”で値は動く――だから単独の数字を“世論そのもの”と見なすのは危ういという論点です。ちょうど医療の検査で条件が違えば結果がぶれるのと似ています、というたとえも示されました。
https://www.youtube.com/channel/UCuSPai4fj2nvwcCeyfq2sIA?utm_source=chatgpt.com
話のきっかけは、直近の調査で「首相は辞める必要はない」が54%という数字が出たこと。3氏は「選挙という最終アウトカム」と調査値が乖離する局面では、とくにサンプリングと設問設計を点検すべきだと指摘。たとえば支持政党別のクロス集計をのぞくと、与党支持層では“首相にふさわしい”の顔ぶれが一変することがある、という現場感覚も披露しました(“総理にふさわしい”ランキングの実態は、誰がどの層で押し上げているかを見ないと誤読する、という趣旨)。実際、該当時期の朝日新聞の電話調査は「辞める必要はない54%/辞めるべき36%」と報じていますが、3氏は“方法の影響”を強く意識すべきだと繰り返します。朝日新聞+1
次に、メディアの役割と構図。3氏は「旧来メディア(報道局)と既成政党、官僚機構の“トライアングル”が情報環境を形づくってきたが、その影響力は弱まりつつある」と分析。動画やSNSが“別系統の可視化”を与え、調査値や紙面の見出しだけでは測れない空気が可視化される場面が増えている、と述べました。反面、強い表現や断片切り取りが拡散しやすい副作用もあるため、「一次情報(元の映像・全文)」に当たる重要性を強調。今回も、首相発言「国を滅ぼしたくない」の文脈をめぐり、見出し先行の受け止めが過熱した、と指摘しました。X (formerly Twitter)
さらに、現場の体感として北村氏は「裏金・不記載といった過去の不祥事の“責任の所在”ばかりが前面化する一方、有権者の今の関心は“今の政権運営への評価”に移っている。取材・遊説現場では“このままではダメだ”という声が主流だった」と述懐。これに対し石橋氏は「報道スタンスが一定方向に寄ると、番組出演者の構成・設問設計・紙面の配置まで連動しやすい」とメディア運用の内側を解説。須田氏は「だからこそ調査は“どう測ったか”を併記し、複数時系列で見るのが最低限」とまとめました。
番組終盤は、スパイ防止法など安全保障関連テーマに触れ、「推進に対して、旧来メディアの一斉批判が想定されるが、いまは“無視戦術”も有効。重要なのは支持者とその周辺が一次情報を拡散し、代替の評価軸を提示すること」との主張で一致。ここでも“世論調査一本足打法”からの脱却を訴えています。
周辺トピックとして、萩生田氏秘書の略式起訴報道に関連し、「判断が固まる前段階の情報がスクープ化され、政治的文脈と絡めて消費される」メディア慣行への違和感も共有。捜査・手続きの節目と報道のタイミングが“世論形成の装置”として働く恐れがある、と問題提起しました。該当件は朝日新聞が8月15日に報道しています。朝日新聞+2朝日新聞+2
—
清澤のコメント;
医療も政治も「測り方次第で見え方が変わる」のは同じ。検査値(=単発の世論調査)も尊重しつつ、方法、一次情報、他社比較、時系列で“多角視”を心がけたいと思います。朝日新聞+1YouTube
参考:本文の数字は朝日新聞の8月16–17日電話調査による報道に拠りました。発言・構成は該当回の虎ノ門ニュース配信・告知を参照しました。朝日新聞+1YouTube+1
動画の基本情報です。




コメント