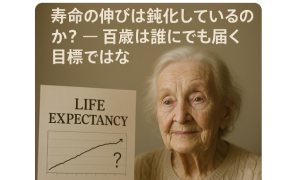 寿命の伸びは鈍化しているのか? ― 百歳は誰にでも届く目標ではない
寿命の伸びは鈍化しているのか? ― 百歳は誰にでも届く目標ではない
(出典:José Andrade, Carlo Giovanni Camarda, Héctor Pifarré i Arolas. Cohort mortality forecasts indicate signs of deceleration in life expectancy gains. PNAS, 2025年, 米国科学アカデミー紀要)
邦文題名:「コホート死亡率予測は寿命延長の鈍化を示している」
背景
20世紀初頭から、医療の発展や衛生環境の改善により人類の寿命は大きく伸びました。特に高所得国では「期待寿命(ある年に生まれた人が平均で何歳まで生きるか)」が直線的に延び続けており、「人類は誰でも百歳に届く時代になる」といった楽観的な見通しも語られてきました。
しかし、近年の研究では「本当に寿命は今後も同じペースで延び続けるのか」という疑問が浮上しています。今回紹介する研究は、過去の実際の死亡データを使って「寿命の伸び方が鈍化しているのではないか」を検証しました。
目的
研究の目的は、これまでの寿命延長の傾向が今後も続くのか、それとも減速しているのかを明らかにすることです。特に「ある年に生まれた集団(コホート)」ごとの寿命に注目しました。これにより、「期間寿命(その時代の平均的な死亡率をもとにした期待値)」では捉えられない、より現実的な長寿の姿を描き出そうとしました。
方法
研究チーム(ウィスコンシン大学マディソン校のピファッレ・イ・アロラス博士ら)は、Human Mortality Databaseという世界的な死亡統計のデータベースを用い、21の高所得国を対象に分析しました。
-
対象となるコホート:1850年~1938年に生まれた集団(すでに人生を終えており「完全に観測」できるデータ)
-
予測対象:1939年~2000年に生まれた集団(まだ生存している人が多いため、予測モデルを適用)
-
分析手法:寿命予測には6種類の統計モデルを使用(Lee-Carterモデルなど)。頑健性を確かめるために交差検証や感度分析も行いました。
結果
-
1850~1938年生まれでは、コホートごとに平均寿命が約 0.46年ずつ延び続けていた。つまり1世代進むごとに半年近く寿命が伸びていたことになります。
-
しかし、1939~2000年生まれの予測では、寿命の延びは 37~52%減少。1コホートごとの寿命の伸びは 2.5~3.5か月に縮小しました。
-
この減速の多くは「若い世代の死亡率がすでに非常に低くなっており、改善の余地が小さい」ことに起因します。20世紀初頭の劇的な寿命延長は、乳幼児や若年期の死亡率改善に大きく依存していましたが、現代ではその恩恵をほぼ使い切ってしまったのです。
-
今後の寿命延長は、高齢期の死亡率改善や生活習慣の改善(喫煙率低下、運動や食生活の改善)、あるいは医学的なブレークスルー(加齢関連疾患治療など)にかかっています。
結論
この研究は「人類の寿命がもう延びない」と結論づけてはいません。しかし、20世紀に見られた直線的な寿命の伸びはすでに鈍化しており、100歳が標準的な寿命になる時代はまだ到来していないことを示しています。
研究者は「寿命の限界があるのか、それとも新しい医療技術で再び大きく延びるのかは未解決の問題」と述べています。感染症や社会的危機が寿命を縮める可能性もありますし、逆に画期的治療が寿命を押し上げるかもしれません。
まとめ
-
20世紀前半は乳幼児死亡率の低下が寿命延長を牽引
-
現代ではその余地が少なくなり、寿命の伸びは鈍化
-
今後は高齢期の健康対策や医学の進歩が鍵を握る
-
「100歳は誰にでも届く目標」ではなく、「努力と環境次第で可能になるかもしれない到達点」である
👉 この研究は、寿命の未来を考えるうえで非常に示唆的です。私たち一人ひとりが生活習慣や健康管理を意識することも、長寿社会を形作る大切な要素となります。




コメント