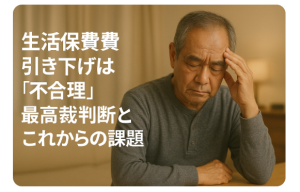 生活保護費引き下げは「不合理」――最高裁が示した判断とこれからの課題
生活保護費引き下げは「不合理」――最高裁が示した判断とこれからの課題
2025年6月、最高裁判所は「2013年以降に行われた生活保護費の引き下げは合理性を欠く」との判断を示しました。この判決は、単なる数字の問題ではなく、「人が人らしく暮らすための最低限の基準」をどう守るかという社会全体のテーマを問い直すものです。今回はこの裁判の背景と、私たちの生活への意味をわかりやすく整理します。
生活保護制度は、憲法25条に基づいて、病気や失業などで生活が困難になった人に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。その中心となるのが、食費・光熱費・衣類などをまかなう「生活扶助基準」。いわば“生きるための最低ライン”を示す指標です。
政府は2013年から「物価が下がっている」「低所得世帯より生活保護世帯の消費が高い」として、この基準を平均6.5%、最大10%引き下げました。世帯によっては月1万円前後の減額となり、多くの受給者が生活の苦しさを訴えました。しかし、この算定方法には「実際の生活実態が反映されていない」との批判が起こり、全国29都道府県で1000人以上が訴訟を起こしました。
そして2025年6月、最高裁は「物価が下がっても人々の生活水準がそのまま下がるとは限らない」と指摘。国の基準改定は“根拠と説明が不十分で、合理性に欠ける”と判断しました。つまり、「デフレだから下げる」という単純な理屈では、憲法の掲げる最低生活を守ることはできない、という強いメッセージです。
一方で、国への損害賠償請求は退けられました。違法とされたのは基準改定の手続きと方法であり、すぐに生活保護費が上がるわけではありません。
厚生労働省は今後、基準を再検討する方針を示しており、改めて「最低生活とは何か」を問い直す議論が始まっています。
この判決は、特別な人だけの問題ではありません。病気、事故、失業など、誰でも一時的に生活が立ちゆかなくなる可能性があります。生活保護は「恥」ではなく、社会全体が支え合うための仕組みです。今回の判断は、国に「人の暮らしの基準」を再び考え直すよう促す転換点といえるでしょう。
院長コメント
社会保障のニュースは、医療現場とも無関係ではありません。経済的な不安があると、受診や治療を先延ばしにする患者さんは少なくありません。今回の最高裁の判断は、「人が生活の安心を失えば健康も保てない」という現実を、司法の立場から明確に示したものだと感じます。医療や福祉の制度は、人の dignity(尊厳)を支える柱です。どなたも必要な時に支援を受けられる社会であってほしい――そう願って、日々の診療を続けています。




コメント