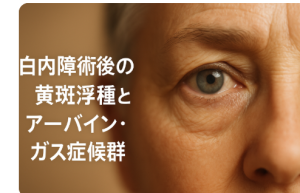 「見えるようになったのに、また見えにくい」
「見えるようになったのに、また見えにくい」
〜白内障術後の黄斑浮腫とアーバイン・ガス症候群〜
白内障手術を終えた患者さんから、「手術直後はよく見えていたのに、最近またかすんできた」と相談を受けることがあります。 術後の視力回復を心待ちにしていた方にとって、これはとても不安な出来事です。
このようなケースで、私たちがまず疑うのが「黄斑浮腫」、特に「嚢胞様黄斑浮腫(Cystoid Macular Edema, CME)」です。 そしてその中でも、白内障手術後に典型的に見られるパターンは、「アーバイン・ガス症候群」と呼ばれています。
この名前を聞くと、私はいつもある先生のことを思い出します。
ガス博士と藤野貞先生
アーバイン・ガス症候群の名の由来となったガス博士(Dr. Robert Gass)は、網膜疾患の分野で世界的に知られる泰斗であり、AZOOR(急性帯状潜在性網膜外層症候群)など、神経眼科領域にも深い造詣を持たれていた方です。 私が研修医時代と助教授時代にお世話になった藤野貞先生も、かつてマイアミのバスコン・パルマー研究所(Bascom Palmer Eye Institute)でガス博士と同僚だったと伺っています。
藤野先生からは、「ガス博士は、網膜の構造と機能を“詩のように語る”先生だった」と教わりました。 その言葉どおり、黄斑浮腫という現象を、網膜の中心で起こる“静かな炎症のさざ波”として捉える視点は、今でも私の診療の根底にあります。
黄斑浮腫とは何か?
白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入することで視力を回復させる手術です。 しかし、手術による刺激や炎症が引き金となって、網膜の中心部「黄斑」に水分が滲み出し、むくみを起こすことがあります。 この状態が「黄斑浮腫」、特に網膜の中に小さな水ぶくれ(嚢胞)ができるタイプを「嚢胞様黄斑浮腫(CME)」と呼びます。
この浮腫が起こると、視界がかすんだり、中心がぼやけたり、直線が波打って見えることがあります。 視力検査では、手術直後に回復していた視力が、再び低下していることもあります。
なぜ起こるのか?
黄斑浮腫の原因は、主に術後の炎症反応です。 特に糖尿病や網膜静脈閉塞症などの既往がある方、あるいは手術中に合併症があった場合には、発症リスクが高まります。 また、硝子体の牽引が黄斑にストレスをかけている場合も、浮腫の一因となります。
どう治療するのか?
治療の基本は、炎症を抑えることです。
-
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)点眼は、軽症例や予防的に使用されます。
-
ステロイド点眼や内服、テノン嚢下注射は、中等度以上の浮腫に対して有効です。
-
抗VEGF薬の硝子体内注射は、糖尿病網膜症などの合併症がある場合や、難治性の浮腫に用いられます。
治療の効果を確認するためには、OCT(光干渉断層計)による定期的な観察が欠かせません。
予後と患者さんへのメッセージ
多くの患者さんは、適切な治療によって数週間から数ヶ月で視力が回復します。 ただし、放置すると視力の回復が遅れたり、後遺症が残ることもあるため、早期発見・早期治療がとても重要です。
白内障手術は、視力を取り戻すための素晴らしい手段ですが、その後の経過観察とケアもまた、視る力を守るために欠かせません。
感謝祭に寄せて
感謝祭は、目の前の人と目を合わせ、感謝を伝える日です。 その“視線”が交わることの尊さを、私たちは日々の診療の中で実感しています。
「見えるようになって、孫の顔がはっきり見えるようになった」 「紅葉の色がこんなに鮮やかだったなんて」 そんな言葉を聞くたびに、目の力の大きさを思い知らされます。
この季節、目の健康にも感謝を。 そして、少しでも見え方に違和感を覚えたら、どうか遠慮なくご相談ください。 “視る”という営みを、これからも一緒に守っていきましょう。




コメント