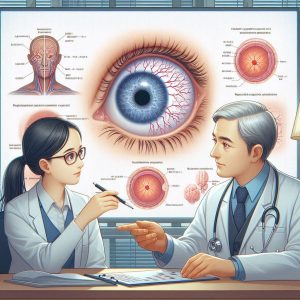 多発性硬化症や視神経脊髄炎スペクトラム障害に伴う視神経炎についての最近の動向
多発性硬化症や視神経脊髄炎スペクトラム障害に伴う視神経炎についての最近の動向
清澤のコメント:最新の日本の眼科の眼科医の手引きには視神経炎に関する2つの評論が掲載されています。嘗ては、私も視神経炎を含めた神経眼科一般の診療を直接に担当していましたが、最近は視神経炎も細分化されており、保険採用されていたりいなかったりする諸検査の必要性を考慮すると、内服ないしパルスでステロイドを使用するような加療は大学病院クラスの診療施設に早めに依頼するのがよさそうです。この2論説の要点を一般の眼科医と当該疾患の患者さん向けに平易に抄出して採録します。
―――――
論文1:多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害 診療ガイドライン2023解説:
(毛塚剛司:毛塚眼科医院/東京医科大学臨床医学系眼科学分野)
視神経脊髄炎の診療ガイドラインの 意義と変遷
多発性硬化症(MS)や視神経脊髄炎(NMO)は, 視神経炎をきたす疾患として重要である。これらの疾患は稀少であり,全ての医療施設において十分な知識と経験を持った医師や医療スタッフが存在するわけではない。
診療ガイドライン2017 年度版において,MSとNMOが完全に別疾患であると規定され,治療法も異なることが記載された。今回、NMOも「視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)」としてアクアポリン4 (AQP4)抗体関連疾患,ミエリンオリゴデンドロ サイト糖蛋白抗体関連疾患(MOGAD)と細分化された。
診療ガイドラインで新たに加わった点
過去の版ではMSとAQP4抗体陽性NMOSDの診療のみに焦点が当てられていたが,新たにMOGAD について検査診断および治療についての項目が加えられた。MOGADは,小児で急性散在性脳脊髄炎(ADEM)を合併することが多く,また他の神経障害に比べて視神経炎が非常に多いので,検査・治療がさらに充実した。 眼科領域では,視神経炎の検査として, 視力検査,光干渉断層計(OCT)を含めた眼底検査,限界フリッカ値測定,相対性求心性瞳孔反応欠損 (RAPD)を検出するための瞳孔検査,視野検査,造影を含めたMRI検査が推奨されている。血清AQP4抗体(ELISA法:保険適用,CBA法: 保険適用外),MOG抗体(CBA法:保険適用外)も,視神経炎の症例に応じて測定が推奨されている。
視神経炎の急性期治療は,第一選択としてステロイドパルス療法,効果がなければ血漿交換療法もしくは免疫グロブリン療法が挙げられている。視神経炎治療では,ステロイド抵抗性に限り免疫グロブリン療法が保険収載されている。AQP4抗体陽性視神経炎がNMOSDの一型とみなされているため、血漿交換療法は NMOSDでは保険適用とされているが,AQP4抗体陽性視神経炎を除く視神経炎では保険適用外である。ステロイドパルス療法はMSの急性期治療としての視神経炎で保険適用となっている。
診療ガイドラインで新たに加わった点
過去の版ではMSとAQP4抗体陽性NMOSDの診 療のみに焦点が当てられていたが,新たにMOGAD について検査診断および治療についての項目が加えられた。MOGADは,小児で急性散在性脳脊髄炎 AQP4抗体陽性NMOSDに対する再発寛解期の治療は,病状安定期では免疫抑制剤の投与(場合によっては低濃度副腎皮質ステロイドの投与)を行い,再発時または活動性が高いと判断された場合は 生物学的製剤の投与が推奨されている。生物学的 製剤は現在,補体抗体のエクリズマブ,IL-6受容体抗体のサトラリズマブ,B細胞を標的としたCD19 抗体のイネビリズマブ,CD20抗体のリツキシマブ の4剤が挙げられている。最も新しく保険収載された補体抗体のラブリズマブは,最新ガイドラインに 掲載されていない。エクリズマブは2週間に1度の点滴静注, サトラリズマブが1カ月に1度の皮下注射,イネビリズマブとリツキシマブが6カ月に1度の点滴静注となる。どの薬剤も再発防止効果に優れたものであるが,感染症,特に呼吸器感染症と尿路感染症,さらには投与時反応に注意を払う必要がある。薬剤別では,エクリズマブ投与中は髄膜炎感染,サトラリズマブ投与中では血球減少に注意を払う必要がある。イネビリズマブやリツキシマブでは,ワクチン 投与の効果が得られない可能性が高い。
眼科医が知らなければならないこと
この ガイドラインを読んで,内科医がこれらの疾患を診断するために視神経障害の有無について眼科医に問い合わせてくる可能性がある。視力,眼圧,眼底検査は必須であり,眼底検査についてはOCTが視神経炎の診断基準の一つにされていることから,黄斑部における網膜神経節細胞内網状層(GCIPL)厚の 菲薄化や視神経周囲の網膜神経線維層(RNFL)厚 の菲薄化が視神経炎の発症3カ月以内にみられるかどうか,緑内障を除外できているかどうかについて 適切に内科医に伝える必要がある。また視野検査を行う際には,長大な視神経病変をきたすことが多い NMOSDやMOGADにおいて,中心暗点や盲点中 心暗点だけではなく,視交叉病変を示唆する両耳側半盲や脳病変を示唆する同名半盲が認められるか確認する必要がある。
論文2:ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白質抗体関連疾患 (MOGAD)視神経炎
横内裕敬;帝京大学ちば総合医療センター 眼科/ 千葉大学大学院医学研究院 眼科学
はじめに ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白質抗体関連疾患(myelin oligodendrocyte glycoprotein anti body-associated disease: MOGAD)は中枢神経系炎症性脱髄疾患であり,この中でもMOGAD視神経炎の臨床像や検査所見には特徴的なことがあることがわかってきた。2023年に改訂され,筆者が発 刊に携わった日本神経学会の診療ガイドラインを踏まえて本疾患の背景や最新の診断・治療エビデンスについてまとめてみたい。 MOGAD視神経炎 MOGADは,髄鞘構成蛋白の一つであるMOG に対する自己抗体を有し,自己免疫的な機序が病態に関与している。MOG抗体は古くから小児の急性散在性脳脊髄炎(ADEM)を引き起こす可能性のある病原性自己抗体として知られていた。
MOGAD は,近年のMOG抗体測定系(Cell based-assay: CBA法)により確立された視神経炎,脊髄炎, ADEM,脳幹脳炎,大脳皮質脳炎など多彩な症状を呈する疾患を含んだ概念である。欧米では成人中枢神経脱髄疾患の1.2~6.5%,小児ではその頻度はさらに高く約40%と報告され,本邦での推定患者 数は1.34人/10万人とされている。発症年齢は小 児と30歳前後の成人例の2峰性であり,男女比はほぼ同等,成人では若干女性が多いとされている。 注目すべきは,MOGAD患者の約80%に視神経炎がみられ,さらに両眼性視神経炎は約40%程度にみられることである。典型的な視神経乳頭腫脹を呈し,眼痛を訴えることが多く,眼痛の存在が本疾患の特徴の一つである。石川らの本邦における全国調査でも本疾患では高度の視神経乳頭腫脹(76%), 眼球運動痛(77%)を伴うことが多かった。視力低下は高度であるが,ステロイドパルス療法に反応 良好な症例が多く視力予後は比較的良好である。一方で再発を繰り返すうちに視野障害を呈する症例や,視力障害が進行する症例が一部存在する。MRI (magnetic resonance imaging)は本疾患の診断・ 鑑別には非常に有用で造影MRIでのSTIR画像, T1強調脂肪抑制画像で増強効果が確認できる。視 神経前方の障害が強いのが一般的であり,MRI画 像では強い腫脹とそれに伴う視神経の屈曲と蛇行が特徴である。近年,光干渉断層計(OCT)は視神経炎の診断には必須となってきており,European Academy of Neurology は OCT 検査手法の標準化 ガイドラインを2016年に発表し2021年には改訂版を策定するなど中枢神経脱髄性炎症性疾患における必須の検査手法としての立場を確立しつつある。
急性期で視神経乳頭腫脹が軽度の症例には視神経 乳頭周囲のRNFL(cpRNFL)厚の測定が評価に有用であるが,黄斑部網膜内層(mGCIPL)の菲薄化 は急性炎症時にはみられず,数週間から数か月後の 慢性期に徐々に進行する。このため視神経炎急性期 にmGCIPLの菲薄化がみられることは過去の視神経炎の既往を示唆する。
急性期の治療は高用量の副腎皮質ステロイド (CS)薬であるステロイドパルス(IVMP)治療が 第一選択である。Randomized controlled trial はな いが,急性増悪に対するIVMPと再発予防に対する経口CS薬の有効性が報告され,国際的調査では 急性増悪期にはすべての専門医師がIVMPを選択している。IVMPが不完全な場合には71.2%の医師 が血漿浄化療法を行っている。IVIg療法(免疫グロブリン大量静注療法)はステロイドパルスが効果不十分な視神経炎の急性期に有効であり早期治療 介入により視機能予後を改善する。慢性期(後療法)の治療に関しては二重盲検試験でエビデンスが確立 された薬剤はないが,観察研究として経口CS薬, リツキシマブ,ミコフェノール酸モフェチル,IVIg の有効性が示唆されている。 まとめ MOGAD視神経炎では早期診断・早期治療が重 要であり,脳神経内科医と密に連携をとって眼科的 検査を定期的に行う必要がある。注意すべきは,本 疾患ではステロイド治療が奏効する症例が多いためか急性期は眼科が積極的に関与するが,脳神経内科 へ紹介されて慢性期になった途端に眼科受診が途絶 えてしまう患者さんが多いことである。本疾患の特性を考えると,今後は急性期だけでなく慢性期に関 しても注意を向けていく必要があるが,MO抗体 検査は現在保険適応外という問題もある。
[文 献] 多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療 ガイドライン2023. 監修:日本神経学会 編集:多 発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイ ドライン作成委員会




コメント