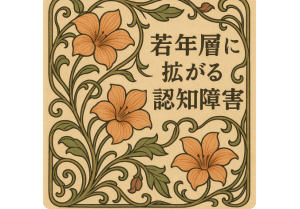 米国で若年層にも拡がる「認知障害」―10年間で倍増した新たな公衆衛生課題
米国で若年層にも拡がる「認知障害」―10年間で倍増した新たな公衆衛生課題
背景
「認知障害(cognitive disability)」とは、記憶力や集中力、意思決定に深刻な困難を感じる状態を指します。米国疾病予防管理センター(CDC)が実施する「行動危険因子監視システム(BRFSS)」では、成人の自己申告によるこのような障害を全国的に調査しています。
従来は高齢者に多いと考えられてきましたが、近年では若い世代にもその広がりが見られ、社会全体の問題として注目されています。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行以降、「ブレインフォグ(思考のもや)」など長期的な後遺症が増えたことも、認知機能の低下と関連していると考えられています。
目的
本研究の目的は、2013年から2023年の10年間における米国成人の自己申告による認知障害の有病率を解析し、年齢、人種・民族、社会経済的背景との関連を明らかにすることでした。特に、若年層における変化を重点的に評価しています。
材料と方法
研究チームは、CDCの「障害・健康データシステム(DHDS)」に収録された、2013~2023年のBRFSS調査データを用いました。
対象は18歳以上の米国成人4,507,061人。質問項目は「集中力・記憶・意思決定に深刻な困難がありますか?」という自己申告による単一質問です。
結果は人口統計学的要因(年齢、性別、人種、教育水準など)で調整され、調査加重ロジスティック回帰モデルを用いて有病率の変化を評価しました。
結果
10年間で、自己申告による認知障害の年齢調整後有病率は5.3%(2013年)から7.4%(2023年)へと上昇しました。
特に注目すべきは18~39歳の若年層で、5.1%から9.7%へとほぼ倍増しており、この層が全体増加の主因とされています。
全体の回答者の約6割が非ヒスパニック系白人でしたが、黒人、ヒスパニック、アメリカ先住民などの少数民族では依然として高い有病率が維持されています。
教育水準や所得の低い層でも認知障害の割合が高く、社会的格差が明確に存在しました。
考察
認知障害はこれまで高齢化に伴う問題と考えられてきましたが、今回の研究は「若年成人にも急速に広がる現象」であることを示しました。
背景には、長期化するストレス社会、スマートフォンやSNSによる情報過多、うつ病や不眠の増加、さらにはCOVID-19後遺症など、複合的な要因があると考えられます。
この傾向は、将来的に労働生産性の低下や医療費の増大につながる恐れがあり、国全体の公衆衛生上の課題となる可能性があります。
結論
2013年から2023年の10年間で、米国の自己申告認知障害は着実に増加し、特に若年層で倍増しています。
この結果は、認知機能低下を「高齢者だけの問題」とせず、生活習慣・メンタルヘルス・社会的要因を含めた包括的な対策の必要性を示しています。
日本においても、スマホ依存やストレス過多の若年層で集中力や記憶の低下を訴える例が増えており、教育現場や医療機関での早期介入が望まれます。
清澤のコメント:
この報告は、認知機能の低下を「老化現象」とだけ捉える従来の考え方を覆す重要な警鐘です。眼科診療でも、高次脳機能や注意力の低下が服薬管理や通院継続に影響する例をしばしば見ます。認知の健康を「脳の視力」として守る発想が、これからの医療に求められているのかもしれません。
出典:
Wong K, Anderson CD, Peterson C, et al. Increasing Cognitive Disability as a Public Health Concern Among US Adults: Trends From the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2013–2023. Neurology. 2025;105(8). doi:10.1212/WNL.0000000000214226




コメント