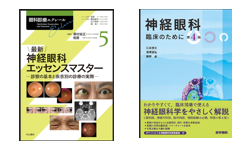 『日本の眼科』2025年10月号に宇野真先生は「レジデントはこれを読め」を寄稿されました。宇野先生はこの中で私も関係して藤野貞先生の遺志を継ぐ『臨床のための神経眼科学』第4版へも言及してくださっており、感謝を申し上げます。
『日本の眼科』2025年10月号に宇野真先生は「レジデントはこれを読め」を寄稿されました。宇野先生はこの中で私も関係して藤野貞先生の遺志を継ぐ『臨床のための神経眼科学』第4版へも言及してくださっており、感謝を申し上げます。
神経眼科の「登山道」を照らす本
眼の病気のなかでも、脳や神経と関係する「神経眼科」はとりわけ奥が深い分野です。眼球の動きが乱れる、片目が見えにくい、視野が欠ける――その原因が眼だけでなく、脳や神経のどこにあるのかを探るのが神経眼科医の役割です。臨床の現場では、診察室がまるで推理小説の舞台のように、症状から原因を突き止めていく知的な緊張感に満ちています。
そんな神経眼科の「登山道」を示してくれる本として、岐阜県の宇野真先生が『日本の眼科』(2025年10月号)で紹介しているのが、『眼科診療エクレール 最新神経眼科エッセンスマスター』(中山書店, 2024)です。その執筆陣はまさに日本神経眼科学会の“オールスター”。最新の知識が、各専門家によってコンパクトかつ実践的にまとめられています。宇野先生は「デート2回分の出費で心の平安が得られる」とユーモラスに述べつつ、現場医にとって即効性のある“お守り”のような本だと評しています。
臨床を離れない神経眼科学 ― 藤野先生の精神
宇野先生がもう一冊、特別な思いを込めて紹介しているのが、『神経眼科 臨床のために』(医学書院, 第4版, 2023)です。
この本には、私も共著者のひとりとして関わらせていただきました。初版から第2版までは藤野貞先生が単独でご執筆され、第3・第4版は藤野先生の弟子である医科歯科大学の後輩が改訂を引き継ぎました。ページをめくると藤野先生の手描き図が随所に登場し、写真は一枚もありません。モノクロ印刷の中にところどころ挿まれたカラー文字だけが彩りを添える、まさに“文章で語る”古典的教科書です。
宇野真先生はその序文にも気が付いておられます。藤野先生の初版への序に戻ってみますと、「科学を重視すると現実から離れる。実地本位に流れると科学を失う。いずれを採るか、個々の患者のニーズも違う。今目の前にいる患者さんのために良きように。」と記されています。これは、「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」という夏目漱石の『草枕』(1906年〈明治39年〉発表)の冒頭部分にある有名な一節を意識したものとも思われますが、実に神経眼科の本質を突いた教えです。
学び続ける医師の姿勢
記事の中で宇野先生は、自らの再出発をユーモラスに語ります。開業医として地域医療に携わってきた後、久しぶりに大学病院の神経眼科外来に加わり、「エベレスト登山のベースキャンプで高山病になりかけているよう」とその心情を吐露します。
その不安を支えるのが、こうした書物と、日々の学びです。
英語の定番書『Walsh & Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology』をはじめ、国内外の症例報告や学会参加を通じて知識を広げる姿勢も語られています。
宇野先生が最後に述べる「診察室はわれわれ臨床家にとって戦いの場。知識という盾と鎧を磨くしかない」という言葉は、すべての医師に通じる真実です。
学び続けることこそが患者さんを守る力になる――そんな思いが行間ににじんでいます。
清澤のコメント
神経眼科を志す若手医師にとって、この二冊はまさに道標です。
藤野先生の「臨床のための神経眼科学」は、科学的厳密さと人間的温かさを兼ね備えた希少な教科書であり、今日の私たちの診療の原点を思い出させてくれます。
また、宇野先生の文章は、苦しみながらも真摯に患者と向き合う医師の姿を生き生きと描き、読む者に勇気を与えてくれます。
神経眼科の道は険しくとも、その先には患者の笑顔がある。
学びと臨床の両輪を忘れずに、私もこれからも一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
(参考:宇野 真「レジデントはこれを読め」『日本の眼科』第96巻10号, 2025年)




コメント