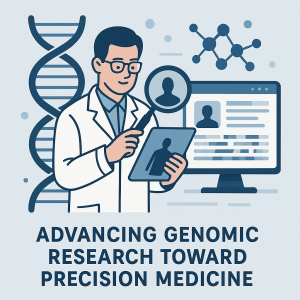 シンポジウム1 精密医療に向けた最新のゲノム研究
シンポジウム1 精密医療に向けた最新のゲノム研究Latest Genomic Research for Precision Medicine
4月 17(木)9:00‒10:20 第1 会場(東京国際フォーラム C ブロック4F ホールC)
■ 前田亜希子 先生(神戸市立神戸アイセンター病院) RPE65遺伝子異常による網膜ジストロフィは幼少期から夜盲や低視力を示し、2023年に日本で初めてこの疾患に対する遺伝子治療が承認されました。網膜構造が保たれているうちに治療することが重要であり、遺伝子検査と治療が同時に承認されたことで早期診断の体制が整いました。同院では2012年から1,761例に遺伝子検査を行い、RPE65異常は10例に認められ、そのうち4例が遺伝子治療を受け、1例にはiPS細胞由来RPE移植も実施されました。遺伝子検査が疾患特異的治療の入り口であり、早期介入に不可欠であることが再確認されました。
■ 上田香織 先生(神戸大学) レーベル遺伝性視神経症(LHON)は母系遺伝性で、両眼の視力低下と中心暗点を呈します。主な原因はMT-ND4遺伝子の11778G>A変異であり、この変異に対する遺伝子治療として、アデノ随伴ウイルス(AAV)を用いたMT-ND4のアロトピック発現による補完療法が検討されてきました。米国、欧州、中国での臨床試験では一定の有効性が示され、興味深いことに片眼の治療で反対眼にも効果が見られる例も報告されています。今後はさらなる病態解明と治療最適化が期待されます。
■ 後藤健介 先生(大阪大学・ヒューマン・メタバース疾患研究拠点) 次世代シークエンス(NGS)の活用により、遺伝性網膜ジストロフィ(IRD)の病因遺伝子の同定が進んでいますが、変異の病的意義を標準化して判定することが課題です。日本人2,325名を対象とした大規模解析により、これまで報告のない100以上の新規病的変異が同定され、東アジア人特有の変異パターンが明らかとなりました。西洋人中心のデータとは異なる日本人特有の特徴を反映した精密医療の枠組み構築が求められています。
■ 森雄貴 先生(京都大学) パキコロイド疾患は加齢黄斑変性(AMD)との関係が注目されており、とくに中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)はアジア人において重要な背景疾患とされます。脈絡膜の厚みや血管構造の違いが病態形成に関与しており、補体因子H(CFH)遺伝子はCSCとAMDで逆の影響を持ちます。CSCに続発する脈絡膜新生血管は、アジア人に多いポリープ状脈絡膜血管症と遺伝的背景を共有することが明らかとなり、病期ごとのゲノム的知見が病態理解と治療戦略に貢献します。
■ 秋山雅人 先生(九州大学) 緑内障をはじめとする複合眼疾患は遺伝要因と環境要因の相互作用で発症します。全ゲノム関連解析(GWAS)により疾患感受性遺伝子が特定され、ポリジーンリスクスコア(PRS)によって個人の発症リスクを定量化することが可能になりました。原発開放隅角緑内障(POAG)では高PRS群が若年発症・重症化しやすい傾向があり、今後は遺伝情報を活用した個別化医療への応用が期待されます。




コメント