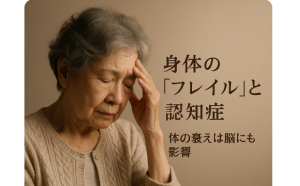 身体の「フレイル」と認知症 ― 体の衰えは脳にも影響する?
身体の「フレイル」と認知症 ― 体の衰えは脳にも影響する?
近年、高齢者の健康を語るときに頻繁に耳にする言葉のひとつが「フレイル(frailty)」です。これは、加齢に伴う筋力や体力、認知機能の低下が重なり、ちょっとしたストレスでも体調を崩しやすい状態を指します。JAMA(米国医師会雑誌)の2025年10月3日号で紹介された社説では、この**「身体のフレイルが認知症の発症に深く関わっている」**という新しい研究結果が紹介されました。
英国バイオバンク49万人の長期調査
この研究は、英国で実施されている大規模な疫学研究「UKバイオバンク」の約49万人を14年間追跡したものです。対象者の中から、疲れやすい・活動量が少ない・歩くのが遅い・握力が弱い・意図しない体重減少といった「フレイルの兆候」をもつ人々を抽出し、認知症との関係を分析しました。
その結果、フレイルの症状を3つ以上持つ人では、約5%が認知症を発症。一方で、症状が1〜2個の人では2%、まったくない人では1%にとどまりました。つまり、フレイルの症状が多いほど、将来の認知症リスクが高くなる傾向が明確に示されたのです。
フレイルがあると認知症リスクは3倍に
さらに、年齢や性別、喫煙や糖尿病など他のリスク因子を統計的に調整しても、フレイルと診断された人は、健康な人に比べて認知症を発症するリスクが約3倍に上ることがわかりました。症状が1〜2個しかない“軽度フレイル”でも、リスクは50%高かったと報告されています。
また、遺伝的に認知症の素因をもつ人では、この傾向がさらに強く、MRIなどの画像検査で脳構造にも認知症関連の変化が見られるケースが多かったとされています。
フレイルと脳の関係 ― 原因か結果か?
この研究は「フレイルが認知症を引き起こす原因なのか、それとも脳の老化が先に進行してフレイルが現れるのか」という点については明確には断定していません。おそらく双方が影響し合うと考えられます。
身体の活動量が減ると、血流や代謝が低下し、脳への酸素供給が減ります。一方、脳の萎縮や神経の変性が進むと、運動機能ややる気が落ちて身体活動が減る――そのような悪循環が生じるのです。
視覚障害もフレイル・認知症の一因に
このJAMAの記事自体では触れられていませんが、過去の研究では視覚障害もフレイルや認知症のリスクを高めることが報告されています。
視力低下により外出機会が減り、筋力やバランス感覚が低下することが、身体的フレイルの第一歩になります。また、見えにくさは社会的孤立や抑うつを招き、脳の刺激が減ることも認知機能の低下に拍車をかけます。
このため、「眼の健康を守ること」も認知症予防の一環としてとても重要なのです。
フレイル予防で「脳を守る」
フレイルを防ぐ基本は、「栄養」「運動」「社会参加」の3本柱です。
-
バランスの良い食事(特にタンパク質とビタミンD)を意識する
-
毎日の軽い運動(散歩やストレッチ)を継続する
-
人との関わりを保つ(会話や趣味の集まり)
これらがフレイルを防ぎ、結果的に脳の健康も守ります。眼科的には、白内障や緑内障、加齢黄斑変性などの視力低下を放置しないことが、フレイルと認知症の両方を防ぐために大切です。
清澤のコメント:
今回のJAMA社説は、「体の衰えが心や脳の老化と密接に結びついている」ということを科学的に裏付ける内容でした。
眼科診療の現場でも、視力が落ちて外出を控えがちになった患者さんが、数年後に認知機能の低下を示す例をしばしば経験します。
「足腰と目は老いの鏡」と言われます。どちらも保つことが、人生後半の質を支える最大の鍵なのかもしれません。
出典:
Andeller S. “Frailty Symptoms Linked to Increased Risk of Dementia.” JAMA. Published online October 3, 2025. DOI: 10.1001/jama.2025.17486




コメント