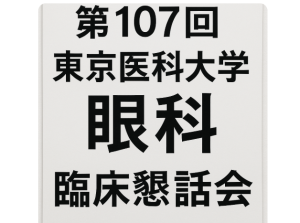 第107回 東京医科大学眼科臨床懇話会に参加して
第107回 東京医科大学眼科臨床懇話会に参加して
(2025年10月4日 京王プラザホテル)
10月4日、京王プラザホテルで開催された第107回 東京医科大学眼科臨床懇話会に参加してきました。
東京医科大学では主任教授が後藤浩先生から若林美宏先生に交代され、座長を務められた准教授陣のご活躍からも、教室全体の新しい勢いを感じました。
演者の先生のご都合により講演順の一部変更がありましたが、いずれの発表も眼科医としての原点を思い出させてくれる内容でした。日々の臨床の疑問を出発点に、研究と教育をどう結びつけるか――その姿勢が全体を通して貫かれており、深く印象に残りました。
① 緑内障と転倒 ― 名古屋大学大学院 眼科学講座 准教授 結城賢弥先生
最初の講演は、結城賢弥先生による「緑内障と転倒」。
先生は名古屋のご出身で、慶応大学時代から地元に戻られた経緯もご紹介くださいました。緑内障では視野が欠けても患者自身がその異常を自覚しにくく、その結果として転倒や骨折のリスクが高まるというデータが示されました。特に下方視野の障害は段差や障害物の発見を妨げ、転倒事故の大きな要因となります。
結城先生は、「視野障害は単なる視覚の問題ではなく、生活の安全に直結する」と強調されていました。このお話を伺い、私自身も日常診療の中で、視野の変化が患者さんの生活動作にどう影響しているかをより丁寧に尋ねたいと感じました。
② 「研究をやらない手はない!」 ― 福井大学 眼科学講座 准教授 高村佳弘先生
続いて登壇された高村佳弘先生は、ご自身の糖尿病網膜症研究の歩みを振り返りながら、若手育成に対するお考えを語られました。
日常診療の中で生まれる“素朴な疑問”を見逃さず、「なぜだろう?」という気づきを研究につなげることこそ、臨床医の真価であると話されました。
特に印象的だったのは、後輩を励ますための「さ・し・す・せ・そ」の言葉です。
-
さ=さすが!
-
し=知らなかった!
-
す=すごーい!
-
せ=センスあるね!
-
そ=そうなんだ!
この五つの言葉で若手の意欲を引き出すというお話に、会場の空気が和みました。
先生の語り口には温かみがあり、研究室の中に息づく「人を育てる文化」が伝わってきました。最近のエピジェネティクス研究にも触れられ、基礎と臨床を橋渡しする姿勢に共感を覚えました。
③ 小児の神経眼科症例 ― 埼玉県立小児医療センター
最後は、埼玉県立小児医療センターからの小児神経眼科症例の報告でした。
豊富な経験に裏づけられた診断力が光る、印象的な症例が次々と紹介されました。
-
眼の周囲が腫れた8歳児:MRIと病理で眼窩横紋筋肉腫と診断。初期には炎症と誤認されやすく、画像検査の重要性が強調されました。
-
小児の斜視や眼振の症例:視神経や脳の発達異常を背景とする神経眼科型斜視。単なる斜視とは異なり、神経学的な視点が求められます。眼振例では**Septo-Optic Dysplasia(視神経中隔形成異常症)**が報告され、下垂体機能低下を伴うことも多く、小児内分泌科との連携が不可欠とされました。
-
てんかん性スパズム症候群治療中の視野障害:抗てんかん薬ビガバトリンによる薬剤性視野障害。早期発見には定期的な視野検査が必要とのことでした。私自身、かつて同薬の日本導入をめぐる研究会の存在を思い出し、感慨を覚えました。
-
ビタミンA欠乏によるドライアイとビトー斑:自閉症児で偏食が強く、結膜に白色の乾燥斑を形成。発達障害を背景とした栄養性疾患が複数報告されました。
いずれの症例も、「見えにくさ」の背後に多様な要因が潜むことを教えてくれました。
小児神経眼科という分野を地道に切り拓かれてきた先生方の熱意に、心から敬意を抱きました。
まとめ
今回の懇話会は、緑内障・糖尿病・小児神経眼科という異なるテーマを通じて、「臨床の中に研究の種がある」という共通の信念が感じられる会でした。
私自身も、診療の中で見過ごしがちな小さな疑問をもう一度大切にし、そこから次の一歩を踏み出す勇気をいただきました。
穏やかでありながら、心に火をともすような時間でした。




コメント