 医師としての「最後の夜」──研修の日々を超えて
医師としての「最後の夜」──研修の日々を超えて
かつて米国の研修医の当直は、眠る時間もままならないほど過酷でした。テレビ番組ERをご覧になった方には想像できるでしょう。2~3日に一度は夜を通して働き、仮眠は数時間。日本でも数十年前までは、同じように病院に泊まり込む日々が珍しくなかったでしょう。いまでは働き方改革によって改善が進みましたが、医師が「人間らしさ」を失わずに成長することの難しさは、今も変わりません。疲れがたまると患者を敵視する傾向も出かねません。
JAMAに掲載された内科医レノア・M・バックリー博士(イェール大学)のエッセイ「私の心の一部:最後の夜」は、その長い医師人生を締めくくる静かな回想です。
眠れぬ夜と「第二の家」
研修医時代、バックリー医師にとって病院は「第二の家」でした。夜間当直のたびに、あと何時間眠れるかを計算しながら廊下を歩き回ったといいます。しかし、救急呼び出しのベルが鳴るたび、睡眠への希望は消えていきました。それでも彼女は前向きに働き、4年間を戦い抜きました。「睡眠への執着は今も私の中に残っている」と彼女は振り返ります。
成長と学び、そして別れ
リウマチ学の専門医となってからの彼女は、炎症性疾患に苦しむ多くの女性患者と向き合いました。痛みや関節の変形だけでなく、母として、妻として、働く女性として生きる苦悩を共有しました。患者との対話を通して、自らの人生の試練に向き合う力を得たといいます。
やがて医学の進歩によって、生物学的製剤や疾患修飾薬が登場し、患者の生活は劇的に改善しました。通院が必要なくなり、ビデオ診療で処方を補うだけの患者も増えた――それは医療の勝利であると同時に、かつてのように人と深く語り合う機会が減ったことへの一抹の寂しさでもありました。
病院という「聖域」
退職を目前にした今、バックリー医師は40年前の「最後の当直」を思い出します。
病院の夜は静かで、まるで教会のようだと彼女は表現します。くすんだ灰色の壁、点滅する蛍光灯、鳴り続ける警報音――そんな無機質な空間の中にこそ、人々が再生と修復を求めて集う「神聖さ」がある、と。
「もし私たちが、ここで起こるすべての出来事の重みを完全に理解してしまったら、その神聖さに圧倒されて動けなくなってしまうかもしれない」と彼女は記します。
最後の廊下を歩きながら
その夜、彼女は患者たちの顔を思い出しました。病気や老いのために人生の岐路に立つ人々。医学が救えた命、そして救えなかった命。そこにあるのは、絶望と希望、喪失と再生の交錯する世界でした。
「病院の灰色の壁の向こうに、私は栄光を見た」と彼女は述べます。それは誰にも見せない、医師だけが知る“静かな神聖さ”の瞬間。
夜が明ける前、彼女は白衣と古い身分証を脱ぎ捨て、車の助手席に置きました。
「この仕事が私を今の私にしてくれたが、同時に大きな代償もあった。もう振り返らない。手放して前に進むときが来た。」
清澤コメント
この文章には、医師という職業の本質が凝縮されています。患者と病を通して成長し、心身をすり減らしながらも、最後には静かに使命を終える――それはまさに“臨床の美学”といえるでしょう。
日本でも、若い医師たちはかつてほど過酷ではないにせよ、今も深夜の病棟で孤独に向き合っています。医療の進歩が彼らの負担を減らし、そして患者とのつながりを守る形で進むことを願わずにはいられません。
出典:
Lenore M. Buckley, MD, MPH. A Part of My Heart: The Last Night. JAMA. Published online November 6, 2025. doi:10.1001/jama.2025.18916


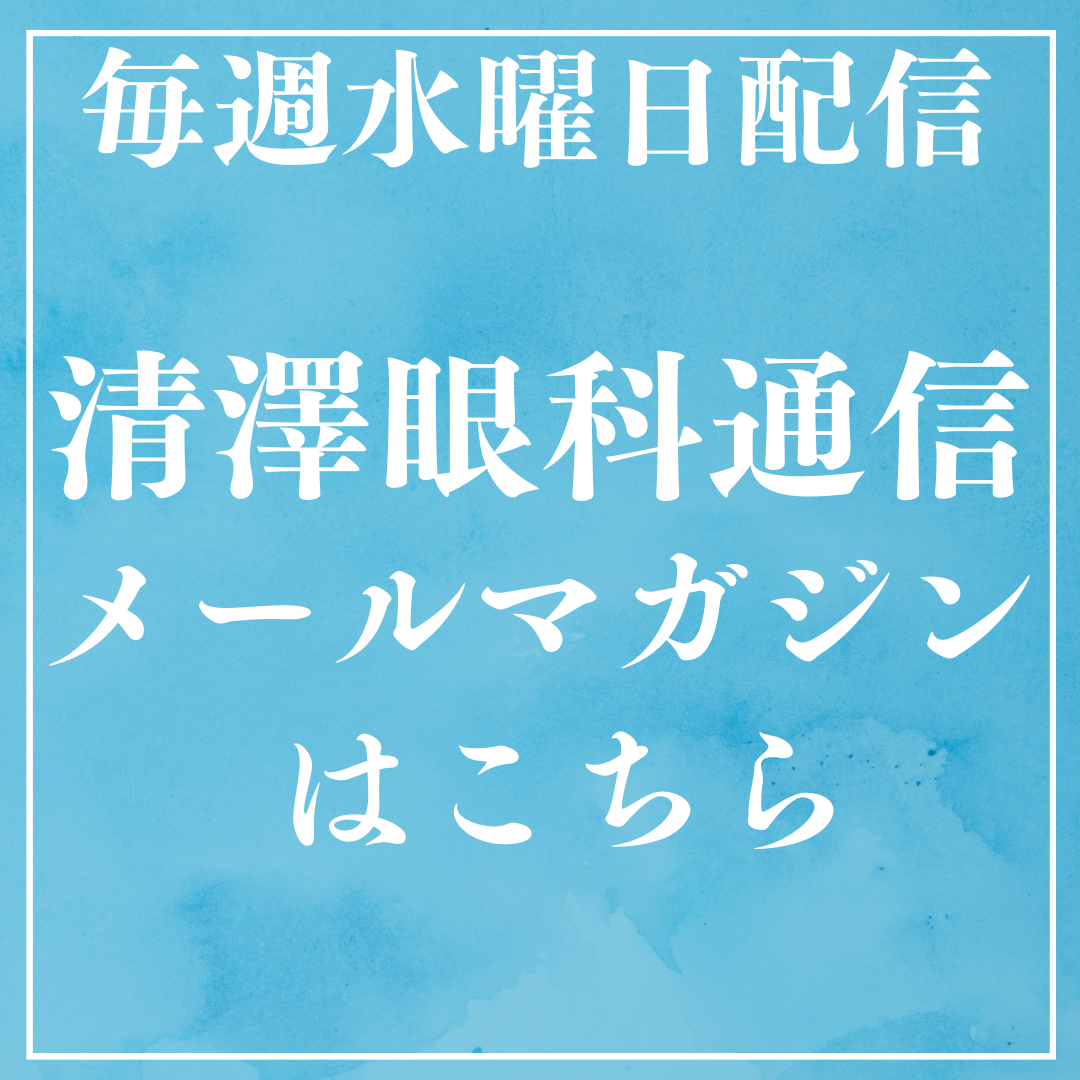

コメント