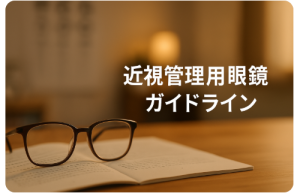 近視管理用眼鏡ガイドライン(第1版)概要
近視管理用眼鏡ガイドライン(第1版)概要
(出典:『日本眼科学会雑誌』129巻10号 855–860 日本近視学会ガイドライン作成委員会)。①一日2時間以上の戸外活動、⓶低濃度アトロピン点眼、③オルソケラトロジー、に続いて今回の複数の焦点を持つ近視管理用眼鏡が近視進行予防治療のラインアップに加わってきました。今回はそのガイドラインを紹介します。最初に超短縮版、続けてやや詳しい短縮版をまとめて見ました。)
Ⅰ.背景
近視は世界的に増えており、2050年には約49億人が近視、9.4億人が強度近視になると予測されています。強い近視では網膜や脈絡膜に変化が起こり、黄斑変性、網膜剥離、緑内障など失明につながる病気の危険が高まります。特に小児期からの近視進行を抑える対策が重要とされています。
日本近視学会は、近視進行を抑える「近視管理用眼鏡(多分割レンズ)」に関する指針をまとめました。対象はMiYOSMART®(HOYA社)とEssilor® Stellest®(ニコン・エシロール社)です。
Ⅱ.ガイドライン要約
1.処方者
近視管理用眼鏡の処方は、眼科専門医が行います。小児の視機能や光学に詳しいことが条件です。
2.作製者
レンズの構造が特殊なため、国家資格をもつ眼鏡作製技能士が精密に加工します。
3.適応
対象は主に5〜18歳の小児で、近視進行が確認された場合に処方します。強度近視の家族歴がある場合や希望が強い場合も適応になります。
4.禁忌・慎重処方
斜視、弱視、円錐角膜、白内障術後などの患者、または協力が得にくい場合は処方を控えます。
5.インフォームド・コンセント
この眼鏡で近視が治るわけではなく、進行速度を平均55~59%抑えることが目的です。効果には終日装用と定期受診が必要です。副作用は報告されていません。装用初期の2週間は激しい運動を控えます。
6.処方前検査
問診・視力・屈折・眼軸長測定・眼底検査などを行い、続発性近視を除外します。
7.処方上の注意
完全矯正が基本で、瞳孔間距離(PD)に合わせたセンタリングと、ずれにくいフルフレーム選定が推奨されます。
8.2週間後の確認
視力、装用時間、疲れ、頭痛などをチェックし、レンズ位置や度数が適正か確認します。
9.6か月ごとの経過観察
定期的に屈折・眼軸長・視機能を測定し、近視進行を確認します。8歳未満や進行が速い場合は注意深く評価します。
10.経過観察の注意点
-0.5D以上進行した場合はレンズ交換を検討します。中心ずれは1mm以内が目安です。
近視の進行はおおむね18歳頃に安定し、その後中止してもリバウンドはありません。必要に応じて低濃度アトロピン点眼との併用も考えられます。
院長コメント
このガイドラインは、近視管理用眼鏡を安全かつ効果的に使うための手順を示したものです。処方から作製、装用、定期検査までを一貫して管理することが重要です。お子さんと保護者の協力のもと、無理のない形で近視進行を抑える取り組みを進めていきましょう。
もう少し詳しい概要も記載しておきましょう:
日本近視学会/日本眼科学会共に公表された「近視管理用眼鏡(多分割レンズ)ガイドライン(第1版)」(『日本眼科学会雑誌』129巻10号 855-860)を、なるべく章立てを保ちつつ、患者さん・ご家族向けにわかりやすくまとめたものです。出典も明示します。
Ⅰ 緒言
近視(視力が遠くにピントを合わせにくくなる状態)は、世界的にも増加傾向にあります。例えば2000年には近視の方が約13億人、強度近視(‐5 D以上など)でも1.6億人と推定されていましたが、2050年には近視約49億人、強度近視9.4億人と予測されており、強度近視の割合が約5.8倍になるとも言われています。 ニチガン+2journal.nichigan.or.jp+2
強度近視が進むと、眼軸(目の奥行き)が伸びすぎることで網膜や脈絡膜に変化が生じ、黄斑変性、網膜剝離、緑内障など、視力を失うリスクのある眼疾患を発症しやすくなります。 ニチガン
このため、特に子ども期に「近視が進まないように手を打つ」ことが、医学的にも社会的にも急務とされています。アジア地域では特にこの傾向が深刻で、日本でも成人(40歳以上)に比べて中学生など若年層で強度近視の割合が上回ってきています。 ニチガン+1
このような背景から、近視の進行を抑える目的で、点眼(アトロピン)、オルソケラトロジー(深夜に特殊コンタクトレンズを装用して角膜を変形させる手法)、多焦点ソフトコンタクトレンズ、さらには「多分割眼鏡レンズ(multiple-segments spectacle lens)」や「低光線拡散レンズ(diffusion optics technology: DOT lens)」といった“近視管理用眼鏡”も開発・臨床評価されてきました。 ニチガン+1
こうした流れを受けて、このガイドラインでは「近視管理用眼鏡レンズ(特に多分割眼鏡レンズ)」について、処方者・作製者・適応・禁忌・インフォームド・コンセント・処方前検査・処方上の留意事項・経過観察・経過観察での留意点という構成で整理しています。 ニチガン+1
なお、このガイドラインは「適切に使用されるためには、患者およびそのご家族の協力を得ながら体系的に実施することが重要」である旨も明記されています。 ニチガン
Ⅱ ガイドライン
以下、主要項目を分かりやすくご紹介します。
1.処方者
近視管理用眼鏡レンズを使った小児近視管理は、眼科医が担当するべき治療であり、特に小児の視機能発達・眼光学(目の光学的仕組み)に精通していることが処方者としての条件とされています。 ニチガン
2.作製者
この種の近視抑制用眼鏡レンズは、構造・作用機序が通常の眼鏡レンズと異なるため、**眼鏡作製技術者(国家資格)**で、加工精度・フィッティングなどの専門技術を有していることが望ましいとされています。特にレンズのセントリング(光学中心位置)やフレーム調整が視機能最適化の鍵です。 ニチガン
3.適応
この眼鏡の適応は「視機能が発達中の小児」を主対象とし、臨床試験データを踏まえて慎重に選択するべきとされています。具体的には:
-
年齢:対象年齢は5歳~18歳(製品によって7~18歳も)でした。5歳未満は原則推奨されません。 ニチガン
-
対象:調節麻痺下検査で両眼とも近視–0.5D超などの近視があり、「進行が確認された時点」で検討可とされています。強度近視の家族歴がある場合、本人・保護者が強く希望する場合も適応となります。 ニチガン
4.禁忌または慎重処方
次のような場合、原則としてこの眼鏡による近視管理は禁忌または慎重に行うべきとされています。
-
斜視・弱視・眼振・頭位異常など両眼視機能に異常のある場合
-
偽近視・調節異常・色覚異常・遺伝性疾患に伴う近視・二次性近視・円錐角膜・先天白内障・白内障術後等、眼疾患を伴う近視
-
不同視(左右で度数差)では慎重に適応判断
-
装用・検査・フォローアップにおいて患児や保護者の協力が得られないと予想される場合も処方を控えるべき、との記載があります。 ニチガン
5.インフォームド・コンセント
保護者・児童(装用者)ともに理解しておくべき重要ポイントとして:
-
この眼鏡は“近視が治る・軽くなる”というものではなく、「近視進行の速度を一定程度抑える」ものである(例えば2年間平均で55〜59%の抑制率報告あり)と明記されています。 ニチガン+1
-
そのためには「終日装用」「長期間継続」「定期的な眼科受診(屈折検査含む)」が必要となること。近視進行が判明した場合、レンズ交換が頻回となる可能性もあります。副作用の報告は現時点ではないとされています。 ニチガン
-
装用開始後、慣れるまで(約2週間)に激しいスポーツ・球技・運転操作などには注意する旨の記述もあります。 ニチガン
-
装用者・保護者にはそれぞれ適切な説明を行い、保護者管理・協力のもとで装用治療を進めることが強調されています。 ニチガン
6.処方前検査
処方前に必須または推奨される検査が複数提示されています。主なものを整理します。
-
問診:既往歴・家族歴・視覚症状・近視発症年齢・進行速度(D/年・mm/年)・他近視管理治療歴・眼鏡使用歴など。 ニチガン
-
予備検査:屈折検査(自動/他覚・自覚)、視力検査(裸眼・矯正・既使用眼鏡装用下)、遮閉試験(既使用眼鏡時)など。 ニチガン
-
屈折+バイオメトリー:調節麻痺下検査(例:シクロペントラート点眼45〜60分後自動レフラクトメータ)強く推奨。眼軸長測定(レーザー光干渉計)推奨。難しい場合は検影法でオーバーレフラクション可。 ニチガン
-
処方予定眼鏡装用時の視機能評価:遠見矯正視力、両眼視機能(遠方・近方)、遮閉試験、近見立体視等。 ニチガン
-
追加検査(続発性近視および合併症除外目的):細隙灯顕微鏡検査、眼底検査、角膜形状解析、眼圧、視野、色覚、眼球運動、OCTなど任意項目あり。 ニチガン
7.処方上の留意事項
処方時に押さえておきたいレンズ・フレームに関する詳細です(多少専門的ですがポイントを整理します)。
-
レンズ度数:調節麻痺下で得られた値を基準に、近視・乱視とも完全矯正を基本とし、低矯正・過矯正になっていないか確認する。処方可能範囲は製品によって異なります。例えば、MiYOSMART®では球面度数Sが−10.00 D~0.00 D、乱視Cが−4.00 D~0.00 Dまでなどの範囲が定められています。 ニチガン
-
光学中心間距離(瞳孔間距離:PD)を測って処方箋に記載し、眼鏡店でそれに従ってレンズ光学中心をフレーム内で調整・入れ込むこと。 ニチガン
-
フレーム選定:フルフレーム(メタルまたはプラスチック)で、フィッティング調整可能、下方偏位しにくいもの。特に縦幅が30 mm以上(目安)ある方が望ましいとされます。さらに、最大の光学効果を得るためのパラメータ(装用時そり角・前傾角・フレーム–角膜頂点距離・頂点間距離など)が製品ごとに定められています。 ニチガン
8.経過観察 — 装用開始2週後
装用開始2週後に行う確認ポイントが記載されています:
-
問診:遠方・近方視力低下、眼精疲労、頭痛、1日あたりの装用時間など。 ニチガン
-
レンズ度数の確認:過矯正となっていないか、既存の眼鏡装用下で自覚的屈折検査・オーバーレフラクションを実施。 ニチガン
-
レンズのセンタリング・フィッティング確認:処方上の留意事項と併せ、適正な位置・フィットであるかを眼鏡店・眼科が確認。 ニチガン
-
視機能評価:遠方矯正視力やアンケートによる装用者の見え方評価(遠・中・近見、見え方の安定性、慣れなど)を行い、不具合がある場合保護者用質問票による確認も。 ニチガン
9.経過観察 — 6か月ごとのフォローアップ受診
半年毎のフォローで確認すべき項目も整理されています:
-
問診:症状・装用時間など。
-
検査:調節麻痺下屈折検査、眼軸測定(レーザー光干渉計)を強く推奨。視機能評価(遠見矯正視力・両眼視機能・遮閉試験・近見立体視等)も必要。8歳未満または進行が速い児童では、フォローアップごとに視機能評価を行うことが望ましいとされています。 ニチガン
-
追加検査:続発性近視・近視合併症を除外するため、細隙灯・眼底検査など任意検査。 ニチガン
10.経過観察での留意点
最後に、フォローアップで特に留意すべき事項です:
-
レンズ交換の目安:等価球面度数で片眼または両眼で−0.50 D以上近視が進行した場合、両眼のレンズ交換が推奨されています。片眼だけ進行した場合は、もう一方のレンズが損傷なく良好なら片眼のみ交換も可となっています。 ニチガン
-
レンズのセンタリング:装用時、レンズ中心が瞳孔中心と水平・垂直ともに1 mm以内のずれであるか、眼鏡店・眼科で確認が必要です。1 mm以上ずれがあれば再加工またはフレーム調整を依頼すべきとあります。 ニチガン
-
近視管理終了の目安:エビデンスは限られますが、この眼鏡療法を中止してもリバウンド(進行抑制効果の消失+加速)は報告されておらず、装用中止自体はいつでも可能です。ただし、目安として「近視進行が安定する年齢(15歳で48%、18歳で77%、21歳で90%、24歳で96%)」が示されており、進行を見ながら18〜24歳あたりまで装用継続を検討することが望ましいとされています。 ニチガン
-
低濃度アトロピン点眼液との併用:現時点ではエビデンスは限られていますが、近視管理用眼鏡と低濃度アトロピン点眼を併用することで抑制効果が高まる報告もあります。 ニチガン+1
-
最後に、「今後も必要に応じて再検討される可能性あり」という記述も付されています。 ニチガン
眼科院長としてのコメント
当院でも「近視進行の抑制」に関しては、小児期から将来の眼疾患リスクを減らす観点から積極的に取り組んでいます。今回ご紹介したガイドラインは、眼鏡という比較的低侵襲・日常的な装用治療を、きちんとした手順とフォローアップをもって行うための“設計図”と捉えることができます。ポイントは、「処方だけで終わりではない」ことです。適応選定、作製・装用開始・2週間後・6か月ごとの検査・装用継続・レンズ交換・定期フォロー、と一連の流れをきちんと守ることが、抑制効果を実現する鍵となります。さらに、保護者・お子さまの「終日装用」「協力」「定期受診」の理解・協働も不可欠です。
また、近視管理用眼鏡で「絶対に進行を止められる」と過度に期待させるのではなく、「進行スピードをある程度遅らせ、将来起こりうる強度近視の合併症リスクを減らす」という説明を丁寧に行うことが、信頼関係を築くうえでも重要です。
当院では、ご希望・適応に応じてこの種の眼鏡治療をご案内しつつ、点眼(低濃度アトロピン)やオルソケラトロジーなど他の近視抑制手段とも比較・検討していきたいと考えています。患者さん・ご家族との対話を通じて「治療継続可能なライフスタイル設計」を共に行っていきましょう。
ご参考:
「近視管理用眼鏡(多分割レンズ)ガイドライン(第1版)」(近視管理用眼鏡ガイドライン作成委員会)『日本眼科学会雑誌』129巻10号 855–860(2025年) ニチガン+1




コメント