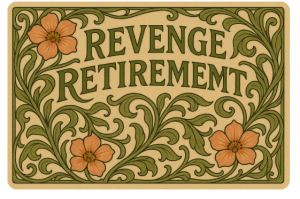 医療機関にとっても他人事ではない「リベンジ退職」
医療機関にとっても他人事ではない「リベンジ退職」
私が世話になっている税理士事務所からのメルマガを毎月興味深く拝見しています。今月取り上げられていた話題の一つが「リベンジ退職」でした。これは会社や組織に不満を持った従業員が、退職の際に意図的に不利益を与える行為を指す言葉です。医療機関に勤務する私にとっても、決して無関係ではないと感じました。なぜなら、医療の現場でも社会保険支払基金からの調査の原因が「退職者からの内部告発」であった、という話を耳にすることがあるからです。退職者に強い不満や恨みを残させてしまえば、医療機関にとっても大きなリスクにつながりかねません。そのため、医療現場においても「リベンジ退職」を防ぐ視点が重要だと感じました。
リベンジ退職の具体的な事例
リベンジ退職と一口に言っても、その行為は多岐にわたります。代表的なものとして、以下のようなケースが報告されています。
-
顧客・患者情報や機密データの持ち出し
これが競合や外部に流れれば、信用失墜や法的問題に発展します。 -
SNSでの誹謗中傷や内部事情の拡散
匿名性を利用して悪評が広まると、ブランドイメージを回復するのに大きな労力が必要です。 -
業務の引き継ぎ拒否
突然辞めることで現場が混乱し、残されたスタッフに過大な負担を与えることになります。 -
内部告発や悪意ある情報提供
医療機関では不適切請求などを指摘されれば調査に発展し、組織運営に大きな影響を及ぼします。
これらはいずれも、単なる「不満の表現」にとどまらず、組織の存続や信頼を揺るがす深刻な行為です。
なぜリベンジ退職が起きるのか
背景には、従業員が抱える「不満」や「不公平感」があります。長時間労働、パワハラやセクハラ、不透明な評価制度、人間関係の悪化など、日常的に蓄積した不信感が退職を機に爆発してしまうのです。さらに近年は転職市場が活発化し、「我慢して働き続けるよりは辞めてしまおう」という風潮も強まりました。その結果、退職をきっかけに会社や組織に仕返しをするケースが増えているといわれています。
医療機関を含む組織にできる予防策
リベンジ退職を完全に防ぐことは難しいものの、リスクを減らす工夫は可能です。
-
コミュニケーションを大切にする
定期的な面談やアンケートを行い、スタッフの不満を早めに把握して解消する姿勢が大切です。 -
評価や報酬の透明化
なぜその評価なのかを丁寧に説明すれば、不公平感を減らせます。納得感のある評価はモチベーションの維持にもつながります。 -
ハラスメントの徹底防止
セクハラ・パワハラを許さない風土を作り、相談窓口や研修で安心して働ける環境を整えます。 -
信頼できる上司・管理者の存在
「この人なら話せる」と思える関係が築けていれば、不満が爆発することを防げます。
まとめ
リベンジ退職は企業だけでなく、医療機関にとっても無視できないリスクです。その被害は経済的損失だけでなく、信頼や評判といった目に見えにくい部分にも及びます。そして、その根底には従業員の心に溜まった「不満」があります。だからこそ、日々のコミュニケーションや透明な評価制度、ハラスメントのない健全な職場環境づくりが最良の予防策となります。
医療の現場でも、患者さんに質の高い医療を提供し続けるためには、まずスタッフが安心して働ける職場であることが欠かせません。退職者に恨みを残させないよう心を配ることは、組織の健全な運営に直結する大切な取り組みといえるでしょう。




コメント