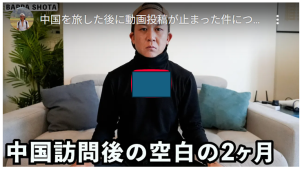 bappa shotaさんは少なくも中国政府につかまっていたわけではなかったと話しています。下のウイグルに関する動画をアップしたのちに自分が何者であるのかに自信を失って、逼塞していたと説明しています。
bappa shotaさんは少なくも中国政府につかまっていたわけではなかったと話しています。下のウイグルに関する動画をアップしたのちに自分が何者であるのかに自信を失って、逼塞していたと説明しています。
これが、バッパショウタ氏が苦労して撮影したウイグルの動画です。;カシュガルでは相当に締め付けが激しいと言っています。
中国・新疆ウイグル自治区を日本人YouTuberが実見し、ネット上の「人権侵害」「監視社会」といった否定的情報と現地の肌感のギャップを探った記録。ウルムチでは街中の監視カメラと武装警察の多さ、飛行機内から続く監視の厳しさを体感。一方で治安の良さや「監視は安全のため」と受け止める住民の声もあり、モスクは開門時間が限定され活気は乏しいが、宗教実践や外観(ヒジャブ等)は一様ではなかった。地元市場では多民族文化が交わる食や暮らしを紹介。対照的に、ウイグル文化が色濃く残るカシュガルでは、再開発で伝統家屋やモスクの破壊・転用が進み、住戸にはQRコード管理、郊外には新築群と厳重な警備が目立つ。年長層からは「監視が人々の心を病ませる」「宗教を問わないで」との切実な声も。強制労働疑惑など国際報道と中国側の否定の間で評価は割れ、住民の間でも「経済発展を良しとする立場」と「アイデンティティ保全を重視する立場」に分かれる。筆者は「一方の目線だけで地域を断じるべきでない」と結び、広域資源・地政学・一帯一路の要衝としての新疆の特殊性と、多層的な現実を提示している。
旅人ユーチューバー、2か月間の沈黙を経て語った「現実」と「再出発」
世界を14年間旅し続け、感動や学びを動画で共有してきたユーチューバーBappa Shota氏が、約2か月間の沈黙を破り、自身の現状と今後を語りました。最後の動画投稿は6月28日。SNSやYouTubeから距離を置いた理由には、燃え尽き症候群、孤独、そして影響力の大きさに対する恐怖があったと率直に告白しています。
3年間休みなく旅を続け、週ごとに国や環境が変わる中で、健康管理や規則正しい生活は難しく、心身の疲労が蓄積。出会いはあっても別れが日常となり、深い人間関係を築くことは困難でした。その結果「自分は誰なのか?」という問いに直面し、ネット世界の中で現実を見失ったと語ります。
さらにウイグルに関する動画が、意図せず人々の対立や憎しみを増幅させてしまった経験も大きな転機でした。発信の影響力が幸福をもたらす一方で、分断の火種にもなり得るという「恐怖」を強く感じたといいます。コメント欄の憎悪に触れ、自分の存在意義を見失った結果、SNSそのものから距離を置かざるを得なくなったのです。
この2か月間、彼は旅の記憶を整理し直し、自らの体験をタトゥーとして刻むことで「宝物」として昇華しました。そして「旅が好き」「地球が好き」「Bappa Shotaである自分が好き」と再確認。視聴者への謝意を述べつつ「復活しました!」と力強く宣言しました。
今後も世界を巡り、リアルな学びを届けていく姿勢は変わらないと強調。大きな影響力を持つ自らの立場を自覚しつつ、新しい視点で活動を続けていく決意を示しました。




コメント