「労働時間規制は緩和すべきか――“一律”をやめ、自己選択と強い保護へ」
清澤のコメント:労働者を守るという思想がこの30年間の日本の沈滞を招いた。欧米人が長期休みを取るというが、野望のある人はそれ以上に働いているというのはわたくしもフランスと米国で感じたところでした、勤務していても個人営業者としての自己意識を持つ人が伸びられる環境も欲しいですね。
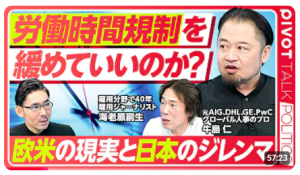
【討論参加者】
司会:佐々氏(PIVOT)
ゲスト:牛島氏(カナミト代表CEO、グローバル人事・人材開発の専門家)
紹介・論点提供:海原氏
本日のテーマは「労働時間規制を緩和すべきか」。出発点は、日本の“何でも一律”という発想です。残業には上限があり、数字上はそれなりに働けますが、「もっと挑戦したい人」も「無理に働かされたくない人」も同じ枠に押し込められ、現場で歪みが生まれています。結果として、管理職は若手に任せたい成長機会を渡しづらく、若手は経験が積みにくい――いわゆる“ゆるブラック”の温床です。
海外の実情は対照的でした。欧州では生活中心の働き方が尊重され、有休を連続で長期取得するのも普通。一方で、経営層やその候補は自ら選んで猛烈に働きます。米国は成果重視で、やりたい人は徹底的にやる。ただし前提に「強い労働者保護」があります。無理な残業の指示や未払いには厳罰と高額賠償、集団訴訟という抑止が機能します。欧州では企業横断の労組や従業員代表制度がブレーキ役です。つまり“やりたくない人にやらせる”を防ぐ仕組みが盤石なのです。
日本はこの土台が弱いまま“一律ルール”だけが走りました。労基監督体制の人手不足、外部労組の力の弱さ、訴訟のハードルの高さ――保護と監視が薄ければ、規制の緩和は「現場に我慢を強いるだけ」になりかねません。人手不足を理由に緩めるのは筋違いで、本来は生産性向上、適正な価格設定と賃上げ、必要に応じた人材流動化で需給を整えるべきだという指摘が出ました。
結論は三点です。①まず保護を強くする――強制残業への厳罰、監督官の増員、外部労組や従業員代表の実効性を高める。②そのうえで「自己選択の個別契約」を認める――本当に望む人が追加の責任と引き換えに、長く・重い仕事へ挑める道筋を用意する。③報酬と負担はフェアに――「ノーペイン・ノーゲイン」。挑戦する人には昇給・昇格、選ばない人には生活を守る働き方を確保し、一律昇給の名ばかり平等は見直す。
日本の強みである「おもてなし」や連帯感は尊い一方、無償の自己犠牲に依存すれば持続しません。必要なのは“一律をやめる勇気”と“強い保護の土台”。個人が納得して選べる働き方を広げることこそ、規制を緩める・緩めないの前に置くべき本当の論点だ――これが本討論の到達点でした。
一昨日から昨日への話題の補追です。:
10月28日、横須賀の米海軍空母ジョージ・ワシントン艦上で行われた演説の中で、トランプ大統領は高市首相を指さしながらこう語った。
“This woman. That’s right. This woman is a winner. So, we’ve become very close friends all of a sudden, because their stock market today and our stock market today hit an all-time high. That means we’re doing something right.”
すなわち、「この女性――そう、この女性は勝者だ。突然だが私たちは親しい友人になった。なぜなら、今日、日本の株式市場もアメリカの株式市場も史上最高値を付けたからだ。つまり、私たちは何か正しいことをしているということだ」と述べ、日米の経済の好調をユーモラスに重ね合わせてみせた。この一節は、政策論ではなく、観衆との軽妙なやりとりの中で、同盟関係の親密さを象徴する一幕となった。




コメント