フェルマーの最終定理は“人の物語”だった—中田敦彦さん動画を眼科院長ブログ向けにやさしく要約
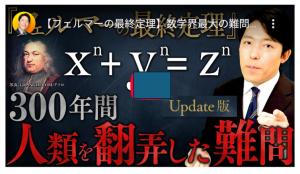 はじめに
はじめに
きょうは中田敦彦さんの「フェルマーの最終定理」解説動画を視聴しました。数学の話なのに、まるで歴史ミステリーやスポーツの長編ドキュメンタリーのように胸が熱くなる内容でした。数式びっしりの難解講義ではなく、「人類と一つの謎が300年かけて向き合った物語」。患者さんやご家族にも楽しめるよう、要点をやさしくまとめます。ぜひ元の動画をご視聴ください。感動できますよ。
1)すべては“直角三角形”から始まった
入口はおなじみのピタゴラスの定理(x²+y²=z²)。3・4・5の直角三角形など、美しい整数の組が無限に見つかります。この「美しさ」が、後の人びとの探究心を燃やしました。
そこから時代は下り、古代ギリシャ末期の天才ディオファントスが算術の大著を著します。戦乱で全13巻のうち6巻しか残らなかったものの、のちの世に大きな影響を与えました。
2)裁判官フェルマーの“余白メモ”が人類を翻弄
17世紀フランス。職業は裁判官、趣味は超一流の“数学”だったピエール・ド・フェルマーが、ディオファントスの本の余白に書き込みをします。
xⁿ + yⁿ = zⁿ は、nが2より大きい整数なら解は存在しない。
「証明は思いついたが、この余白では狭すぎる」
この一文が公開されると、プロ数学者たちが総出で挑戦。フェルマーの残した難問群は次々と解決されましたが、最後まで倒れなかった一問がこの“最終定理”。ここから300年の追走劇が始まります。
3)伝説級の挑戦者たち
-
オイラー:18世紀最大級の天才。フェルマーの痕跡からn=4の場合の不可能性をすくい上げ、自らn=3も証明。ただ、全体の決着には届きません。
余談ですが、オイラーは目の病で視力を失ってもなお暗算と記憶で成果を挙げました。*「これで計算に集中できる」*という言葉は、視覚の専門家としても胸に残ります。 -
ソフィー・ジェルマン:女性が学問にアクセスしづらい時代に偽名で学び、巨匠ガウスをうならせた才媛。彼女の着想はn=5、7での不可能性の道を拓き、後続にバトンを渡しました。
4)日本からの“橋”:谷山–志村予想
20世紀半ば、日本の谷山豊と志村五郎が、いかにも別世界に思えた二つの分野――楕円方程式とモジュラー形式――が本質的に結びつくのではないか、と大胆に予想。これはすぐに完全証明とはいきませんでしたが、数学の“地形図”を塗り替えるほどの大きな道標になりました。
5)異分野ドッキングでフェルマーへ接続
1980年代、フライは「谷山–志村予想が正しければフェルマーの最終定理も従う」と指摘。こうして、直接解けなかった巨大問題が別の理論の完全証明へと“橋渡し”されます。
要するに、フェルマーを倒す鍵は、谷山–志村を証明することに変わったのです。
6)アンドリュー・ワイルズ:6年間の“密室”と逆転劇
少年時代からフェルマーに魅せられたアンドリュー・ワイルズは、教授となってから6年の極秘研究に没頭。段階的に別テーマの論文を“定期配信”して周囲の目をごまかしつつ、最後の仕上げに挑みました。
1993年の連続講義で**「やったか?」と世界が沸騰。しかし、査読でひとつの穴が見つかり、歓喜は一転して緊張へ。数か月の苦闘の末、かつて使えないと退けていた岩澤理論とコリヴァギン=フラッハ理論**を“合わせ技”にすることで突破口を発見。1995年、ついに完全決着。300年の長編に幕が下りました。
7)「役に立つか」よりも「美しいか」
動画が伝える核心は、「数学は役に立つからやる」のではなく、“美しさと面白さ”に価値があるという姿勢です。もちろん結果的に応用の花は次々に咲きますが、源泉は純粋な知的遊び。ワイルズは達成後に「喜びと同時に寂しさもある」と語りました。人生を燃やした最高のゲームが終わったからです。
8)現在進行形の“難問”も
物語はフェルマーで完結しません。動画ではabc予想にも触れ、証明の主張や査読・評価の難しさ、最前線で続く議論の熱も紹介されます。
大切なのは、世界中で今も人類の知が前進しているという実感です。
9)眼科の視点で一言
オイラーの失明後の偉業の逸話は、見えにくさがあっても知的活動は続けられることを示す象徴的な話です。現代はルーペ、拡大読書器、音声読み上げ、コントラスト最適化などロービジョンケアの選択肢が豊富です。視機能に不安がある方は、早めに専門医へご相談ください。適切な補助と環境調整は“知的な喜び”を守ります。
まとめ
-
フェルマーの余白メモが300年の挑戦を生み、
-
オイラーやジェルマン、日本の谷山–志村ら多彩な才能がバトンを繋ぎ、
-
ワイルズが異分野理論を束ねる“合わせ技”でついに決着。
この長編は、数学が「記号の計算」ではなく、人の情熱・友情・発想のドッキングが生むドラマであることを教えてくれます。医学・眼科の世界でも、基礎と臨床、異分野の連携が新しい治療や支援を生みます。美しさを追いかける知的遊び心こそが、明日の医療や暮らしを静かに前進させていくのだと思います。
院長コメント
数学の物語を観て、研究や診療の原点を思い出しました。「役に立つからやる」の前に「心が動くからやる」。この熱源が、人を支え、学問を進め、やがて患者さんの笑顔に届く。フェルマーの長い航海は、医療者にも確かな励ましをくれます。感動できますからぜひ動画全篇をご視聴ください。




コメント