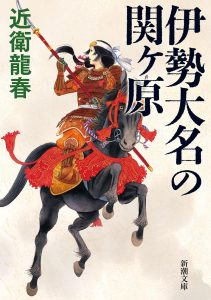 伊勢大名の関ヶ原(著:近衛龍春)のあらすじを書きます。この大名の城は攻め落とされますが、この大名家は関ヶ原の戦いの後、論功行賞で再び栄誉を得ます。しかし、大久保長安事件に連座して取潰しの憂き目にあうのです。
伊勢大名の関ヶ原(著:近衛龍春)のあらすじを書きます。この大名の城は攻め落とされますが、この大名家は関ヶ原の戦いの後、論功行賞で再び栄誉を得ます。しかし、大久保長安事件に連座して取潰しの憂き目にあうのです。
あらすじ
戦国末期、東西の勢力が対峙し、天下が大きく動こうとしていた時代――。伊勢国安濃津(港町・安濃津)を領していた大名、富田信高。彼はある時、松江などを拠点とする西国の大名・吉川元長・吉川元春ら毛利家の強大な軍勢が伊勢に押し寄せてくるという危機に直面します。
移封によって伊勢に入った信高は、元より複雑な地元の商人・地侍(じざむらい)たちが根を張るこの土地で、穏やかな気性と物事を見抜く眼(慧眼)をもって治世を行います。彼は領民の声に耳を傾け、新田開発を進め、地域の基盤を少しずつ整えていきました。
信高の妻となる蓼姫(たでひめ/胆力ある女性)も、ただ後ろに控えるだけの存在ではありませんでした。二人は夫婦として、時には領国経営のパートナーとして、地域の統治に向き合っていきます。
しかし、世が動き出します。東西の分裂が明確となるなか、安濃津城には「東軍」「西軍」の影が迫り、ついに毛利・吉川の大軍(数万)と、わずか千数百の伊勢勢がぶつかる事態となります。毛利・吉川の大軍3万、対する伊勢勢は1,700余という数字も出ています。
この“絶望的とも思える数の差”の中、信高は諦めません。挙国一致で領民・家臣をまとめ、城を守り抜こうとします。そこへ現れたのは、馬上に立つ“若武者”――実は妻の蓼姫自身であったといわれる異色の戦い手。薙刀(なぎなた)を手にし、夫の窮地を救うために駆ける姿が語られます。
最終的に、信高・蓼姫夫妻と領地・領民との絆、そして信高の治世に臨む姿勢が物語の中心テーマとなります。城をめぐる攻防、家督相続、戦前・戦後の政変などを含めて、戦国期伊勢を舞台に描かれた“夫婦の戦い”が深く刻まれています。
追記:大久保長安事件とは?
大久保長安(おおくぼながやす)は、江戸時代の初めに徳川家康に仕えた優れた政治家で、鉱山の開発や治水、道路整備などを任された実務家でした。もとは武田信玄の家臣で、その後家康に見込まれて「天下の総代官」と呼ばれるほどの力を持つようになりました。全国の金山・銀山の収益を取り仕切り、幕府の財政を支える存在でしたが、その豊かな暮らしぶりや莫大な蓄財が次第に疑われるようになります。慶長18年(1613年)に長安が亡くなると、幕府はただちに彼の家を調べ、「鉱山の利益を私していた」などの罪を追及しました。結果、長安の息子たちは処刑され、一族は断絶。さらに、彼と親しかった多くの大名や代官までが連座して処分を受けました。この「大久保長安事件」は、家康が幕府の財政を厳しく引き締め、家臣たちの独走を防ぐために行った権力再編とも言われています。つまり、個人の不正追及にとどまらず、幕府が中央集権を強めていく大きなきっかけとなった事件でした。
コメント(眼科院長より)
「数では勝てない状況でも、絆・統率・視点(眼)を鍛えることで道は開ける」という教訓も得られそうです。
教訓
- 「眼を閉じずに見ること」:信高は支配地の“隠れた声”も聞き、舵をとりました。眼科診療でも、見えない領域にも“目を開いて”診ることが重要です。
- 「数だけであきらめない」:毛利・吉川の大軍に対し、信高らは少数でもあきらめず戦いました。“あきらめない”姿勢が鍵です。
- 「支え合う力」:蓼姫というパートナーの存在、領民・家臣との“協力”が勝負を分けました。チームの支え合いが結果に直結します。
- 「視点を広く持つ」:信高は単に戦に備えるだけでなく、治世・新田開発・地域の発展を見据えていました。眼科でも、「生活の質」「職場・趣味・将来」を見据えたケアが大切です。歴史物語という少し異なる角度から考えてみました。追記




コメント