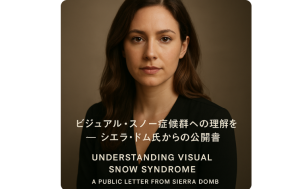 ビジュアル・スノー症候群への理解を ― シエラ・ドム氏からの公開書簡
ビジュアル・スノー症候群への理解を ― シエラ・ドム氏からの公開書簡
世界人口の約2〜3%が、視界全体に砂嵐のようなチラチラした光の粒が見える「ビジュアル・スノー症候群(Visual Snow Syndrome, VSS)」を経験しているといわれます。これは幻視ではなく、脳の感覚処理ネットワークに生じる変化によって起こる神経学的な疾患です。このほど、国際的な患者支援団体「ビジュアル・スノー・イニシアティブ(VSI)」の創設者であるシエラ・ドム(Sierra Domb)氏が、世界中の家族・教育者・医療者に向けた公開書簡を発表しました。彼女自身もVSSを患い、長年の孤立と誤解を乗り越えて活動を続けています。
1. まだ知られていない「見え方の異変」
VSSの最大の特徴は、目を開けても閉じても続く「静電気のような粒のベール」が常に視野にかかることです。さらに、光が眩しく見える(羞明)、物の輪郭がにじむ、残像が残る、暗い場所で見えにくいといった症状が重なります。
耳鳴りや倦怠感、集中力低下、不安感、現実感の喪失などの非視覚的な症状を伴う人も少なくありません。これらはすべて「目の異常」ではなく、脳が視覚情報を処理する過程での異常によるものと考えられています。
2. 誤解と孤立の歴史
この疾患は1940年代から報告があるものの、長く医学界では軽視され、心理的問題とみなされることもありました。患者の多くは検査で異常が見つからず、医師から「問題ない」と言われて途方に暮れます。しかし近年、神経画像研究により視覚野や視床の過活動、神経伝達物質(セロトニン・GABAなど)の関与が指摘され、世界保健機関(WHO)によるICD-11に正式登録されました。VSSは「現実の病」であり、見逃されるべきではありません。
3. 支援と理解の輪を広げるために
ドム氏は書簡の中で、「VSSを持つ人を見かけたら、否定せず、まず信じてほしい」と呼びかけています。周囲の理解や配慮は症状の軽減に大きく寄与します。例えば、明るすぎる照明を避けたり、休憩を許可したりするだけで、感覚の過負荷を防ぐことができます。医療者にとっては、診断や治療が難しくても、「あなたの症状は本当です」と伝えること自体が治療の第一歩になります。
4. 科学と共感の両輪で進むVSIの活動
VSIは、国際的な医師ディレクトリの整備、VSS診断基準の確立、シミュレーター教材の提供などを通じて、研究と教育を推進しています。さらに子ども向けの「VSI4Kids」では、学校での配慮方法や親のサポートガイドも公開されています。
脳画像研究や神経調節療法、色補正レンズ、マインドフルネス療法などの臨床研究も進行中で、治療の糸口が少しずつ見えてきています。
5. 清澤のコメント
ビジュアル・スノー症候群は、眼球自体が正常でも「見え方」が異なるという点で、眼科医にも深く関わるテーマです。眼科での検査で異常がない患者を「問題なし」とせず、**「中枢性視覚情報処理の異常かもしれない」**という視点を持つことが重要です。この公開書簡は、医学の遅れによって苦しんできた患者たちへの共感と行動を促す重要なメッセージです。当院でもVSSの理解を広げるため、今後も国際的な動向を紹介していきたいと思います。
出典:
Sierra Domb, Open Letter on Visual Snow Syndrome to Friends, Families, Educators, Employers, and Healthcare Providers, Visual Snow Initiative, 2025.




コメント