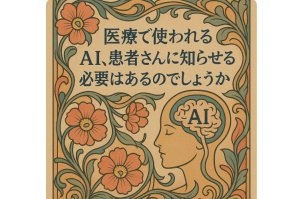 医療で使われるAI、AI使用を患者さんに知らせる必要はあるのでしょうか?
医療で使われるAI、AI使用を患者さんに知らせる必要はあるのでしょうか?
最近、医療の世界でも人工知能(AI)が当たり前のように使われるようになってきました。たとえば心電図の自動解析、がん治療薬を選ぶためのデータ解析、診察記録をまとめてくれる音声認識ツールなどです。私たち医師にとってはありがたい存在ですが、患者さんにとっては「AIが診療に関わっている」と聞くと少し不安になることもあるようです。
実際にアメリカで行われた調査では、成人の約6割が「医師がAIに頼るのは不安だ」と答えています。一方で「AIで医療がよくなるかもしれない」と信じている人は3分の1にとどまりました。また「AIが使われているなら事前に知りたい」と考える人も6割以上に上ります。
では、私たち医療者はどの範囲まで患者さんに知らせるべきなのでしょうか。
どこまで説明が必要?
今回紹介する JAMA の記事では、AIの使用を「知らせる必要がある場合」と「知らせなくてもよい場合」を整理しています。基準は大きく二つです。
-
そのAIが失敗したら患者さんに害が及ぶかどうか
-
AIを使うか使わないかで患者さん自身が選択や行動を変えられるかどうか
たとえば、手術支援ロボットや、がん薬を選ぶAIの場合は、誤りがあれば患者さんに大きな影響が出ますし、患者さんには「ロボット手術にするかどうか」を選ぶ余地があります。こうした場合は、同意を取ることが望ましいとされています。
一方、診察記録をまとめるAIや、心エコーの追加検査をすすめるAIでは、害のリスクは小さいものの、知っておくことで患者さんが検査や説明を理解しやすくなります。こうしたケースでは「通知」することが大切です。
逆に、手術室で血液を準備しておくかどうかをAIが予測して決める場合などは、患者さんの選択に直結しません。そうした裏方のAIまで一つひとつ説明すると、かえって混乱や不信感につながる恐れがあります。
患者さんへの伝え方
記事では「説明は技術的なことまで細かく語る必要はない」としています。大切なのは次のようなポイントです。
-
AIを使っている事実
-
どんな目的で使っているのか
-
最後は人間の医師が確認していること
-
なぜそのAIを導入しているのか(診療を効率化するため、精度を上げるためなど)
-
もし選択肢があるなら、どんな選択ができるか
このくらいの情報を、口頭だけでなく紙やWebサイト、案内パンフレットなどで伝えるのが現実的です。
結論
AIの活用はこれからますます広がっていきます。そのときに大事なのは「何でもかんでもAIを使っていると説明すること」ではなく、「患者さんにとって意味がある説明をすること」だと強調されています。さらに、医療機関としては、AIをどう導入しているかをホームページなどで公開し、透明性を高めることも信頼につながります。
出典
Michelle M. Mello, JD, PhD, MPhil; Danton Char, MD, MAS; Sonnet H. Xu.
The Ethical Duty to Tell Patients About Use of Artificial Intelligence Tools.
JAMA. 2025;334(9):767-770.
doi:10.1001/jama.2025.11417
清澤眼科院長コメント
私たち眼科でも、OCT画像の解析や診療録の要約にAIが導入されつつあります。患者さんにとって大切なのは「AIがすべて判断しているのではなく、医師が責任を持って確認している」という安心感です。これからもAIは診療を助ける大切な道具として広がっていくでしょう。その一方で、患者さんとの信頼関係を守るための説明も忘れないようにしたいと思います。




コメント