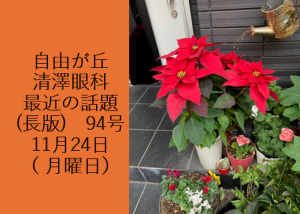 ◎ ブログを元に、最近の話題を取りまとめてこの「自由が丘清澤眼科最近の話題:長版)と、それから記事を厳選したメルマガの発信をしています。今回(11月24日)で94号。メルマガ読者数は眼瞼痙攣患者さんを中心に(11月23日で)910人になりました。(⇒視聴登録募集。ご登録はこちらから)、登録取り消しも簡単にできます。さて、一度読めていたのに、最近メルマガ配信が中断したという方は、あなたの携帯電話の迷惑メールボックスに入っている可能性がありますので来院時に当院職員にご相談ください。
◎ ブログを元に、最近の話題を取りまとめてこの「自由が丘清澤眼科最近の話題:長版)と、それから記事を厳選したメルマガの発信をしています。今回(11月24日)で94号。メルマガ読者数は眼瞼痙攣患者さんを中心に(11月23日で)910人になりました。(⇒視聴登録募集。ご登録はこちらから)、登録取り消しも簡単にできます。さて、一度読めていたのに、最近メルマガ配信が中断したという方は、あなたの携帯電話の迷惑メールボックスに入っている可能性がありますので来院時に当院職員にご相談ください。
① ご近所の話題など
◎ 今週の自由が丘ランチ:「魚卵丼専門店・波の)
当医院からもほど近い、熊野神社に近い場所の地下にあるお店です。一口にいくらといっても魚の種類は様々あってイクラの食べ比べができます。今の季節に一年分を漬け込んでおき、一年かけて消費するそのだそうです。お店はもう10年続いているそうで、、店主の方とざっくばらんにお話がうかがえました。自由が丘で新しい飲食店を2年間続けるのはなかなかむつかしいそうです。
◎ 自由が丘清澤眼科通信の歩みと、これからの3年に向けた新しい取り組み
何ができるでしょうか?この自由が丘清澤眼科通信は完成形を想定しない、成長し続ける眼科関連ブログの構築を目指します。
◎ ラ・パウザ 自由が丘店 市内のイタリアレストラン
町の中にあるイタリアレストランです。場所は地下ですが、開店時間までは階段下のシャッターが下りていて、通路の電灯も消えていたので、今日は休みだったのかと疑って電話をしました。そうしたら、今開けましたとのお答えでした。店の箱も大きく、大勢のお客さんが正午近くまでには入って来ました。スパゲッティーやドリンクバーなど、廉価で家族連れ向けの印象です。
クリスマスの雰囲気を盛り上げるのがプリンセチア。今見るプリンセチアと夏に見たブーゲンビリアは全く異なる植物ですが、“花のように見える部分が実は花ではない”という共通点があります。ここが似ていると感じる理由でしょう。
◎ 出口治明『哲学と宗教全史』を読む
書評をを見てあたりを付けて置き、床屋の帰りに新宿紀伊国屋で探して購入してきました。
◎ 投稿を編集 “青山繁晴 僕らの国会 流行語大賞にノミネート「オールドメディア」の要旨です。
最近よく聞く等になったオールドメディアという言葉は、青山繁晴さんの造語だったそうです。
◎ 眼科検査機器で眼科にもなじみ深いニデック社は、昨年来株が暴落しているニデック社とは別の会社です.
M and Aで急成長し、特徴的な経営者を戴くも、今年の経理承認が得られずに苦しむニデック社は、われわれ眼科医がよく知るニデック社とはカタカナが同じですが、アルファベットでは違う会社です。
眼科検査機器などを製造して我々眼科にもなじみの深いニデックという会社は、昨年来株が暴落しているニデックとは全くの別会社ですか?
② 一般患者さん向けの眼科の話題
実際的な話です。コンタクトレンズの受け取りを便利にすることで、眼科との関係も保てて、野放しのコンタクトレンズ使用になることが防げるのです。メルスプラン(メニコン社)と都度便および宅配便(ジョンソン社)があります。
◎ こころのケアで目の疲れや痛みに向き合う ― 臨床心理学的カウンセリングの方法
目の疲れや痛みを訴えても、検査で異常が見つからない――このような「眼精疲労」や「眼痛」は、現代では決して珍しくありません。パソコンやスマートフォンの使用時間が長く、ストレスの多い生活の中で、目の症状に「こころ」の要素が関わっていることが分かってきています。そこで注目されているのが、臨床心理学的なカウンセリングによるサポートです。
後発白内障では、外来で3分。ヤグレーザーを当てるだけで白内障術後数か月で下がった視力の回復が得られるという場合があります。
◎ 「ロービジョンケアの実際と、外来眼科医にできる支援」
現代の眼科医が提供できる治療には限界があります。網膜色素変性症の進行そのものを止める決定的な治療はまだ確立されておらず、進行をゆるやかにしたり合併症を管理したりする程度にとどまるのが現状です。その一方で、視覚を使った生活をどう支え、残された視機能を最大限に生かして生きやすくするかという視点に立てば、ロービジョンケアで眼科が担える役割はあります。
◎ テルソン(Terson)症候群は、くも膜下出血などで眼内出血を伴う病態です
乳児虐待症候群では眼底出血を見ることが多いとされていますが、その鑑別としてはテルソン症候群も重要な鑑別疾患です。そこでくも膜下出血に伴う網膜硝子体出血であるてルソン症候群についてその特徴などを調べてみました。
◎ 眼科とアレルギー診療のこれから ―「Total Allergist(総合アレルギー専門医)」に眼科医は不必要か?
アレルギー性結膜炎には「重症化しない病気」「抗アレルギー点眼薬で簡単に良くなる」といった誤解もあり、眼科医の関心は決して高くなかったのが現状でした。
◎ トプコン社「マルチファンクショントポグラフィー」MYAHの紹介を伺いました。
近視進行予防治療に有効な眼軸長を測ることのできる新しい機材の説明を受けました。
③ 此処からは論文紹介など眼科のやや専門的、学術的な話題です
◎ 臨床眼科学会のYonekawa Yoshihiro先生の講演を視聴しました:
世界に誇る日本の眼科医を紹介していただきましたが、acute retinal necrosisの発見者の浦山晃先生の写真には当時の東北大学主任教授であった桐沢先生の写真が間違って使用されていたことに気が付きました。これは、理由のある差し間違いです。1978年卒業の私は、その間違いを確信をもって指摘できる最後の世代だと思います。
◎ 米国「MAHA戦略;Make Our Children Healthy Again;」とは?――食から子どもの慢性疾患に挑む国家計画
米国ホワイトハウスは「MAHA」という国家戦略を発表しました。若い世代に拡大する肥満、糖尿病、心臓病などの慢性疾患の主因が「超加工食品の過剰摂取」と「体を守る食べ物の不足」という二重の問題であると指摘し、これらを改善することを大きな目的としています。心臓病の約半数と2型糖尿病の7割が食生活に起因するとされ、食の問題は医療の周辺ではなく“中心課題”と認識されています。
米国「MAHA戦略;Make Our Children Healthy Agai;」とは?――食から子どもの慢性疾患に挑む国家計画
◎ 「気のせい」ではなかった飛蚊症の辛さ、ついに数値化へ |
自己評価症で硝子体手術まで必要なような症例の症状を評価できるようになったという希望の持てる報告が出ています。もう飛蚊症に硝子体手術というのはやりすぎという時代ではなくなりつつあるようです。(次週に詳報を予定です)
◎ 糖尿病性網膜症における「血流」と「網膜感度」の関係を追う
糖尿病性網膜症(DR)は、血糖コントロールが不良な状態が続くことで網膜の細い血管が障害を受け、酸素や栄養の供給が不足し、視機能が低下していく病気です。従来、毛細血管が詰まる「非灌流」領域が広がるほど視力に悪影響を与えると考えられてきましたが、実際にどの程度血流の減少と視機能の低下が対応しているのか、またその関係が時間とともにどう変化していくのかは、十分に明らかになっていませんでした。
◎ 医師としての「最後の夜」──研修の日々を超えて;エッセーの紹介
かつて米国の研修医の当直は、眠る時間もままならないほど過酷でした。テレビ番組ERをご覧になった方には想像できるでしょう。2~3日に一度は夜を通して働き、仮眠は数時間。日本でも数十年前までは、同じように病院に泊まり込む日々が珍しくなかったでしょう。有名な女性の教授が定年退職にあたって感想を述べています。
◎ 長期コロナ後遺症に伴う「脳の霧」への挑戦 ―3つのリハビリ介入を比較した初の大規模試験
BrainHQ単独群、PASC-CoRE併用群、tDCS併用群のいずれも、アクティブ比較群と比べて有意差はなく、統計的に0.0〜0.1程度の小さな差しか見られませんでした。ただし、全ての群で時間の経過とともに少しずつ改善がみられた点は注目されます。これは、自然回復や「訓練を受けている」という心理的効果が影響している可能性があります。副作用はほとんどなく、安全性は確認されました。
④ 眼瞼痙攣、ビジュアルスノウなど神経眼科関連の話
◎ 眼瞼痙攣における羞明とはどういうことか? 患者友の会の私の演題抄録が完成し、友の会の運営委員会にこれを送付しました。
眼瞼痙攣に伴う羞明の発生原因を説明してみます。ハンドアウトのほかに、スライドは見やすいように黒地に白文字で制作しました。友の会は11月30日に行われます。
◎ セロトニン再取り込み阻害薬が「ビジュアルスノウ症候群」を引き起こす?
この研究では、データベースから計24症例が確認されました。全員にビジュアルスノウがあり、そのうち10名(42%)は症候群の診断基準を満たしていました。症状の出現時期を見ると、セロトニン再取り込み阻害薬服用中に発症した人が14例(58%)、減量時が6例(25%)、中止後に出た人が4例(17%)でした。(私は最近この著者からメールで直接にこの論文が出たという通知をうけとりました。)
◎ 眼瞼ミオキミアとは? ― まぶたがピクピクする症状の原因と対処法
眼瞼ミオキミアを眼瞼痙攣や片側顔面痙攣ではないかと疑って来院される患者さんは少なくありません。原則的にそれなら1週間程度で自然に消退します。
◎ 片側顔面けいれん──まぶたのピクつきから始まる神経の病気
片側顔面痙攣は小脳動脈が顔面神経を圧迫して起きる病気で、ジストニアとしての眼瞼痙攣とは別の疾患ですが、同じ病気だと思って来院する患者さんも少なくはありません。治療法はほぼ共通です。
今週も多くの話を提供できました。目をいたわって、健康でお過ごしください。




コメント