2025年日本眼科学会で発表された「一般講演 近視セッション」から得られた最新の研究成果をもとに、眼科医院の院長が患者さんや保護者の方に向けて説明するためのやさしい解説文です。
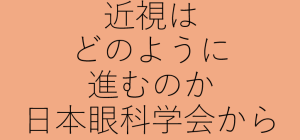 ? 〜研究の最前線から〜
? 〜研究の最前線から〜
近視の進行を抑える方法を探る研究は、年々進化しています。日本眼科学会で発表された最新の研究から、注目すべきトピックをいくつかご紹介します。境膜の虚血や、肥満細胞の関与、視神経の変化など新しい説も提唱されているようです。
① 目の奥の「肥満細胞」の動きが近視に関係しているかもしれません
研究者:福地 智一先生(慶應義塾大学)
近視を誘導したマウスの目の奥では、「肥満細胞」という免疫細胞が活性化していることがわかりました。この細胞の働きを抑える点眼薬(ぺミロラスト)を使うと、近視の進行が抑えられる可能性が示されました。今後、近視の新しい治療法の糸口になるかもしれません。
② 目の「白目部分」が酸素不足になると近視が進む?
研究者:池田 真一先生(慶應義塾大学)
目の「強膜(白目)」が酸素不足になると、細胞の働きにストレスがかかり、それが近視の進行につながることがわかりました。酸素の不足によって細胞内で異常な反応が起き、眼球が伸びやすくなる可能性があるのです。目を健康に保つには、全身の健康や血流も関係していると考えられます。
③ 保護者の不安と知識のギャップが明らかに
研究者:二宮 ささゆり先生(伊丹中央眼科)
全国の保護者を対象にしたアンケートでは、近視に関心を持つ方は多いものの、「眼球が伸びることで進行する」という基本的な知識を知っている方は少数でした。また、お子さんの視力が悪くなるにつれ、不安や生活の質(QOL)も低下している傾向が見られました。正しい情報提供の大切さが改めて示されました。
④ 子どもの視神経にも変化が起きている?
研究者:西垣 誠先生(愛知医科大学)
7〜10歳の子どもを対象に、目の中の神経の厚さを調べたところ、眼圧が高い子ほど視神経の厚みが薄くなっていることがわかりました。これは、将来的に視神経への影響が出てくる可能性を示しており、眼圧の管理も子どもの近視ケアには重要であると考えられます。
⑤ 視神経まわりの「円形の支え構造」が目を守っている
研究者:熊苹 建先生(東京科学大学)
近視の方の目の奥にある視神経の周囲には、円形に配列した線維の構造が存在します。この構造は非常に安定していて、目が伸びてしまっても、視神経をしっかり支えて守る「アンカー」のような役割をしているそうです。近視が進んでもこの支え構造があることで、視神経へのダメージを防いでいると考えられます。
✨まとめ:近視は「予防」と「正しい知識」で未来が変わる
最新の研究からもわかるように、近視は単なる屈折異常ではなく、目の中でさまざまな生物学的な変化が起きている「病的な進行性の変化」でもあります。
だからこそ、正しい知識をもとに、年齢やライフスタイルに応じた対策を行うことが大切です。
✅ 戸外活動を増やす
✅ 近業作業(スマホ・勉強)の時間をコントロール
✅ 必要に応じた治療(低濃度アトロピン点眼、オルソケラトロジーなど)
当院でも、定期的な検査や予防的なアドバイスを行っておりますので、ご不安のある方はお気軽にご相談ください。




コメント