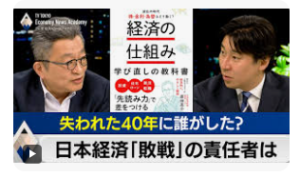 日本の長期停滞をどう抜けるか――バブルから「世代交代」までの教訓
日本の長期停滞をどう抜けるか――バブルから「世代交代」までの教訓
清澤のコメント;連休でいくつかの動画を視聴しました。心にしみたものを採録しています。日本が正社員を温存し、派遣の非正規社員に無理を押し付けた結果、社員の効率まで下がっていったと、先日ネットフリックスで見た「ハケンの品格」というドラマに通じることを一流のジャーナリストも言っていました。
要点
-
バブル後の30~40年停滞の根因は、金融政策の遅れだけでなく、組織・人事・IT投資の遅れという“制度疲労”。
-
終身雇用維持を最優先し賃金・人材投資・設備投資を抑制、非正規拡大とイノベーション低下が進行。
-
家電などはハード偏重で“組み合わせの価値(ハード×ソフト×サービス)”に乗り遅れた。
-
外圧(円高・通商圧力)と内需拡大策が資産バブルを肥大化させた面も。
-
2025年以降、団塊世代の完全リタイアで価値観が転換しうる。賃上げ継続・人材/IT投資・介護医療等の公的賃金テコ入れが鍵。
本文要旨
番組は「日本経済の長期停滞はなぜ起き、どう避けるか」を、日経新聞の原田亮介氏とともに整理する。出発点は、バブル崩壊を単なる日銀の判断ミスに還元しない視点。プラザ合意後の急激な円高対応としての金融緩和・財政出動は、国際環境の制約と国内政治の選択が絡み、結果的に資産市場へ資金が流れ過熱を招いた。だが核心はその後の「制度疲労」だ。メールやERPが組織階層を圧縮し生産性を高めるはずのIT化を、日本企業は内製力や意思決定の硬直で活かしきれず、システム丸投げの構図が続いた。終身雇用を守るため賃金を抑え、人材育成や留学などの投資を削減、非正規化が進展。結果として賃金デフレと新陳代謝の鈍化を招いた。
産業面では、家電はハードの強さに依存し、iPod/iTunes/iPhoneに象徴される「ハード×ソフト×配信」の統合価値に対応が遅れた。既存事業のカニバリゼーションを恐れる“イノベーションのジレンマ”が背景にある。一方、自動車は巨大な系列と現地化で競争力を維持できたが、家電はコモディティ化の波で韓国・中国勢に敗れた。企業の資金使途も、賃金・設備より配当に傾き過ぎ、人と研究開発への再配分が必要だ。
停滞のもう一つの構造要因はリーダーシップ。リスクを取らず「大丈夫か」だけを繰り返す意思決定は、新規事業やDXを遅らせた。とはいえ展望もある。2025年、団塊世代が経営のフロントから完全に退き、若い経営層はオープンイノベーションやアジャイル、国際感覚を前提に方針転換しやすくなる。賃上げを景況次第で止めない“哲学”を持ち、人材・IT・研究に継続投資を振り向けること、さらに介護・医療・保育など公的賃金の底上げで波及効果を生むことが、日本経済再生の実務的打ち手となる。外部要因(関税等)には現地化と為替耐性で能動的に対応し、政府は国内の成長分野を明確に示す——。過去の失敗から学び、世代交代をテコに「失われた40年」を回避できるかが問われている。




コメント