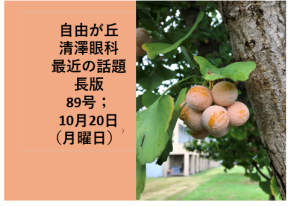 ◎ ブログを元に、最近の話題を取りまとめてこの「自由が丘清澤眼科最近の話題:長版)と、それから記事を厳選したメルマガの発信をしています。今回(10月20日)で89号。メルマガ読者数は眼瞼痙攣患者さんを中心に(10月19日で)875人になりました。(⇒視聴登録募集。ご登録はこちらから)、登録取り消しも簡単にできます。さて、一度読めていたのに、最近メルマガ配信が中断したという方は、あなたの携帯電話の迷惑メールボックスに入っている可能性がありますので来院時に当院職員にご相談ください。
◎ ブログを元に、最近の話題を取りまとめてこの「自由が丘清澤眼科最近の話題:長版)と、それから記事を厳選したメルマガの発信をしています。今回(10月20日)で89号。メルマガ読者数は眼瞼痙攣患者さんを中心に(10月19日で)875人になりました。(⇒視聴登録募集。ご登録はこちらから)、登録取り消しも簡単にできます。さて、一度読めていたのに、最近メルマガ配信が中断したという方は、あなたの携帯電話の迷惑メールボックスに入っている可能性がありますので来院時に当院職員にご相談ください。
① ご近所の話題など
◎ 自由が丘ランチ探訪:黒毛和牛「腰塚」―自家製コンビーフと卵黄が決め手の逸品
自由が丘駅から徒歩2分ほどの場所にある「黒毛和牛 腰塚 自由が丘店」は、精肉店直営の焼肉と惣菜の店です。以前この店は都市再開発前の時計貴金属眼鏡店「一誠堂」の近くにありましたが、都市開発でここに移転しました。肉の品質に徹底してこだわり、黒毛和牛を一頭買いして扱うスタイルが特徴。1階は精肉と惣菜の販売、2階が焼肉を提供するレストランになっています。
◎ 庭の銀杏(イチョウ、ぎんなん) ― 秋の香りと実りの知恵 :悪臭とかぶれに注意
秋が深まると、庭の銀杏の木が一面の黄金色に染まります。扇形の葉は日差しを受けて輝き、足元には丸く黄色い実が落ち始めます。枝に実るときの銀杏は淡い黄緑色ですが、地上に落ちると果肉が柔らかくなり、まもなく発酵して独特の悪臭を放つようになります。それでも、丁寧に処理をすれば、あの美しい翡翠(エメラルド)色の食用銀杏を楽しむことができます。ここでは、その安全な採取と処理の手順を紹介します。
◎日本の「ゾンビ企業」から学ぶ:アメリカ経済への警鐘;記事採録
低金利は一見やさしい処方箋。しかし日本が経験したように、企業を甘やかす長期の金融緩和は経済の体力を奪う。今、米国にも同じ影が迫っている。世界経済の行方を占ううえで、日本の過去が再び注目されています。ブルームバーグのコラムニスト、アリソン・シュレーガー氏は「日本の経験こそ、これからのアメリカ経済への警鐘である」と述べています。テーマはずばり、“金利を人為的に低く保ち続ける危うさ”です。
◎ 欧州でのジェンダー認識の今 ― 医療の現場にも広がる「多様性と平等」の視点
② 一般患者さん向けの眼科の話題
◎ 両方の目がもともと殆ど動かない病気 ― 進行性外眼筋麻痺(PEO)を中心に
外来で、視力や視野は保たれているのに、まぶたが下がり(眼瞼下垂)、目がほとんど動かないという患者さんに出会うことがあります。こうした症状の背景には、外眼筋(眼球を動かす筋肉)の萎縮や麻痺を引き起こす、いくつかの神経・筋疾患が考えられます。その代表が「進行性外眼筋麻痺(progressive external ophthalmoplegia: PEO)」です。その遺伝も調べました。
◎ 低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療の手引き(日本近視学会)の要約です
当医院でも私費診療での低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療を導入しておりますが、この「診療の手引き」(日本近視学会編)が日本眼科学会雑誌の10月号に掲載されました。この話題は当ブログでも何回か取り上げていますが、この記事では素人向けに要約した要約を再録します。
◎ 白内障手術のあとに見える「光の不思議」 ― 視覚陽性現象と視覚陰性現象とは?
白内障手術を受けたあと、「視界が明るくなってよく見えるようになった」という嬉しい声が多く聞かれます。一方で、「目の端に光がちらつく」「黒い影が動く」「何かがキラッと光る」など、不思議な見え方を訴える方も少なくありません。これらは多くの場合、術後の視覚陽性現象(positive visual phenomena)または視覚陰性現象(negative visual phenomena)と呼ばれるものです。今回はその違いや原因、経過についてわかりやすく説明します。
◎ コロナ後の「ブレインフォッグ」と視覚の不調ーー”目にも表れる思考の霧の影響
新型コロナ感染症から回復した後、思考が鈍る・集中できないといった「ブレインフォッグ(脳の霧)」を訴える方が少なくありません。これは単なる疲労ではなく、注意・記憶・処理速度などの高次脳機能が一時的に低下する状態です。そして、このブレインフォッグには「視覚の扱いにくさ」が伴うことが多いことが、最近の研究で分かってきました。
◎ (コンタクトレンズ小話:③)ハードコンタクトレンズの便利さと、その裏に潜む危険な使い方について
ハードコンタクトレンズ(以下ハードレンズ)は、角膜に小さく接触する設計のため酸素透過性に優れ、長期にわたり安定した視力矯正が得られる特徴があります。また乱視矯正効果も高く、角膜に形状異常がある場合でも有効に使えるケースがあります。さらに、レンズ自体が長持ちし、使い捨てタイプと違って経済的という利点もあります。しかし一方で、誤った使用やケアの不十分さが重なれば、やはり目に深刻なトラブルをもたらすことがあります。今回は、ハードレンズを使っている患者さんに特に注意していただきたい危険な使用法を解説します。
③ 此処からは論文紹介など眼科のやや専門的、学術的な話題です
◎ 自殺願望のある軍人および退役軍人のための簡単な認知行動療法:論文紹介
アメリカでは2001年以降、自殺率が30%以上増加し、特に軍人の自殺率は約50%も上昇しています。軍や退役軍人の多くは、亡くなる直前まで精神医療を受けていたことから、医療現場での効果的な自殺予防介入が求められています。そこで注目されたのが「Brief Cognitive Behavioral Therapy(BCBT:短期認知行動療法)」です。私も難病に対しては「患者さんの気づき」を訴求する臨床心理士による認知行動療法を診療に取り入れています。
◎「血をサラサラにする薬」は、多すぎても危ない?
脳梗塞を防ぐ薬には2種類ある。2種類をいっしょに使っても効果は変わらない。2つを併せると脳出血がふえるので、1種類で十分。薬を飲むときは、必ずお医者さんに相談しよう。
◎ (悪い意味での)原始的なケア ― 医療と健康意識の「間」にある新しい空間;記事紹介
医療者がこの「原始的ケア」の存在を認識する必要があると指摘します。多くの人の健康の旅はこの段階から始まります。もし医療がこの層を無視すれば、患者はアルゴリズムや広告、マーケティング(宣伝)に導かれ、誤った方向に進む危険があります。
◎ 子どもの近視治療 ― 一生の医療費にどんな差が出るの?
欧州で行われた「近視の一生コスト」の研究:近年、世界中で子どもの近視が増えています。近視が強く進むと、将来、網膜剥離や緑内障、黄斑変性などの病気を起こす可能性が高くなります。
◎ 診療ガイドで「どの程度の効果なら意味があるか」を明確にする新しい考え方:GRADEガイダンス42:
— 医療の「決定閾値(Decision Threshold)」をめぐって —医療の現場では、「この治療を行うべきか」「この薬を使うべきか」という判断を日々行います.。どれほどの効果があれば「やる価値がある」といえるのかは、人や状況によって違います。このような判断を体系的に整理し、透明性を高めるために生まれたのが GRADE(グレード)ガイドライン です。
◎ 未破裂脳動静脈奇形の出血リスク ― 新たな国際研究から見えた自然経過の実像
未破裂脳AVMの自然経過における出血率は、一般的に考えられていたより低めであり、全例に積極的な治療を行う必要はない可能性が示唆されました。年齢・位置・動脈瘤合併などの要素を考慮した個別化リスク評価が、治療方針を決める上で重要です。これは脳硬膜動静脈奇形とは別のものです。
◎ Apple Watchが高血圧を知らせる時代に ―「血圧の手がかり」が手首にやってくる
高血圧は、世界で13億人以上が影響を受ける「沈黙の病」と呼ばれています。自覚症状が乏しく、年に一度の健康診断でも見逃されることが珍しくありません。そんな中、Apple Watchに「高血圧の可能性」を知らせる新機能が登場し、話題を呼んでいます。これは、医療機関に行かなくても日常生活の中で血圧の変化に気づける可能性を開く画期的な一歩です。
④ 眼瞼痙攣、ビジュアルスノウなど神経眼科関連の話
◎ QOL(生活の質)を損なう「光過敏症」~日本人は光に無防備~(眼瞼痙攣関連記事)
普通の人なら平気な光量をまぶしく不快に感じると同時に、目が痛んだり、まぶたが開けづらかったりする。しかし、原因が不明で病名の診断がつかない―。こんな病気を「眼球使用困難症候群」と呼ぶ。この病気に詳しい神経眼科医の若倉雅登さん(井上眼科病院名誉院長)は、その一形態である「光過敏症」について「生活の質(QOL)を著しく低下させるにもかかわらず、日本人は日常生活であふれている光に対し無防備過ぎる」と警鐘を鳴らしている。
◎ 自閉症の人がもつ特有の「見え方」とは―眼科からできる配慮を中心に―(ビジュアルスノウと自閉症の視覚の比較)
自閉スペクトラム症(ASD)は、コミュニケーションの難しさ、興味の偏り・こだわり、感覚の過敏/鈍感などの特徴を持つ神経発達症です。なかでも「視覚の感じ方」は生活のしやすさに直結します。自閉スペクトラム症(ASD)では感覚特性が生涯にわたり高頻度です。細部に強く、全体が入りにくい。ASDでは、細かい模様や規則性に強く気づく一方、全体像の把握が遅れがち、という“細部優位”がしばしばみられます。(追記で、自閉症とビジュアルスノウの比較)
◎ 抗うつ薬を止めた時に起こる「中止症状」最新研究が明らかにした実態: 眼瞼痙攣とも関連
薬剤に関連した眼瞼痙攣はベンゾ系で多いとされますが、抗うつ薬の試用を述べる患者さんも少なくありません。今回は、抗うつ薬を止めた時に起こる「中止症状」の論文を紹介し、ベンゾ系にも言及しておきます。




コメント