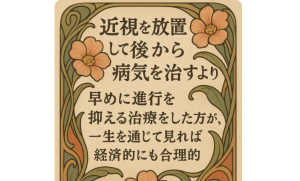 子どもの近視治療 ― 一生の医療費にどんな差が出るの?
子どもの近視治療 ― 一生の医療費にどんな差が出るの?
欧州で行われた「近視の一生コスト」の研究
近年、世界中で子どもの近視が増えています。近視が強く進むと、将来、網膜剥離や緑内障、黄斑変性などの病気を起こす可能性が高くなります。
そこで注目されているのが「近視進行を抑える治療(アクティブ・マイオピア・マネジメント)」です。
低濃度アトロピン点眼や特殊設計の眼鏡・コンタクトレンズ、オルソケラトロジー(夜間装用ハードレンズ)などがその代表です。
アメリカ眼科学会誌 American Journal of Ophthalmology に2025年に掲載された
Lee らの研究 は、これらの治療を取り入れた場合、どのくらい「一生の医療費」が変わるのかを
フランスとイギリスのデータで計算しました。
研究の方法 ― モデルで生涯の費用をシミュレーション
対象は「8歳で近視 −0.75D の子ども」。
そこから25歳までの近視の進み方を「進行が速い子」と「ゆっくりな子」に分けて予測し、
5つの治療法でかかる費用を計算しました。
-
通常の眼鏡・コンタクトで矯正のみ
-
低濃度アトロピン点眼
-
近視抑制用眼鏡(DIMSなど)
-
抑制用ソフトコンタクトレンズ(多焦点など)
-
オルソケラトロジー(夜間装用ハードレンズ)
費用には、眼鏡・レンズ・診察代のほか、将来の視力障害による治療費や仕事への影響など「間接的なコスト」も含まれています。
結果 ― 進行が速い子ほど「将来の節約」につながる
フランスでは、従来治療の生涯費用は約2〜3万ドル、
イギリスでは約3〜5万ドルと試算されました。
進行を抑える治療を受けた場合、速く進むタイプの子どもでは、生涯費用が2〜5割も減る可能性が示されました。
一方、近視があまり進まない子どもでは、治療費がやや上乗せになるケースもありました。
つまり「進行の速い子ほど、早期から積極的な治療をすることで、一生の医療費を減らせる」ことが明らかになったのです。
また、女性はコンタクト使用率や寿命の影響で全体的に費用が高めでした。
結論 ― 「早めの予防」は将来の安心投資
この研究は、「近視を放置して後から病気を治すより、早めに進行を抑える治療をした方が、一生を通じて見れば経済的にも合理的」という結論でした。
特に進行が速いお子さんにとっては、医療費だけでなく、将来の視力低下や生活の質の低下を防ぐ“投資”といえます。
日本の場合はどうでしょう?(清澤院長コメント)
日本では、小・中・高校生までの一般的な眼科診療は、自治体の医療費助成でほぼ無料の地域も多いです。
しかし、オルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼などの「近視進行抑制治療」は保険が効かず、自費診療になります。
そのため、海外のように「長期的にコストが下がる」といっても、日本の現行制度では初期費用を保護者が負担しなければならない点に注意が必要です。
とはいえ、進行の速いお子さんでは、早い段階から近視進行抑制を行うことで、将来の眼病や強度近視を防ぎ、生涯の負担を軽くできる可能性があります。
当院では、進行のスピードや家族歴をふまえた個別相談を行い、「今どの治療を選ぶべきか」を一緒に考えています。
出典:
Lee L, De Angelis L, Barclay E, et al.
Factors Affecting the Lifetime Cost of Myopia and the Impact of Active Myopia Treatments in Europe.
Am J Ophthalmol. 2025; 278: 212–221.
PubMed 40545012




コメント