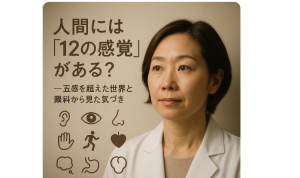 人間には「12の感覚」がある? ― 五感を超えた世界と眼科から見た気づき
人間には「12の感覚」がある? ― 五感を超えた世界と眼科から見た気づき
最近、東京都医師会雑誌の書評欄で『人間には12の感覚がある』という一冊が紹介されていました。
「感覚は五つではなく十二ある」という発想に、最初は少し驚かされました。
しかし調べてみると、この考え方はオーストリアの思想家ルドルフ・シュタイナーによる人間理解の一部であり、教育学や医療、芸術の分野にも広く影響を与えていることがわかりました。
私たちは日常、「見る・聞く・触れる・味わう・嗅ぐ」という五感を通して世界を感じています。けれどもシュタイナーは、人間にはさらに八つの感覚があり、合計十二の感覚が働いていると考えました。
それらは「身体を感じる感覚(触覚・生命感覚・運動感覚・平衡感覚)」、「外界を味わう感覚(嗅覚・味覚・視覚・温感覚)」、「他者や精神世界を感じる感覚(聴覚・言語感覚・思考感覚・自我感覚)」に分けられます。
つまり、“感覚”とは単に情報を受け取るだけでなく、世界や他者とつながる「通路」であるというのです。
たとえば「平衡感覚」や「運動感覚」は、幼児が寝返りを打ち、歩くことを学ぶときに育まれます。
また、「温感覚」や「触覚」は他者との安心感や情緒にも関係するとされます。
さらに「言語感覚」「思考感覚」「自我感覚」は、他人の言葉を理解し、思考を共有し、「あなた」と「わたし」という関係を築く力に通じます。
こうした見方は、感覚を単なる神経機能ではなく、人間発達そのものを支える生命的プロセスととらえるところに特徴があります。
この思想を眼科の立場から見ると、いくつかの示唆を得られます。
まず「視覚」は、単に光を受け取る器官的な機能にとどまらず、「世界をどう感じ取るか」「何に心が動かされるか」という情動や知的体験と密接につながっています。
また、眼の働きは「バランス感覚」や「運動感覚」とも深く関係しています。視覚の異常が姿勢や歩行、集中力に影響を与える例は少なくありません。
「目で見る」という行為は、実は全身の感覚との共同作業なのです。
さらに興味深いのは、患者さんが「まぶしさ」や「疲れ目」といった症状を訴えるとき、それが単なる視機能の問題ではなく、感覚全体の過敏やバランスの乱れとして現れていることがある、という点です。
眼の治療においても、「見る」だけでなく「感じる」「落ち着く」「心地よく過ごす」といった、より広い感覚の調和を意識することが、患者さんのQOL(生活の質)に結びつくのかもしれません。
この「12の感覚」という考え方は、現代科学的な神経生理とは異なる哲学的枠組みですが、感覚を全体として捉えようとする姿勢には深い洞察があります。
私たちが「視る」という行為の中にも、他の感覚や心のはたらきが織り込まれている。そう考えることで、患者さん一人ひとりの“見え方”の背景にある感覚の世界を、もう少し丁寧に理解できるようになる気がします。
五感を超えて十二の感覚を意識する――
それは、眼の前に広がる世界を、もう一度新鮮に見つめ直すきっかけを与えてくれます。




コメント