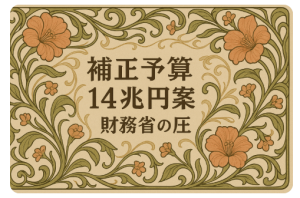 「補正予算14兆円案」と財務省の圧力――高市政権と官僚の綱引き
「補正予算14兆円案」と財務省の圧力――高市政権と官僚の綱引き
話し手:須田慎一郎(ジャーナリスト)
この動画で須田慎一郎さんは、最近の政治の舞台裏として「補正予算をめぐる高市政権と財務省の対立」をわかりやすく解説しています。
まず、地方取材で見た様子として、中国地方の選挙区で与野党を問わず政治活動用ポスターが一斉に貼り替え・増量されており、「解散総選挙が近いのではないか」という空気が広がっていると指摘します。高市内閣の支持率が高い水準で推移していることから、与野党ともに早期選挙を意識し始めているのではないか、という見立てです。
こうした中で注目されるのが、日本経済新聞の「経済対策17兆円規模/補正予算の歳出14兆円程度」という記事です。この記事は最終版だけに載ったことから、須田さんは「日経としてはスクープ扱いの観測報道だったのではないか」と見ています。
問題はここからです。記事によると、2025年度の補正予算(国が実際に支出する規模)は「前年度を上回る14兆円程度」とされています。しかし、昨年度(石破政権時)の補正歳出は13.9兆円で、差はわずか1000億円。数字だけ見れば「ほぼ前年並み」であり、とても景気対策を強化したとは言い難い水準です。
高市政権は「責任ある積極財政」を掲げ、物価高と低所得層・中小企業の苦しさを和らげ、景気の底上げをめざしています。年末に向けて、資金繰りに悩む中小零細企業や所得の低い人々が「年を越せないのではないか」と心配している、というのが高市首相の問題意識だと須田さんは紹介します。そのため、本来なら必要なところにはもっと思い切った規模で予算を投じるべきだというのが積極財政派の考えです。
ところが実際には、各省庁の補正予算の「要求額」自体が小さく、思い切った提案になっていないことが分かってきたと言います。通常、補正予算は「お金を使って景気を下支えする」ことが前提なので、各省庁は知恵を絞って「年度内に実際に使い切れる」対策メニューを積み上げるものです。それなのに今回は、最初から省庁側が遠慮しているような数字しか出していない――。
その背景として須田さんが指摘するのが「財務省による水面下の圧力」です。各省庁に対して財務省側が「大きな要求を出してくるな。どうせ認めない」「要求しても削るから意味がない」といったメッセージを送り、最初の段階から予算要求をしぼませているのではないか、という見方です。その結果として、補正予算の全体像が「前年並み」に収まりそうになっている、と解説します。
もし本当に14兆円程度の小規模な補正で終われば、「石破政権と同じレベルで、生活実感は何も変わらない」と有権者が感じ、高市政権への期待が一気にしぼみかねません。期待が失望や反発に変われば、支持率も急落する恐れがあると須田さんは警鐘を鳴らします。
一方で、日本維新の会など連立参加勢力も、身を切る改革だけでなく「経済を良くした」と有権者に実感してもらわなければ次の選挙で勝てない立場ですから、「前年並みの補正規模では困る」という点では高市政権側と利害が一致している、とも述べています。
結局、構図は「財務省 vs. 高市政権+積極財政派(自民党内+維新など)」の綱引きです。財務省は、一度譲れば高市政権にさらに大きな規模を要求されると警戒し、なんとか規模を抑え込もうとしている。対して高市政権側は、自ら掲げた積極財政の旗をここで降ろすわけにはいかず、片山財務大臣に再度強い指示を出して巻き返しを図るだろう、と須田さんは予測します。
最終的に補正予算が「どの規模で決着するのか」が、財務省との力関係だけでなく、高市政権の今後の命運、さらには近い将来あり得る解散総選挙の行方にも大きく影響してくる――この動画は、そのような視点から補正予算と官僚機構の動きを読み解いた内容になっています。
清澤のコメント:確かに的をついた評価です。大蔵大臣の片山さんも強力な人事ですから、高市首相の意図が財務省をねじ伏せることに期待します。




コメント