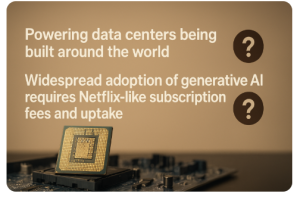 世界の半導体産業の将来はどうなるのか
世界の半導体産業の将来はどうなるのか
――エミン・ユルマズ氏の懸念と、それに対する見方
最近配信されたエミン・ユルマズ氏と高須院長の対話では、半導体産業の将来に関して二つの大きな懸念が示されました。ひとつは、世界中で建設が進むデータセンターに必要な電力が確保できないのではないかという問題。もうひとつは、生成AIを世界に広く普及させて投資を回収するには「Netflix並みの月額課金と普及率」が必要だが、それは非現実的ではないかという指摘です。これらは確かに説得力のある論点ですが、同時に反対側の視点から見れば、必ずしも悲観一色とは言えない面もあります。
まず、データセンターの電力問題についてです。AIモデルは急速に巨大化し、運用に必要なGPUサーバーは膨大な電力を消費します。欧米では既に電力網の逼迫が課題になっており、電力が新たな「ボトルネック」になるとの指摘は妥当です。しかし、反論として重要なのは、電力消費を抑えるための技術革新が現在猛烈なスピードで進んでいることです。各社は省電力型のAI専用チップを開発しており、冷却方式では水冷・液浸冷却・海洋データセンターなどが導入されつつあります。さらに、北欧やカナダ、中東など電力の安定した地域にデータセンターを移す動きも盛んです。国家レベルでも原子力、とくに小型モジュール炉(SMR)が次世代の電源として重視されており、中長期的には電力の供給構造が大きく変わる可能性があります。電力不足が当面の制約であることは事実ですが、永続的な成長阻害要因になるとは限りません。
次に、AI普及の経済性についての懸念です。「Netflixのように世界数億人が月額課金しなければ回収できないのでは」という指摘は一見もっともらしく聞こえます。しかし、AIサービスの収益構造はNetflixとは本質的に異なります。AIは娯楽サービスではなく、企業の人件費・業務効率を直接置き換えるインフラであり、利用の中心は家庭ではなく企業です。実際、OpenAIやGoogleの企業向けサービスは高額であっても急速に普及しており、「企業ごとの導入」「利用量に応じたAPI課金」によって収益が積み上がる構造になっています。AIを支える半導体需要は、配信動画のような娯楽の普及率ではなく、社会全体の業務プロセスの改革に支えられるものですから、Netflix型の普及を前提に悲観する必要はありません。
半導体産業には、AIバブル崩壊や地政学リスクなど他にも不安がありますが、これらに対してもサプライチェーンの分散化や各国の産業政策の強化が進んでおり、楽観とまではいかないまでも、長期的に需要が大きく落ち込むと予測する理由は乏しいと言えます。むしろ私たちの生活や医療を含むあらゆる産業でAIが基盤技術として浸透していく以上、半導体産業は短期的な波をくぐり抜けながらも右肩上がりのトレンドを維持する可能性が高いと考えられます。
清澤院長のコメント
私自身、このブログ記事の作成にも有料版ChatGPTを積極的に活用し、その能力の高さには日々驚かされています。AIはもはや専門家の知的生産を支える重要な道具であり、こうした技術の進化が社会全体の効率を高めることを実感しています。半導体産業の将来には課題もありますが、AIの広がりを見ていると、私はむしろ成長への期待の方を強く感じています。




コメント