 神経多様性のある人にとっての「悲しみ」とは何か
神経多様性のある人にとっての「悲しみ」とは何か
― 長期悲嘆障害(PGD)をどう理解し、どう支えるか ―
私たちは大切な人を失ったとき、深い悲しみに包まれます。その悲しみは時間とともに形を変え、多くの場合は日常生活へと少しずつ戻っていきます。しかし、悲しみが長く続き、生活や心の働きに大きな支障をきたす状態があることも知られています。これが「長期悲嘆障害(Prolonged Grief Disorder:PGD)」です。
背景
米国精神医学会の診断基準DSM-5-TRでは、2022年にPGDが正式な診断名として加えられました。これは「普通の悲しみ」と「治療が必要な病的な悲嘆」との境界を明確にし、支援につなげる目的で導入されたものです。しかし著者は、自閉スペクトラム症(ASD)や知的発達障害(IDD)など、いわゆる神経多様性をもつ人々では、この境界線が非常に分かりにくいと指摘します。
目的
本論文の目的は、PGDという診断概念が、神経多様性のある人の悲嘆を正しく捉えられているのかを問い直し、見逃されやすい苦痛をどう理解し、どう評価すべきかを示すことにあります。
方法
この論文は臨床研究というより、症例の提示、既存研究の整理、精神医学・心理学の理論史(フロイトやボウルビィらの悲嘆理論)を踏まえた概念的・臨床的レビューです。ASDと軽度のIDDをもつ若者が母親を亡くした事例を通して、悲嘆がどのように表現され、どこで誤解されやすいかが丁寧に描かれています。
結果(論文の主張)
神経多様性のある人の悲しみは、言葉ではなく「行動」として現れることが少なくありません。引きこもり、不安の増大、睡眠障害、感情の爆発などがその例です。これらはしばしば「退行」や「別の精神疾患」と誤解され、悲嘆そのものが見過ごされてしまいます。
また、ASDやIDDの人にとっては、愛する人を失うことが「感情的な喪失」であると同時に、「生活を支えてくれていた存在を失う」という二重の喪失になる点も重要だと述べられています。
結論
著者は、PGDを「悲しみを病気にする診断」として恐れるのではなく、適切な支援につなぐための枠組みとして慎重に活用すべきだと結論づけています。そのためには、言葉だけに頼らず、その人の喪失前の状態と比べて何が変わったのかを丁寧に見る姿勢が不可欠です。
悲しみは必ずしも「乗り越える」ものではなく、共存しながら人を深くすることもある――この視点こそが、神経多様性のある人への理解と支援の出発点になると論じられています。
出典
Kerim M. Munir, MD, MPH, DSc.
“Recognizing Grief in Neurodiverse Minds.”
JAMA Psychiatry, Published online December 23, 2025.
doi:10.1001/jamapsychiatry.2025.4225
清澤のコメント
眼科診療でも、重い病気や家族の死をきっかけに心の不調が前景に出てくる患者さんに出会います。
「悲しみ方は人それぞれである」という当たり前の事実を、神経多様性という視点から丁寧に掘り下げた本論文は、専門分野を超えて多くの臨床家に示唆を与えてくれる内容だと感じました。悲しみを急いで治そうとする前に、まず理解し、寄り添う姿勢の大切さを改めて考えさせられます。


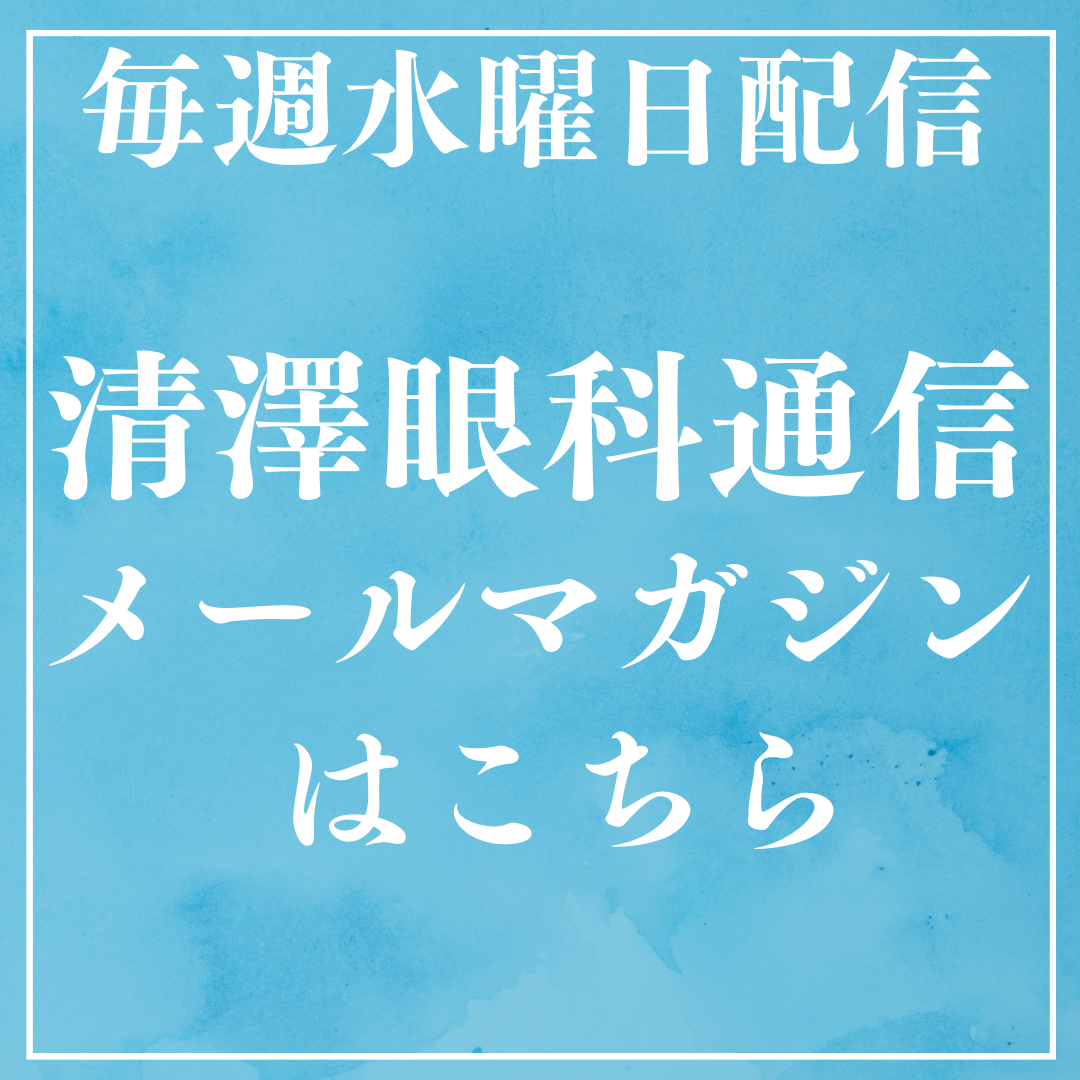

コメント