「イヤ汁」という言葉から考えたこと ― 若者との対話における自省
先日、「老害」と「イヤ汁」という言葉を扱った文章を読みました。(末尾参照)とくに「イヤ汁」という表現のニュアンスが印象に残りました。
この言葉は、エッセイストの酒井順子氏が著書『負け犬の遠吠え』の中で用いた表現だそうです。原文では、「不自然な時間的余裕」と「こじらせた自己表現欲」が混ざり合い、周囲にじんわりとした違和感や不快感を与える雰囲気、と描写されているそうです。
攻撃的でも露骨でもないのに、どこか重たく、押しつけがましく感じられる空気。そうしたものを比喩的に「汁」と呼んでいる点が、なかなか鋭い表現だと感じました。
記事では、中高年が若者と会話する際に、善意や共感のつもりで、自分の知識や経験を「質問の形」で次々と提示してしまう場面が紹介されていました。たとえば、若者が「コーヒーが好きです」と言ったときに、
「どこの豆?」「スペシャリティ?」「焙煎は?」
と畳みかけるように問いかけてしまう。形式上は質問でも、実質は自分の知識の披露になってしまうことがある、という指摘です。
書き手は、そこに悪意はないが、受け手によっては「知識で圧をかけられている」「試されている」と感じられる可能性がある、と述べています。そして、そのにじみ出る自己顕示の気配こそが「イヤ汁」なのだ、と。
読んでいて、私も少し考えさせられました。
年齢を重ねると、知識や経験が増えるのは自然なことです。また、仕事や子育てが一段落すると、趣味や学びに向き合う時間も増えるでしょう。それ自体は決して悪いことではありません。
しかし、その熱量を、相手が求めているかどうかを考えずに出してしまうと、意図せず「圧」になることがある。記事は、そうした点に注意を促していました。
さらに印象的だったのは、「語る快感に飲まれると、人は相手を見失う」という趣旨の一節です。確かに、自分の経験や考えを話すことは心地よいものです。とくに、ある分野に深く関わってきた人ほど、その思いは強いでしょう。
ただ、その快感が前に出過ぎると、対話ではなく一方通行になる。これは若者との関係に限らず、患者さんとの会話においても通じる点があるように感じました。
記事では、若者と向き合うときの基本として、「まず聞き役に回ること」が勧められていました。
「私のときはね」と言いかけたら少し飲み込む。
代わりに、「どんな感じ?」「困っていることある?」と尋ねてみる。
中高年が本当に強みとして持てるのは、知識量そのものよりも、むしろ「聞ける力」ではないか、という指摘です。
読後、私自身も少し自省の念を抱きました。実際の場で、知らず知らずのうちに“説明しすぎて”はいないか。相手の話を引き出す前に、結論を提示してしまってはいないか。
「老害」という言葉は刺激的ですが、「イヤ汁」という表現は、より静かに胸に刺さります。攻撃的ではない分、気づきにくいからこそ、注意が必要なのかもしれません。
世代を超えた対話が温かいものになるかどうかは、話す力よりも、聞く姿勢にかかっている。今回読んだ文章は、そのことを改めて考えさせてくれました。
自分の経験を語る前に、まず相手の言葉を受け止める。その小さな意識の積み重ねが、「イヤ汁」を出さない大人への一歩なのかもしれません。
参考文献:「面倒くさい大人」と思われてない? 若者と話すとき意識しておきたい「老害」と「イヤ汁」の視点。《語る快感》に浸っていないか要注意!(⇒原文にリンク)


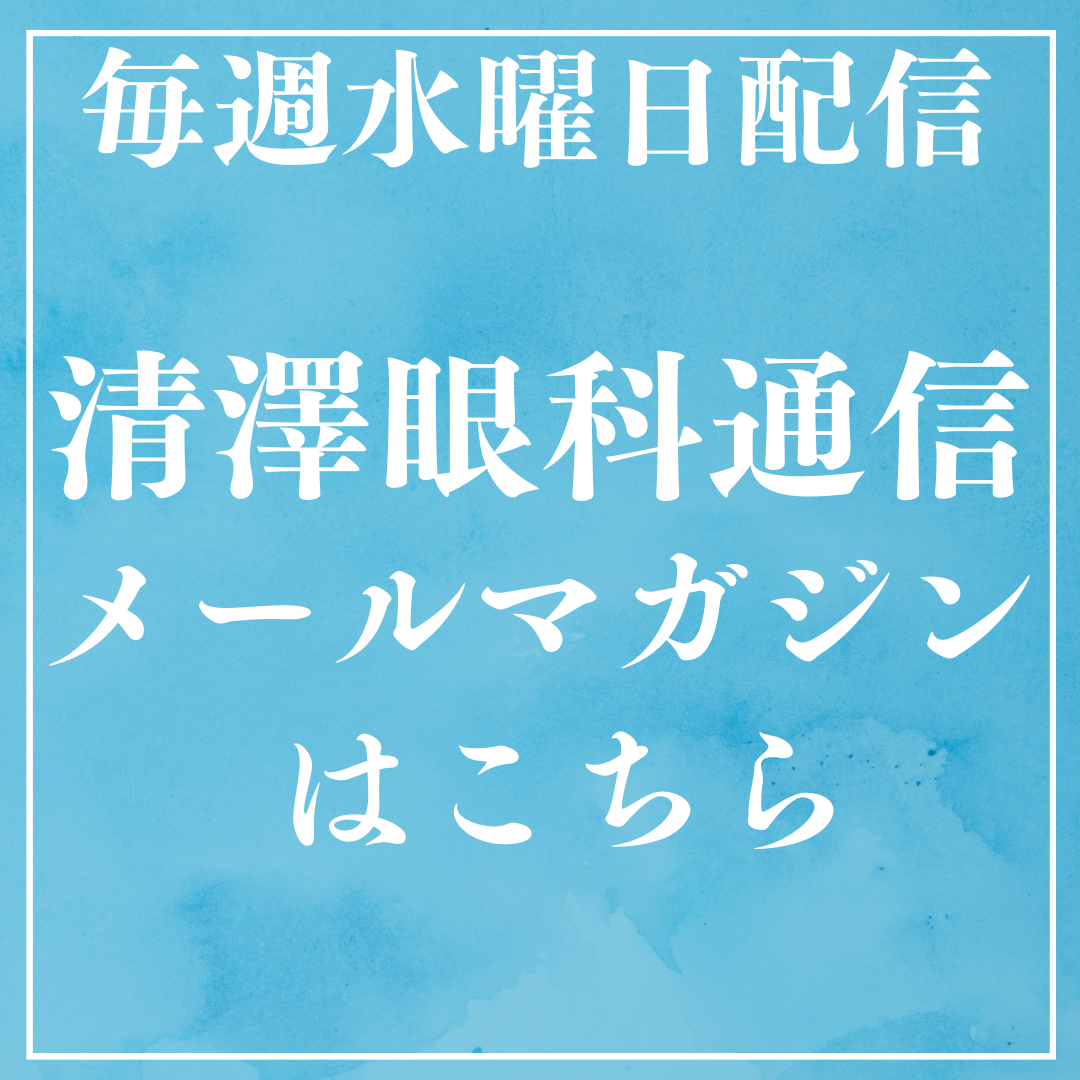

コメント