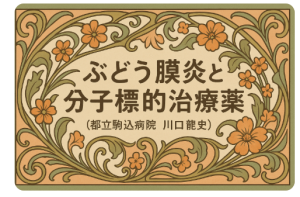 ぶどう膜炎と分子標的治療薬 ― (都立駒込病院 川口龍史)をわかりやすく抄出
ぶどう膜炎と分子標的治療薬 ― (都立駒込病院 川口龍史)をわかりやすく抄出
ぶどう膜炎とは、目の中にある「ぶどう膜」と呼ばれる組織に炎症が起こる病気です。原因はさまざまですが、特に感染を伴わない「非感染性ぶどう膜炎」は自己免疫の異常が深く関わり、再発を繰り返したり、視力を脅かしたりすることがあります。従来は副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬で炎症を抑えるのが標準治療でしたが、長期使用で白内障・緑内障・糖尿病悪化などの副作用が問題となり、薬を減らすと再発してしまうケースも少なくありませんでした。
近年、こうした課題に対応するために登場したのが「分子標的治療薬」です。これは炎症を引き起こす特定の分子(サイトカインなど)や免疫細胞の働きを狙い撃ちして抑える薬で、リウマチや炎症性腸疾患などで先に実用化されてきました。免疫学の進歩により、特にTh1細胞・Th17細胞と呼ばれるリンパ球がぶどう膜炎に関与することが分かり、それを踏まえた薬が開発されています。
主な分子標的薬
-
TNF-α阻害薬
炎症性サイトカインの代表格であるTNF-αをブロックします。インフリキシマブ(点滴製剤)やアダリムマブ(皮下注射)が代表で、ベーチェット病や難治性のぶどう膜炎に効果を示します。長期観察でも視力維持に役立つことが報告されていますが、結核や帯状疱疹の再活性化といった感染リスクがあるため注意が必要です。 -
IL-6阻害薬
炎症の慢性化に関わるIL-6というサイトカインを標的にします。トシリズマブ(点滴・皮下注)やサリルマブ(皮下注)があり、視力改善や黄斑浮腫の軽減が示されています。さらに新しい薬は眼内注射で直接投与する方法も研究されており、全身への副作用を減らす手段として期待されています。 -
抗CD20抗体薬
B細胞という免疫細胞を除去する薬で、もともとは血液がんに使われてきました。リツキシマブやオビヌツズマブが代表で、難治例のぶどう膜炎に有効との報告があります。 -
IL-17・IL-23阻害薬
乾癬や関節炎で用いられる薬で、炎症を引き起こすIL-17やIL-23を抑制します。ぶどう膜炎での使用はまだ研究段階ですが、新しい選択肢になり得ます。 -
JAK阻害薬
細胞内の情報伝達経路(JAK-STAT経路)を抑える飲み薬です。トファシチニブやバリシチニブなどがあり、リウマチなどで広く使われています。ぶどう膜炎に対しても効果が報告されていますが、感染症や心血管リスクへの注意が必要です。
今後の展望
これらの薬の登場により、患者さんごとに病態に合わせた「個別化医療」が可能になりつつあります。さらにAIを用いた診断支援やバイオマーカー(体内の炎症の指標)の活用によって、より適切な薬を選ぶ研究も進んでいます。眼科だけで判断するのは難しく、全身の免疫状態を管理する膠原病内科との連携が欠かせません。
まとめ
分子標的薬は、従来の治療で十分に抑えられなかったぶどう膜炎に新しい光をもたらしています。感染症などの副作用に注意しながらも、視力を守り、生活の質を向上させる可能性が広がってきました。今後さらに研究が進むことで、多くの患者さんにより安全で効果的な治療が提供されることが期待されます。




コメント