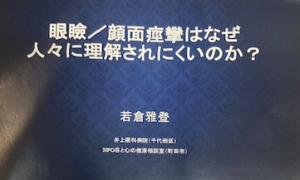 若倉雅登先生の講演を聴いて ― 眼瞼痙攣と光過敏に対する新たな視点
若倉雅登先生の講演を聴いて ― 眼瞼痙攣と光過敏に対する新たな視点
清澤のコメント:第19回例会交流会の講演ならびに交流会、今回の参加人数は会員71名、付添12名、医師・アドバイザー7名(内、お手伝い5名)、合計 90名でした。
◎ 18日北トピアで若倉雅登先生による眼瞼痙攣(ジストニア)に関するご講演を拝聴いたしました。その内容は、原発性・薬剤性の眼瞼痙攣に対する理解や、症状構成、診断の難しさ、さらに治療戦略まで、非常に整理されており、多くの示唆に富んでいました。特に「眼球使用困難症(visual disability without objective findings)」という概念と、それを「遅延型中枢性光過敏」として捉える視点は新しいものであり、今後の臨床と研究の両面で注目されるべき内容だと感じました。
■ 眼瞼痙攣が理解されにくい3つの理由
1. 医療者側の認識不足
多くの眼科医や神経科医は、研修段階で眼瞼痙攣について学ぶ機会が乏しく、顔面痙攣との違いや中枢性運動異常としての理解が浸透していません。過去には、ドライアイ、眼精疲労、眼瞼下垂、自律神経失調症、更年期障害などと誤診される例も多く、42〜69%の患者が“善意によるドライアイ治療”を受けていたとのことです。
また、眼瞼痙攣の症状は以下の3要素から構成されています:
-
① 運動障害(開瞼失行、瞬目異常、閉瞼固守)
-
② 感覚過敏(羞明、乾燥感、霧視、異物感など)
-
③ 精神症状(抑うつ、不安、不眠)
運動障害が目立たないと診断されにくく、特に薬剤性眼瞼痙攣では抗不安薬や睡眠導入剤(例:デパス、レンドルミン、マイスリー等)の長期使用歴が関与する場合があります。
2. 患者の訴えが正しく伝わらない
「まぶしい」「目を開けていられない」といった症状は、定量評価が難しく、医師側の理解を得にくいことがあります。講演では、来院理由の上位として「羞明(95%)」「目が開かない(92%)」「乾燥感(51%)」などが挙げられ、日常生活への深刻な影響が紹介されました。
また、歩行中に起きた支障の例として「電柱や人との衝突」「階段での恐怖」「外出困難」などが挙げられ、視覚情報処理の困難さが生活の質を大きく損なっていることが強調されました。
3. 光過敏脳の存在に対する理解不足
講演の中で特に印象的だったのは、「光過敏脳」という概念の提唱です。光過敏には以下の2つの型があります:
-
① 即時型光過敏:羞明や眼痛など、光を浴びた直後の症状
-
② 遅延型光過敏:羞明の訴えはなくとも、数時間後に頭痛、倦怠感、筋肉痛、めまいなどの全身症状が出現(中枢性光過敏)
こうした症状に対し、若倉先生は新たな治療法として「HDグラス(高濃度遮光眼鏡)」の使用を提案されています。これは、暗室並みの遮光効果を持つメガネで、1日3回、30分程度の使用を推奨。屋外での使用や、装用中の読書・PC作業などは避ける必要がありますが、使用中または使用後の症状改善を自覚した患者は試験中で80%を超えたとのことです。
■ 今後に向けて
現時点では、眼瞼痙攣に対する根本治療法は確立されていません。しかし、薬剤性の場合には原因薬剤の中止、ボツリヌストキシン療法、タッキング手術、感覚遮断や自己調整法、家族への理解など、多面的なアプローチが重要となります。
また、「眼球使用困難症」や「中枢性光過敏」という新しい病態概念が、今後医学界に浸透することで、これまで理解されにくかった患者の苦悩が適切に評価され、診療体制の改善や社会的支援の対象として認知されていくことが期待されます。




コメント