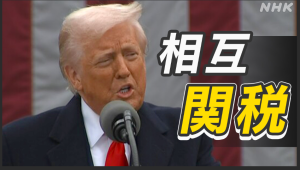 トランプ関税に違憲判決?最高裁で決まるその行方
トランプ関税に違憲判決?最高裁で決まるその行方
2025年8月29日、米ワシントンの連邦巡回区控訴裁判所が注目すべき判断を示しました。トランプ大統領が導入した「相互関税(reciprocal tariffs)」を含む一部の関税措置について、下級審の「違憲・違法」とする判決を支持したのです。司法が「大統領権限の乱用」に再びストップをかけた形になります。
■ なぜ「違憲」とされたのか
これらの関税は、1977年制定の国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に発動されました。この法律は「緊急事態において輸入を規制する」権限を大統領に与えています。しかし裁判所は「関税を新たに課す権限までは与えていない」と判断しました。つまり、「規制」と「課税」は別物であり、大統領が独断で税を課すのは行き過ぎだと結論づけたのです。
また、合衆国憲法では「関税を含む税の制定は議会の専権事項」とされています。大統領が議会の承認なしに課税権を行使するのは、三権分立の原則に反する、という法理も確認されました。
■ 判決が出ても関税はすぐには消えない
「違法」とされたからといって、直ちに関税が撤廃されるわけではありません。裁判所は「最高裁での審理を待つ間、2025年10月14日までは効力を維持する」と猶予を設けました。つまり、実際に関税が廃止されるかどうかは、この先の最高裁判決に委ねられています。
■ 今後の展開と可能性
政権側はすでに最高裁へ上告する方針を示しており、最終判断は連邦最高裁が下します。ここで「大統領にそのような関税権限はない」と認められれば、トランプ大統領が進めたような広範な関税措置は無効となり、事実上「トランプ関税」が消える可能性が出てきます。逆に最高裁が「大統領の権限」と認めれば、今後も同様の措置が続けられることになります。
なお、今回争われているのはIEEPAに基づく関税に限られます。鉄鋼やアルミにかけられた別法(通商拡大法232条など)による関税は、今回の判決の直接の対象ではなく、引き続き有効と見なされています。
■ 眼科院長の立場からの比喩
この問題は、医療に例えるとわかりやすいかもしれません。点眼薬の処方は医師の権限ですが、その薬自体は国家の承認を受けて初めて使えるものです。もし医師が「独自の判断で未承認薬を患者に投与する」とすれば、それは法律違反になります。今回の関税も、大統領が「議会を飛び越えて勝手に税を課した」ことが問題視されたと考えると理解しやすいでしょう。
■ おわりに
今回の判決は「大統領権限の範囲」を問い直す重要な事件です。関税という経済政策の問題でありながら、実際にはアメリカの憲法や三権分立のあり方に直結しています。現時点では関税は存続していますが、最終的に「なくなるかどうか」は最高裁の判断次第です。
私たちが注目すべきは、「法の支配」が経済や政治にどう作用するのかという点です。眼科診療においても「エビデンスに基づいた医療」が患者さんを守る基盤であるように、国家においては「憲法と法」が国民を守る基盤となります。最高裁の結論が出るその日まで、この問題は国際社会にとっても重要なニュースであり続けるでしょう。




コメント