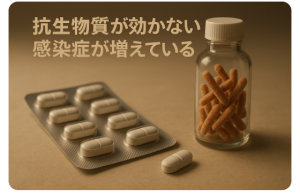
近年、世界中で「抗生物質が効かない感染症」が増えています。抗生物質は細菌感染症を治療するための大切な薬ですが、使えば使うほど耐性菌が現れ、効かなくなってしまうのです。WHOも「人類にとって最も大きな脅威のひとつ」と警告しています。
小児医療での課題
米国シカゴの小児病院で抗菌薬管理を担当するパテル医師は、「抗生物質は必要な時だけ、できるだけ狭い範囲の薬を選び、感染が治ればすぐに中止すること」が大切だと強調しています。
しかし現場では、肺炎や尿路感染症で第一選択薬が効かない事例が増えています。健康な子どもでさえ、食品や環境を介して耐性菌に感染することがあるのです。その結果、より強い抗生物質を使わざるを得ず、副作用リスクが高まり、さらに新たな耐性菌が増える悪循環に陥ります。
また「抗生物質を処方してほしい」という家族からの要望も医師を悩ませます。風邪の多くはウイルス感染であり、抗生物質は不要ですが、医師は水分補給や解熱剤などの支持療法を丁寧に説明し、必要な場合は再診を約束することで、過剰処方を防ごうとしています。
眼科における抗生物質の使い方
抗生物質耐性は全身感染症だけでなく、眼科領域でも重要な問題です。
- 結膜炎
子どもの急性結膜炎は多くがウイルス性であり、抗生物質は不要です。それでも「目やにが出ているから」と抗菌点眼薬を希望される方が多く、安易に処方すると耐性菌増加につながります。細菌性かどうかを見極め、必要な時にのみ点眼することが原則です。 - 角膜潰瘍
細菌性角膜潰瘍では、視力を守るために抗菌薬の適切な選択と投与が不可欠です。フルオロキノロン系など広域抗菌薬の点眼が主力ですが、耐性菌が増えると効果が低下し、失明の危険が高まります。培養検査を行い、原因菌に応じた狭域の薬剤へ切り替える努力が求められます。 - 白内障手術などの予防投与
手術後感染(眼内炎)は最重篤な合併症のひとつです。その予防に抗菌点眼や抗菌薬注射が使われますが、不必要に長期点眼を続けると耐性菌を生み出します。近年は「術前後の短期間で十分」とする考え方が主流になっています。
このように眼科でも「抗菌薬は万能ではない」ことを患者さんに理解いただくことが大切です。
新しい薬と診断法の開発
研究の現場では、新しい抗菌薬の開発が進んでいます。ロシュとハーバード大学が共同開発中の「ゾスラバルピン」は、耐性菌アシネトバクターを標的とする新しい薬剤で、最終段階の臨床試験に入っています。こうした薬が実用化されれば、眼感染症にも応用される可能性があります。
また、より迅速に原因菌を特定できる診断検査が求められています。角膜潰瘍などでも、培養結果が出るまで数日を要するため、経験的に広域薬を投与するしかありません。もし24時間以内に病原菌が特定できれば、より狭い範囲の薬に切り替えられ、耐性化を防げるでしょう。
さらに人工知能(AI)が、検査所見や臨床データをもとに「抗菌薬が必要かどうか」「どの薬を選ぶべきか」をリアルタイムで助言する未来も見えてきています。
医療と社会全体での取り組み
抗生物質耐性は、医療現場だけの問題ではありません。畜産や農業での抗菌薬使用が耐性菌を生み、それが食品や水を介して人間に感染することもあります。人類全体で「抗菌薬を守る」という意識を共有する必要があります。
まとめ(清澤院長コメント)
抗菌薬は眼科でも日常的に用いる薬であり、角膜潰瘍や術後感染予防などでは欠かせません。しかし安易な点眼処方や長期投与は耐性菌を生み、未来の治療手段を失う危険につながります。患者さんには「必要なときに必要なだけ」という考えを共有していただきたいと思います。抗菌薬を守ることは、自分と子どもたちの視力を守ることにもつながるのです。
(出典:Medscape Medical News, 2025年8月12日 Erin Digirolamo 記事より要約)




コメント