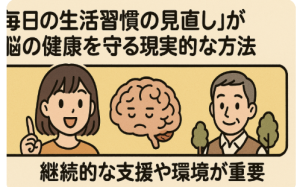 先日もPOINTER研究の論文を紹介(この記事の末尾参照)しましたが、この記事を読み直してみるとさらにわかりやすく説明できそうです。
先日もPOINTER研究の論文を紹介(この記事の末尾参照)しましたが、この記事を読み直してみるとさらにわかりやすく説明できそうです。
薬に頼らず脳の健康を守るには?──米国POINTER研究が示した「生活習慣改善」の力
認知症予防において、「生活習慣の改善」がどれほど効果があるか?
これは高齢化社会を迎える日本にとっても非常に重要な課題です。アメリカで実施された大規模な臨床研究「US POINTER試験」がこの問いに正面から挑み、注目すべき成果を示しました。
背景:薬だけでは防げない認知機能低下
アルツハイマー型認知症(AD)などの認知症に対する治療薬の研究は進んでいますが、現段階では完全な予防は難しく、特に血管性要因などを含む「複合的な病態」には薬物療法だけでは限界があります。
そこで、「非薬物的なアプローチ」=生活習慣の改善に注目が集まり、2015年にはフィンランドのFINGER研究が、生活習慣の改善によって認知機能が維持される可能性を世界に示しました。
その流れを受けて、米国版FINGERともいえる「US POINTER(Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention)試験」が行われました。
目的と方法:構造化された生活改善 vs 自己流の生活改善
POINTER試験は、認知症リスクのある60〜79歳の2111名(平均年齢68.2歳)を対象に、2年間の生活改善プログラムを行ったランダム化比較試験です。
参加者は以下のような条件を満たしていました:
-
運動不足
-
食生活の乱れ
-
家族歴、心血管リスク、人種・民族などによるリスク要因
この参加者を2群に分けました。
-
構造化された多面的介入群(Structured group)
- 運動(中〜高強度)
- MIND食(地中海式+DASH式の脳に良い食事)
- 認知トレーニング
- 社会的交流
- 血管リスクのモニタリング
※専門スタッフによる継続的な支援あり -
自己流の生活改善群(Self-guided group)
- 同様の内容を自分で実施(支援なし)
結果:支援付きプログラムがより高い効果
2年間の追跡で、両群ともに認知機能スコアは向上しましたが、その伸び幅に違いがありました。
-
構造化介入群:年あたり 0.243SDの改善
-
自己流群:年あたり 0.213SDの改善
-
差:0.029SD分の差が統計的に有意(P=0.008)
特に、認知機能の低い人ほど介入の効果が大きく、またAPOE ε4(アルツハイマーのリスク遺伝子)を持っていても持っていなくても同様の効果が見られました。
副作用についても、重大な有害事象は両群とも大きな差はなく、安全に実施できたとされています。
コメント:日常生活の質が「脳の健康」を守る鍵
この研究は、薬に頼らず、「毎日の生活習慣の見直し」が脳の健康を守る現実的な方法であることを示しています。
特に重要なのは、「自己流」ではなく継続的な支援や環境があると、より効果的になるという点です。日本でも、地域ぐるみでの取り組みや、医療機関での介入支援の重要性が高まるでしょう。
参考文献:
Baker LD, Espeland MA, Whitmer RA, et al. Structured vs Self-Guided Multidomain Lifestyle Interventions for Global Cognitive Function: The US POINTER Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online July 28, 2025. doi:10.1001/jama.2025.12923




コメント