当医院では臨床心理士によるカウンセリングを通常の眼科的な治療に合わせて必要に応じて取り入れています。その特殊が以来の頻度は月に一度です。
目の疲れや痛みを訴えても、検査で異常が見つからない――このような「眼精疲労」や「眼痛」は、現代では決して珍しくありません。パソコンやスマートフォンの使用時間が長く、ストレスの多い生活の中で、目の症状に「こころ」の要素が関わっていることが分かってきています。そこで注目されているのが、臨床心理学的なカウンセリングによるサポートです。ここでは、心理学の立場から行われる主な方法を紹介します。
① 認知行動療法(CBT)
最もよく用いられるのが「認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)」です。これは、「考え方」と「行動」のパターンを整理し、ストレスや症状を悪化させている心理的要因に気づき、それを現実的で前向きな形に修正していく方法です。
例えば、「仕事中に少しでもかすむと、不安でたまらない」「痛みを感じたらもう仕事ができない」といった極端な思考を和らげ、段階的に安心感を取り戻す練習をします。
また、目を酷使しない生活リズムを整える行動計画(休憩時間、照明、姿勢など)も一緒に見直します。CBTは数回の面談でも効果が見られることが多く、心因性の眼精疲労や自律神経の乱れを伴う症状にも有効とされています。
② マインドフルネス瞑想法
「今、この瞬間」に意識を向けるマインドフルネスの練習も広く使われています。目の痛みを感じた時、「痛みをなくそう」と焦るのではなく、「いま痛みを感じている自分をそのまま観察する」ことを学びます。
こうすることで、痛みへの過敏な反応(不安や緊張)を和らげ、自律神経のバランスを整えることができます。呼吸や体の感覚に意識を向ける短い瞑想を毎日数分行うだけでも、リラックス効果があり、慢性的な疲労感や不眠の改善にもつながります。
③ バイオフィードバック療法
もう一つの実践的な方法が「バイオフィードバック」です。心拍、筋肉の緊張、皮膚温などの生理的反応をセンサーで可視化し、患者自身がその状態を見ながらコントロールする訓練を行います。
眼精疲労では、特に「前頭部や眼周囲の筋緊張」を緩める練習が重要です。自分の緊張状態をリアルタイムに知ることで、リラックスする方法(深呼吸、姿勢の調整など)を身につけることができます。
④ 自律訓練法・リラクゼーション法
ドイツの精神科医シュルツが開発した「自律訓練法」も、眼の疲労や痛みに伴う体の緊張を和らげる目的で使われます。「手が重たい」「温かい」といった感覚を自己暗示的に繰り返すことで、心身を穏やかに落ち着けます。
また、筋肉の力を意識的に抜く「漸進的筋弛緩法(PMR)」や、穏やかな音楽や呼吸を使ったリラクゼーションも併用されます。これらの方法は、自宅でも練習できる点が魅力です。
⑤ 支持的カウンセリングと心理教育
心理士が話を丁寧に聴き、安心できる場を提供する「支持的カウンセリング」も欠かせません。
「疲れを感じてもよい」「焦らずに回復を待つ」などの言葉を通じて、過剰な自己批判や完璧主義的な思考を和らげることができます。
さらに、ストレスと身体症状の関係、自律神経の働き、睡眠や生活習慣の重要性などを説明する「心理教育」も合わせて行われ、患者さん自身が症状のメカニズムを理解できるようにします。
まとめ
眼精疲労や眼痛は、単に「目の使いすぎ」だけでなく、「ストレス」「緊張」「不安」などの心理的要因が重なって生じることがあります。臨床心理学的カウンセリングでは、こうした心と体の関係を整理し、無理のない生活リズムと穏やかな思考を取り戻すお手伝いをします。
眼科での検査で大きな異常がない場合でも、心理士との面談を通して症状が軽くなる方は少なくありません。心の緊張が和らぐと、目も自然に休まりやすくなります。
参考:日本心理臨床学会『臨床心理士の仕事』(金剛出版)、厚生労働省ストレス対策指針、American Psychological Association “CBT and Somatic Symptoms”。

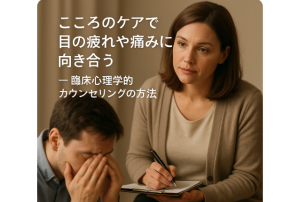



コメント