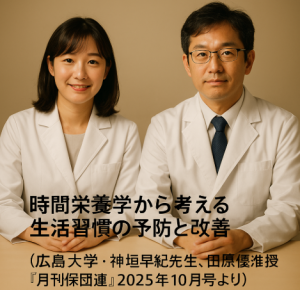 時間栄養学から考える生活習慣の予防と改善
時間栄養学から考える生活習慣の予防と改善
(広島大学・神垣早紀先生、田原優准教授『月刊保団連』2025年10月号より)
① 「いつ食べるか」で考える時代
栄養学といえば「何を、どれだけ」食べるかが中心でしたが、近年は「いつ食べるか」が注目されています。体の代謝やホルモン分泌には24時間のリズムがあり、朝・昼・夜で同じ食事をしても反応が違います。朝は糖の代謝が良く、夜は脂肪をため込みやすいなど、体内時計が関係しているのです。食事のタイミングを整えることは、生活習慣病の予防や改善につながるとされています。
② リブレとAIによる栄養学の進化
血糖センサー「リブレ」などの機器を使えば、食後の血糖変化をリアルタイムに見ることができます。AI解析を組み合わせると、個人ごとの「食べ方の癖」や「最適な食事時間」を見つけることが可能になります。これにより、一律の食事指導ではなく、一人ひとりに合った食事リズムを設計する「個別化栄養」が現実のものになりつつあります。科学の進歩で、栄養学はまさに“あなた専用の食習慣”を作る時代に入っています。
③ 食べる時間が血糖値を左右する
朝に食べた糖質はスムーズに処理されますが、夜遅くに食べると血糖が上がりやすくなります。これは夜になるとインスリンの働きが弱まるためです。したがって、夕食を早めにとる、夜食を控えるなどの工夫が大切です。朝食を抜くと体のリズムが乱れ、昼や夜の血糖値が上がりやすくなる傾向もあります。血糖コントロールのためには「時間の整った食事リズム」を意識することが第一歩です。
④ 食事の回数は少ないほど良いのか?
「食事を減らせば健康にいい」と思いがちですが、極端な少食は逆効果です。食事の回数が少なすぎると、一度に血糖が急上昇しやすくなります。逆に間食が多すぎても血糖変動が続き、体が休まりません。最近は「時間を決めて食べ、夜間はしっかり空ける」方法が注目されています。つまり、食事回数を減らすのではなく、体内時計に合ったリズムで食べることが重要なのです。
⑤ 昼食抜きの落とし穴
忙しさで昼食を抜く人が増えていますが、これは代謝を乱す原因になります。昼を抜くと、夕食で血糖が急上昇しやすくなり、脂肪をため込みやすくなります。また、昼食は体内時計をリセットする役割があり、抜くと午後の集中力も低下します。体を整えるためには、昼食を抜かず、適量をゆっくり食べることが基本です。昼をしっかりとることが、結果的に夜の過食を防ぐ近道になります。
⑥ 時間・質・量を人ごとに最適化
食事の「時間」「質」「量」は人によって最適バランスが異なります。朝型の人と夜型の人では、最も代謝が良い時間帯が違うのです。大切なのは、自分の生活リズムを知り、朝はしっかり、夜は控えめに、という自分流の型を作ることです。AIや血糖モニターを活用すれば、自分に合った食事時間を見つける手助けになります。「時間栄養学」は、健康を自分でデザインする新しい考え方です。
院長・清澤のコメント
時間栄養学は、眼科疾患にも関係する糖代謝や血管機能を整える重要な視点です。夜遅い食事や不規則な生活が続くと、糖尿病網膜症やドライアイなどにも影響します。私自身も夕食を早めにとり、睡眠前の間食を避けるように心がけています。皆さんも「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」にも目を向けて、体と目の健康を守りましょう。




コメント