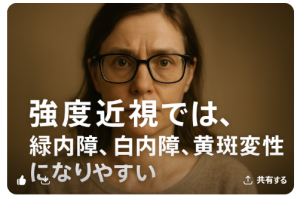 中高年の強度近視とその合併症
中高年の強度近視とその合併症
強度近視の定義
「強度近視」とは、近視の中でも特に度数が強く、眼鏡やコンタクトレンズの度数で-6D以上、あるいは眼軸長(眼の奥行き)が26.5mm以上の場合を指します。中高年になると、若い頃からの強度近視に加えて加齢変化が重なり、さまざまな眼疾患を合併しやすくなります。そのため「近視が強いからメガネが厚いだけ」とは考えず、合併症のリスクに注意が必要です。
強度近視で起きやすい眼疾患と症状
① 緑内障
-
特徴:強度近視眼では視神経乳頭が変形しており、正常眼圧緑内障を発症しやすい傾向があります。
-
症状:初期は自覚症状に乏しく、気づかないうちに視野が欠けます。進行すると日常生活に支障をきたします。
-
治療:点眼薬による眼圧コントロールが基本。場合によってはレーザー治療や手術も検討します。
② 網膜剥離
-
特徴:近視が強いと眼球が長く引き伸ばされ、網膜が薄く弱くなります。そのため裂け目(網膜裂孔)ができやすく、そこから剥離が広がります。
-
症状:飛蚊症(黒い点が飛ぶ)、光視症(ピカッと光が見える)、視野の一部がカーテンのように欠ける。
-
治療:裂孔のみならレーザーで予防可能。剥離が進行すれば硝子体手術が必要です。
③ 近視性黄斑症(近視性黄斑変性)
-
特徴:黄斑部の網膜が萎縮し、場合によっては異常血管(脈絡膜新生血管)が生じます。
-
症状:物がゆがんで見える(変視症)、視力低下。
-
治療:脈絡膜新生血管が出現した場合は抗VEGF薬の硝子体注射が行われます。萎縮型には有効な治療が少ないため、早期発見が大切です。
④ 白内障
-
特徴:近視の人は若い頃から白内障が進行しやすく、中高年期には視力低下の大きな原因となります。
-
症状:かすみ、まぶしさ、眼鏡が合わなくなる。
-
治療:進行した場合は手術で人工レンズを挿入しますが、強度近視眼では眼球が長いため手術リスクがやや高い点に注意が必要です。
⑤ 加齢黄斑変性との鑑別
-
強度近視の黄斑部変化は、加齢黄斑変性と似た症状を示すことがあります。誤診を避けるため、OCT(光干渉断層計)などの詳細な検査が不可欠です。
注意点と生活上の心がけ
-
定期的な眼科受診
-
強度近視の方は、少なくとも年1回の眼底検査を受けることをお勧めします。OCTによる神経線維層の評価や視野検査も有用です。
-
-
症状の早期対応
-
飛蚊症や光視症が出たらすぐに受診。網膜裂孔・剥離の可能性があります。
-
-
適切なメガネ・コンタクトの使用
-
過矯正は眼精疲労の原因となります。視力だけでなく、見え方の快適さも考慮して調整しましょう。
-
-
生活習慣の工夫
-
十分な睡眠、バランスのよい食事、適度な運動が眼の健康にも寄与します。
-
喫煙は血流を悪化させ、網膜疾患のリスクを高めるため控えることが望ましいです。
-
まとめ
中高年の強度近視は単なる「度数の強い近視」ではなく、緑内障、網膜剥離、近視性黄斑症、白内障など、視力に重大な影響を及ぼす合併症を引き起こしやすい状態です。自覚症状が出てからでは手遅れになることもあるため、定期的な検診と早期発見・治療が何より大切です。
自由が丘清澤眼科では、OCTや視野検査を組み合わせ、強度近視患者さんのリスク管理を行っています。ご自身やご家族に強度近視がある場合は、ぜひ定期的なチェックを受けるようにしてください。




コメント