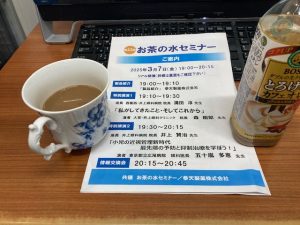 小児の近視管理新時代:最先端の予防と抑制治療を学ぼう:を第23回お茶の水セミナーで聞いてきました
小児の近視管理新時代:最先端の予防と抑制治療を学ぼう:を第23回お茶の水セミナーで聞いてきました
(演者:都立広尾病院 (東京科学大学)五十嵐多恵先生)
清澤のコメント:自由が丘清澤眼科でも東京科学大学(旧東京医科歯科大学眼科)とも連絡を取りながら保険診療の他に、小児の近視治療に対するオルソケラトロジー治療と低濃度アトロピン治療という保険外診療も手掛けています。ご講演は現在の治療法をベスト、ネクストベスト、などに分類され、ご講演テンポも良く、大変参考になりました。皆様の参考にもなればと考えて聴講印象記を記載しました。
ーーーーーーー
1. 近視の現状と重要性
-
小学生の約40%、中学生の約60%、高校生の約70%が近視を有している。
-
年齢別のカットオフ値を用いて、前近視(プレマイオピア)として扱う概念がある。
-
近視進行予防に関する情報はYouTubeなどでも紹介されている。
-
強度近視の約20%は遺伝性であり、基礎疾患を除外した上で近視治療を検討する。
-
本講演では、それ以外の近視の進行予防に焦点を当てる。
2. 近視進行の50%抑制が可能な「ベスト」な治療法
-
低濃度アトロピン点眼
-
LAMP study(Ophthalmology誌)によると、
-
0.01%アトロピンで30%抑制
-
0.02%アトロピンで43%抑制
-
0.05%アトロピンで67%抑制
-
-
アトロピン治療は中止するとリバウンドが強く、近視が再び進行する可能性がある。
-
副作用(散瞳・調節障害)が少なく、長期間使用が可能。
-
-
近視進行管理眼鏡
-
例:ミオスマート(HOYA社)、Stellest(エシロール社)。
-
処方時には 瞳孔間距離(PD)を左右別々に記載し、
-
製品名の指定を要す。
-
フィッティングパラメータの記載 が必要。
-
-
-
近視抑制用ソフトコンタクトレンズ
-
マイサイト(MiSight)、アキビューアビリティー、シードワンデー、バイオフィニティ などが今後市場に登場予定。
-
-
オルソケラトロジー(ナイトレンズ)
-
夜間装用し、角膜の形状を一時的に変化させることで、日中裸眼で過ごせる。
-
近視進行を約50%抑制する効果。
-
感染リスクを管理するため、装用・洗浄指導が重要。
-
3. 近視進行の30%抑制が期待される「ネクストベスト」
-
0.025%アトロピン点眼
-
参天製薬が販売準備中の リジュセアミニ(アトロピン0.025%)。
-
0.02%アトロピン点眼液は「ベスト」に近い抑制効果を示す。
-
現在、国内の約1300の医療施設がシンガポールから輸入したアトロピン点眼を使用している。
-
0.05%アトロピンは世界的に製造されていない。
-
-
多焦点ソフトコンタクトレンズ(デュアルフォーカスレンズ)
-
周辺視のデフォーカスを利用し、眼軸長の伸長を抑制する。
-
近視進行抑制効果は約45~50%。
-
日本では使用可能な製品が限られるが、将来的に選択肢が増える見込み。
-
現在の候補:バイオフィニティ、ワンデーイードフ。
-
-
特殊眼鏡(デフォーカス眼鏡)
-
例:MIYOSMART(ホヤ社)、Stellest(エシロール社)。
-
周辺ぼかし設計により、小児の近視進行抑制効果が報告されている。
-
4. 近視管理の新たな可能性:「ベスト超え」への期待
-
レッドライト治療(赤色光治療)
-
強度近視に対して良好な抑制効果を示す。
-
週4回程度の治療が推奨される。
-
しかし、 レッドライトの長期的な影響についての研究が不十分。
-
近視治療の先進国である 中国では、新規のレッドライト治療機器の開発が一時的にストップされている。
-
5. 近視管理のサポートツール
-
メニコン社が近視管理用手帳を配布。
-
医療機関レベルでの利用が可能であり、治療の経過を記録することで、より適切な近視管理が期待できる。
6. まとめ
-
近視は小児期において急速に進行し、放置すると強度近視へと進展する可能性がある。
-
近視管理には 環境改善(戸外活動の推奨、デジタルデバイスの使用制限) と 適切な治療(アトロピン、オルソケラトロジー、特殊眼鏡、コンタクトレンズ) の組み合わせが重要。
-
近視抑制治療は 「ベスト」・「ネクストベスト」・「ベスト超え」 という3段階に分類できる。
-
今後の研究や技術開発によって、より効果的な治療法が登場する可能性がある。
小児の近視進行を抑制するため、最新の知見を活用し、最適な治療を提供していくことが求められる。




コメント