日本の「ゾンビ企業」から学ぶ:アメリカ経済への警鐘;記事採録
低金利は一見やさしい処方箋。しかし日本が経験したように、企業を甘やかす長期の金融緩和は経済の体力を奪う。今、米国にも同じ影が迫っている。
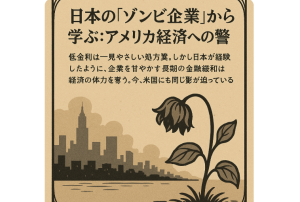 世界経済の行方を占ううえで、日本の過去が再び注目されています。ブルームバーグのコラムニスト、アリソン・シュレーガー氏は「日本の経験こそ、これからのアメリカ経済への警鐘である」と述べています。テーマはずばり、“金利を人為的に低く保ち続ける危うさ”です。
世界経済の行方を占ううえで、日本の過去が再び注目されています。ブルームバーグのコラムニスト、アリソン・シュレーガー氏は「日本の経験こそ、これからのアメリカ経済への警鐘である」と述べています。テーマはずばり、“金利を人為的に低く保ち続ける危うさ”です。
アメリカは今後10年、二つの難題に直面します。ひとつは金利の上昇、もうひとつは人工知能(AI)による産業構造の変化です。これらの課題に対して、政府がつい取りたくなるのが「低金利の維持」という処方箋です。金利を下げれば企業の資金繰りは楽になり、景気も一時的に刺激されます。ですが、そこに“落とし穴”があると筆者は指摘します。
日本の1980年代のバブル崩壊後がその典型でした。日本は景気を下支えするために、長期間にわたり金利を低く保つ「金融抑圧政策」と量的緩和を行いました。結果として、生活の安定は守られたものの、生産性の低い企業まで延命してしまい、「ゾンビ企業」と呼ばれる存在が増えたのです。採算の取れない事業が生き残ることで、新しい企業が成長する余地が奪われ、経済全体の活力が徐々に失われました。
いまアメリカでは、コロナ禍以降の財政出動と金融緩和によって、長期金利が上昇傾向にあります。住宅ローンの金利上昇で家計は苦しくなり、企業も借入コストの上昇に直面しています。政府の利払い負担も増大し、経済構造にひずみが生じています。この痛みを和らげるために、再び低金利政策をとる誘惑が高まっています。
しかし、金利を人為的に抑えれば、アメリカでも“ゾンビ化”が進む危険があります。金利が安ければ、経営体力の乏しい企業でも借入を続けることができ、本来なら市場から退場すべき企業が延命します。こうした企業が増えると、資金と人材が有望な新興企業に流れず、経済の効率性と成長力が失われていくのです。
トランプ前大統領は短期金利の引き下げを求め、現政権の財務長官ベッセント氏も長期金利の抑制を目指す姿勢を示しています。けれども、それをどう実現するのかは不透明で、安易な量的緩和(QE)の再拡大には慎重な意見もあります。実際、パンデミック期のQEは住宅市場を過熱させた後、インフレと急激な金利上昇を招き、財務省には含み損が生まれました。
このように、短期間の金利抑制策でも市場の歪みが生じるのです。もしそれが恒常化すれば、中央銀行の独立性が失われ、経済の健全な循環が壊れてしまう恐れがあります。
シュレーガー氏は最後にこう警告します。
「アメリカが大規模な金融抑圧に踏み込めば、日本と同じように“ゾンビ経済”を自ら招くことになる」。
日本の経験は、決して過去の物語ではありません。低金利という“ぬるま湯”の中で体力を失った経済の姿は、いまの世界が直面する鏡でもあるのです。
出典: Allison Schrager, A Zombie Economy Could Be America’s Future, Bloomberg Opinion, Oct. 14, 2025.




コメント