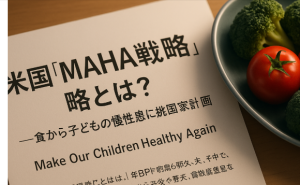 米国「MAHA戦略」とは?――食から子どもの慢性疾患に挑む国家計画
米国「MAHA戦略」とは?――食から子どもの慢性疾患に挑む国家計画
1. MAHA戦略の背景と目的
2025年9月、米国ホワイトハウスは「Make Our Children Healthy Again(MAHA)」という120以上の政策からなる国家戦略を発表しました。若い世代に拡大する肥満、糖尿病、心臓病などの慢性疾患の主因が「超加工食品(UPF)の過剰摂取」と「体を守る食べ物の不足」という二重の問題であると指摘し、これらを改善することを大きな目的としています。米国では心臓病の約半数、2型糖尿病の7割が食生活に起因するとされ、食の問題は医療の周辺ではなく“中心課題”と認識されています。
2. 超加工食品UPFへの対応と広告規制
MAHA戦略の柱は、まず国としてUPFの正式な定義を作り、表示・広告・公共調達などの基準に反映させることです。これまではUPFの基準が曖昧だったため、企業の自主基準に頼る部分が多く、消費者も判断しにくい状況でした。さらに、食品添加物の安全性審査として長年問題視されてきたGRAS制度(企業が自ら「安全」と判断すれば市場に出せる仕組み)を、FDAが必ず確認する形へ改革する方針も示されました。また、子ども向け食品広告の規制を強化し、テレビ・ネット・パッケージ・インフルエンサー動画など、多くがUPFを宣伝している現状を変えることを狙っています。企業の自主規制は効果が薄かったため、国による本格的な介入は環境を大きく変える可能性があります。
3. 医療と食を結びつける「Food is Medicine」
医療の中に栄養を組み込むことも大きな特徴です。医療機関での健康的な食事提供、糖尿病や心血管疾患患者への“医療食”の支給、医師への栄養教育の強化など、治療の一部として食を扱う動きが進められます。米国の低所得者向け食料支援SNAP(年間14兆円規模)についても、今後は果物・野菜・穀類など栄養価の高い食品により多くの予算を振り向ける方針が示されました。これは長年見送られてきた領域であり、もし実行されれば食生活格差の縮小にもつながります。
4. 外食・農業・研究投資の課題
米国では外食が最も栄養バランスが悪いとされており、MAHA戦略はレストランに子ども向け健康メニューの改善を「促す」姿勢を示していますが、まだ強制力は弱く象徴的な内容にとどまっています。また、栄養研究への政府投資は半世紀近く伸び悩んでおり、MAHA戦略は研究支援拡大を掲げるものの具体的な予算案は提示されていません。さらに、米国では農業補助金の多くがトウモロコシ・大豆などの作物に集中し、果物や野菜など健康的な食品は政策支援の対象外のままです。これに戦略が触れていない点は大きな弱点とされています。
5. 科学的矛盾と今後の展望
JAMA論評では、MAHA戦略にワクチンやフッ素など、科学的に確立した事実と異なる記述が含まれている点を問題視しています。また、所得・地域・人種などによる栄養格差への言及も弱く、研究費削減や医療保険制度の調整といった他の政府政策と矛盾する部分も見られます。それでも、UPF定義化、GRAS改革、広告規制、医療との統合、栄養教育の強化などは、米国の慢性疾患対策に対する本気度の表れであり、実行されれば国民の食環境に大きな変化をもたらす可能性があります。成功のためには、科学的な一貫性、十分な予算、政治的独立性が鍵とされています。
出典:Mozaffarian D, Callahan EA, Frist WH. Food and Nutrition in the MAHA Strategy—Promise and Peril. JAMA. Online published Nov 13, 2025. doi:10.1001/jama.2025.22358
清澤院長コメント:食が健康を左右するという考え方は眼科でも重要です。糖尿病網膜症や高血圧性眼底は生活習慣の影響が大きく、治療には患者さんの生活全体を理解する姿勢が欠かせません。MAHA戦略は極端に見える部分もありますが、日本でも食と健康を結びつけた医療の考え方が広がることを期待しています。




コメント