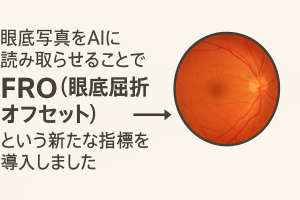 清澤のコメント:JAMA Ophthalmology(2025年6月5日)に掲載された招待解説「近視における球面当量と軸方向の長さを超えて」の要点を、素人にもわかりやすく要約しました。
清澤のコメント:JAMA Ophthalmology(2025年6月5日)に掲載された招待解説「近視における球面当量と軸方向の長さを超えて」の要点を、素人にもわかりやすく要約しました。
近視のリスク評価に新たな指標——FROとは?
近視(近くは見えるが遠くは見えづらい状態)は、東アジアを含め世界的に増加している重要な公衆衛生課題です。近視が強くなると、目の奥(後眼部)が引き伸ばされ、それにより網膜や脈絡膜に変化が生じ、視力に大きな影響を及ぼす可能性があります。たとえば、黄斑変性症、網膜剥離、緑内障などが挙げられます。
これまで近視の進行や合併症リスクの評価には、「眼軸長(目の前後の長さ)」や「球面等価屈折値(度数)」がよく使われてきました。しかし、これらの指標だけでは、眼の内部構造の違いや個々のリスクの差を十分に評価できないという課題がありました。
そこで今回、香港大学の研究チームは、眼底写真をAIに読み取らせることで「FRO(眼底屈折オフセット)」という新たな指標を導入しました。これは、「眼底写真からAIが予測した屈折値」と「実際の屈折値」のずれを示すもので、このずれが大きいほど、目の内部構造が一般的な近視のパターンから逸脱している可能性があるという考えです。
FROが捉える「目の奥の違い」
FROがマイナス方向に大きい場合、通常の近視よりも黄斑部が薄く、脈絡膜の血管が乏しいという特徴があることがわかりました。これは、将来的に黄斑変性や網膜萎縮といった深刻な合併症につながる可能性があります。
つまり、同じ近視度数や眼軸長の人でも、FROの値によってリスクが異なる可能性があるのです。FROを使えば、従来の検査だけでは見逃していた「ハイリスクな目」を早期に見つけ出せるかもしれません。
まだ乗り越えるべき課題も
このFROは、これまでとは違う視点から近視を評価できる画期的な方法ですが、いくつかの課題もあります。
- 今回の研究は白人の中年層が中心で、日本人を含む東アジアの若年層ではまだ検証されていません。
- FROが将来的な合併症リスクを予測できるかどうかは、長期的な追跡調査が必要です。
- 日常の診療に取り入れるには、「高リスク」とみなすFROの基準値を明確にしなければなりません。
- FROを他の指標(遺伝情報や生活習慣)と組み合わせて使うことで、より精度の高いリスク予測が可能になると期待されています。
今後への期待
FROは、AIを活用して普段の眼底写真から新しい情報を引き出し、患者ごとに最適な近視管理を可能にする「精密眼科(Precision Ophthalmology)」の一歩です。たとえば、将来近視性黄斑変性になりやすい人を早期に特定し、生活指導や治療計画を早めに立てることも可能になるかもしれません。
まだ臨床応用には検証が必要ですが、FROは近視管理の新たな道を拓く可能性のある有望な指標といえるでしょう。これからの研究と実臨床での導入に期待が集まっています。




コメント