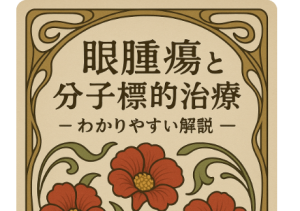 眼腫瘍と分子標的治療 ― わかりやすい解説(鈴木茂伸:国立がん研究センター)の内容を抄出
眼腫瘍と分子標的治療 ― わかりやすい解説(鈴木茂伸:国立がん研究センター)の内容を抄出
はじめに
「腫瘍(がん)」は遺伝子の傷によって細胞の制御が壊れることで起こります。その中で腫瘍の増殖に直接かかわる遺伝子を「ドライバー遺伝子」と呼びます。もしこの遺伝子やその産物を狙い撃ちできる薬があれば、がんの成長を抑えられる可能性があります。これが分子標的治療です。抗体薬(~mab)や小分子薬(~nib)に代表され、従来の「細胞分裂の速い細胞を一括して攻撃する抗がん剤」と違い、がん細胞をより選択的に狙うのが特徴です。副作用を減らしつつ効果を高めるという点で、がん治療を大きく変えてきました。
分子標的治療と免疫の関係
がん細胞は血管を新しく作り出し、酸素や栄養を得て増えます。その流れを止める「血管新生阻害薬」も眼科で広く使われており、これも分子標的治療の一つです。また、がんは免疫から逃れる仕組みを持っていますが、それを解除するのが免疫チェックポイント阻害薬(ICI)です。これも「特定の分子」を標的にしているため、広義の分子標的治療に含まれます。
眼腫瘍での応用例
眼にできる腫瘍は稀少疾患で、まだ研究途上ですが、いくつかの薬が使われはじめています。
-
皮膚・結膜の悪性黒色腫(メラノーマ)
BRAFという遺伝子変化がある場合、BRAF阻害薬とMEK阻害薬を併用する治療が有効です。日本でも承認済みの組み合わせがあります。また、免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ、キイトルーダなど)も有効性が示されています。
ただし日本人ではBRAF変化は約3割程度に限られ、結膜のメラノーマは遺伝子背景が異なりICIの効果も限定的です。 -
ぶどう膜悪性黒色腫(眼球内にできる黒色腫)
皮膚の黒色腫とは異なり、BRAF変化はほとんどありません。そのためBRAF/MEK阻害薬は効かず、免疫治療も効きにくいことが課題です。2021年にtebentafuspという新薬が生存率を改善したことが報告され、大きな希望となりました。ただし特定のHLA型を持つ人にしか使えず、日本人では対象が少数です。 -
眼内リンパ腫
中枢神経系リンパ腫の一種で、リツキシマブなどの抗CD20抗体薬を用いた治療が中心です。最近ではブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害薬が登場し、治験でも有効性が報告されています。今後の標準治療に組み込まれる可能性があります。 -
眼窩や眼付属器のリンパ腫
抗CD20抗体、抗CD19抗体に加え、抗体に放射線や抗がん剤を結合させた抗体薬物複合体(ADC)や、患者自身の免疫細胞を改変して戻すCAR-T療法も導入されつつあります。 -
網膜血管芽腫(VHL病に伴う良性腫瘍)
低酸素状態を感知する分子(HIF)が関係しており、これを抑える薬(belzutifan)が米国で承認されています。眼の病変への効果も期待されています。
治療の原則と注意点
がんの基本治療はあくまで「完全切除」です。薬物治療は切除できない場合や転移例に限られます。また、多くの分子標的薬は「この遺伝子変化がある患者にのみ使用可能」と決まっており、事前に遺伝子検査(コンパニオン診断)が必須です。さらに複数の遺伝子を一度に調べるがん遺伝子パネル検査も普及しつつありますが、保険診療では生涯1回のみ認められています。
まとめ
眼にできる腫瘍は稀少で、従来は手術や放射線が中心でした。しかし、分子標的治療や免疫治療の登場により、根治が難しかった症例にも新しい可能性が広がりつつあります。まだ国内で承認されていない薬も多いですが、今後の臨床試験やエビデンスの蓄積によって治療選択肢は増えていくでしょう。重要なのは「腫瘍の性質を遺伝子レベルで理解し、それに応じた薬を選ぶ」という考え方です。




コメント