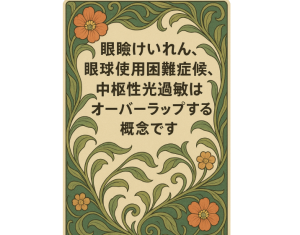 清澤のコメント:眼瞼痙攣のうちでも羞明が強くて目を開けていられないものを眼球使用困難症と呼びその原因としての機序を中枢性の光過敏であると考えるのが若倉雅登先生の考え方です。その発想を説明する記事が週刊新潮に掲載されるということの連絡をいただきました。
清澤のコメント:眼瞼痙攣のうちでも羞明が強くて目を開けていられないものを眼球使用困難症と呼びその原因としての機序を中枢性の光過敏であると考えるのが若倉雅登先生の考え方です。その発想を説明する記事が週刊新潮に掲載されるということの連絡をいただきました。
拡散希望
週刊新潮で「光過敏脳」取り上げられます!
皆様 週刊新潮(9月11日木曜発売)で、日本の光環境、それによる健康問題に一石を投じる「光過敏脳」が、私への取材をもとにした記事で紹介される予定です。
ご承知のように眼瞼けいれん、眼球使用困難症候群、中枢性(非眼球性)光過敏などは互いにオーバーラップする疾患概念です。日本にこうした異常がなぜ激増しているのかここ十数年ずっと考えてきました。薬物を含む様々な素因、誘因、原因があげられる中で、近年は特に日常の光環境(日光、LED照明など屋内照明、パソコンやスマホなどのバックライトなど)によるヒトへの健康被害が懸念されることを、私は機会あるごとに表明しています。また、目と脳の感覚過敏(中でも光過敏脳)がこれらの病気の中核をなすメカニズムだとの持論を「今、光過敏脳が危ない」(仮題)と題する一般書向け原稿に著し、出版社など何人かに見せておりました。ところが、内容は興味深いが、この問題を自分事と考えて本を手に取る人は少ないだろう(つまり売れないだろう)との意見が大勢で、書籍化は保留になっています。
そうした中で、この草稿を読んだあるジャーナリストにより、週刊新潮でこのテーマを取り上げるとの話が進み、上記のように9月11日発売の同誌で4ページにわたる「光過敏脳」の概要を紹介することが決まりました。
記事への反響が高く、連鎖すれば今日の光環境への関心や、光過敏脳で苦しむ方々への理解が深まり、公的対策への足掛かりともなるでしょう。もっと詳しく知りたい方々のためにと、一般向書籍の刊行が再浮上するかもしれません!?
そういうわけで、皆様には、是非記事をお読みいただき、SNS上などでの情報拡散、また(賛否どちらでも)ご意見を積極的に多数発信いただきたく、メールを差し上げました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
若倉雅登




コメント