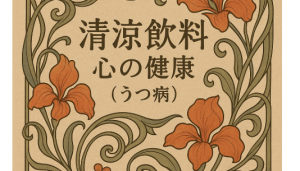 清涼飲料と腸内細菌、そしてうつ病
清涼飲料と腸内細菌、そしてうつ病
――女性に強く現れる関連と新しい予防の可能性
背景
炭酸飲料やジュースなどの「清涼飲料」は、身近で手軽に飲める一方で、肥満や糖尿病、心血管疾患といった生活習慣病と関連していることがよく知られています。ところが、最近の研究では「心の健康」、とくにうつ病との関連にも注目が集まっています。
過去の大規模調査では、清涼飲料をよく飲む人ほど抑うつ症状が強いことが指摘されてきましたが、その理由や体の中で起きている仕組みは分かっていませんでした。今回紹介する研究は、腸内環境(腸内細菌叢)がその鍵を握っている可能性を示しました。
研究の目的
この研究の狙いは次の2点です。
-
清涼飲料の摂取とうつ病(大うつ病性障害:MDD)の診断や症状の重さとの関連を明らかにすること。
-
その関連が腸内細菌叢、特に「エガーテラ(Eggerthella)」や「ハンガテラ(Hungatella)」という細菌の存在量の変化によって説明できるかどうかを検証すること。
方法
対象となったのはドイツで行われた多施設コホート研究「マールブルク・ミュンスター感情コホート」です。2014年から2018年にかけて、18〜65歳の大うつ病性障害(MDD)患者405人と健康な対照527人が参加しました。
患者は臨床的に診断されたもので、全体の約3分の2が女性でした。研究チームは清涼飲料の摂取量を調べ、うつ病の有無や症状の程度との関連を統計的に解析しました。さらに腸内細菌叢を測定し、清涼飲料 → 腸内細菌の変化 → うつ病、という因果関係が成り立つかどうかを「媒介分析」という方法で検証しました。
結果
-
清涼飲料をよく飲む人ほどMDDの診断を受けやすく、症状も重いことが分かりました。
-
この関連は特に女性で強く、飲料摂取量が多いほど抑うつ症状が悪化する傾向が明確に示されました。
-
女性では清涼飲料の摂取が「エガーテラ」という細菌の増加と関連しており、その結果としてうつ病の診断や症状の重さに結びついていました。媒介効果としては、診断の約3.8%、症状重さの約5%をエガーテラの増加が説明しました。
-
一方で「ハンガテラ」という細菌は有意な関与を示しませんでした。
つまり、清涼飲料を多く飲むことによって腸内環境が変化し、その一部がうつ病の発症や悪化に結びついている可能性がある、ということです。
意義と今後の展望
この研究は、清涼飲料とうつ病の関連を「腸内細菌」という新しい視点から裏付けた初めての大規模な調査といえます。
-
清涼飲料の過剰摂取を減らすことは、身体だけでなく心の健康を守る意味でも大切。
-
特に女性や若い世代に向けた教育・啓発が有効と考えられます。
-
将来的には腸内細菌のバランスを整えるような介入(プロバイオティクスや食事指導など)がうつ病予防や治療の一助となる可能性があります。
清澤眼科医のコメント
今回の研究で示されたのは「清涼飲料とうつ病の関連が、腸内細菌を介している可能性がある」という点です。では、何が悪いのでしょうか?
多くの清涼飲料は砂糖を多量に含んでいます。糖分の過剰摂取が腸内環境を乱し、特定の細菌の増加を招いている可能性は十分考えられます。一方で、人工甘味料を含む「カロリーゼロ飲料」でも腸内細菌叢に影響するという報告があり、糖だけが原因ではない可能性も否定できません。今後の研究が待たれるところです。
患者さんにこの結果をどう伝えるかですが、難しく説明する必要はありません。「清涼飲料を飲みすぎると体だけでなく心の調子にも悪影響を与える可能性があることが分かってきました。とくに女性では強い関連がみられます。水やお茶を中心にして、清涼飲料は時々楽しむ程度にしましょう」とお話しするのが現実的です。
このような生活習慣の工夫は、眼科の診療でも患者さんと共有できる健康情報のひとつだと考えます。
出典
Tanaraja SE, Ribeiro AH, Lee J, et al.
Soft Drink Consumption and Depression Mediated by Gut Microbiome Changes in Women.
JAMA Psychiatry. Published online September 24, 2025. doi:10.1001/jamapsychiatry.2025.2579




コメント